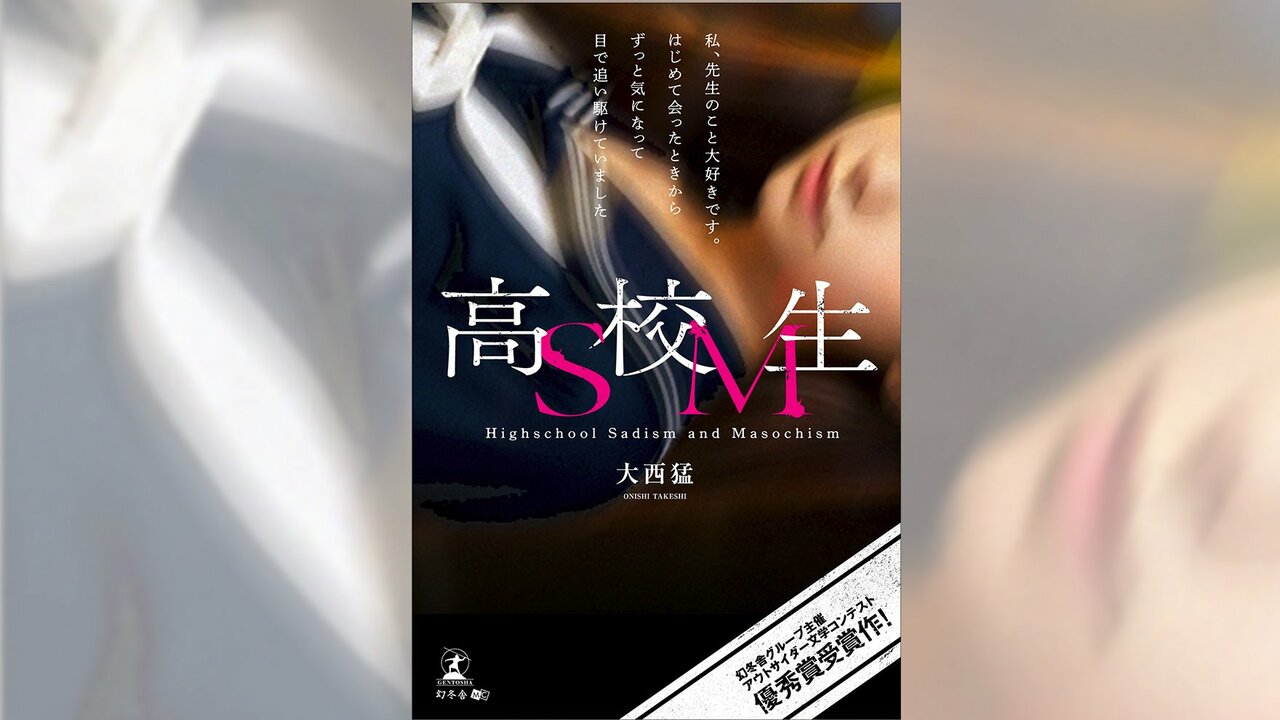3
私は気づくとあの人の後を追い駆けていた。あの人は廊下の端を生徒を避けながら歩いていた。私はあの人を追い抜き、その行く手を阻んだ。驚くあの人の顔は一ヵ月前と同じだった。
「先生、お久しぶりです」
私は一か月前なら眩しくて見られなかったあの人の顔を真正面から見つめた。
「おお、久しぶり」
あの人は私の顔を覚えていただろうか。夏休みの間一度でも私のことを思い出してくれただろうか。確かなのは今あの人の目は私に向けられているということだけだった。あの人はこの瞬間、私のものだった。
「夏休み、先生の教えてくれた『アメリカの悲劇』読みました。すごく面白かったです」
「全部読んだの?」
「はい。読みました」
あの人はそれを聞いて口元を緩めた。
「すごいな。大変だったでしょ?」
私は首を横に振った。きっと学校からの課題だったら、苦痛で仕方なかっただろう。でも、あの人に教えてもらったものなら楽しい以外の感情は生まれなかった。
「またおすすめの本とか映画、教えてください」
あの人はまだ私の知らない本をたくさん読んでいた。知らない映画もたくさん観ていた。私は知識を得ることで少しでもあの人に近づきたかった。あの人の考えていることを理解したかった。
私はあの人に勧められた本や映画はすべて読んで、観た。それ以外にも、図書館に通って気になる本は片っ端から借りた。知りたいという欲求はかつてないほど大きくなっていた。そして、知ることの喜びも。私は寝るのさえ惜しかった。
二学期の中間テストの世界史で、私は満点を取った。あの人はテスト用紙を返すとき、私にだけ「よくやったね」と言ってくれた。その一言で私の努力が認められた気がした。私は少しだけあの人に近づくことができのだ。