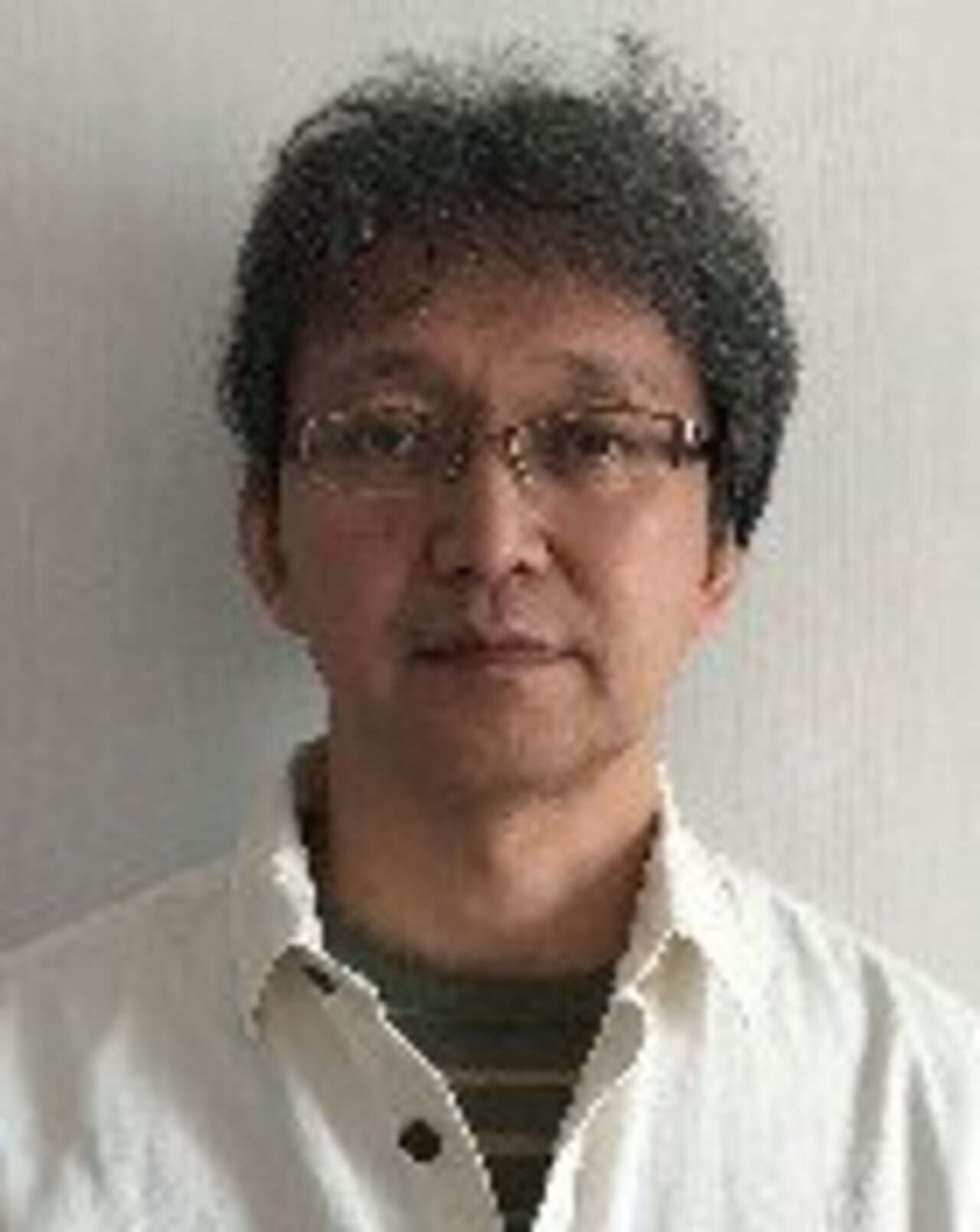心臓外科と共同で行う腫瘤摘出手術の線が消えたため、鳥海医師には、家から近い市民病院に戻ることを勧められた。抗がん剤治療となれば、がん診療連携拠点病院であればどこでもやれることは同じというわけだ。
一理はあるが、転院してきた時点で和枝と廉はK大病院で治療をお願いしようと決めていた。
鳥海医師の外来最終日に呼吸器内科の高井潔医師を紹介された。
三十代後半だろうか、和枝に明るく笑いかけ、聞き上手でもあるのだろう、不安材料を次々吐き出させていた。二人のやり取りを見ていて、この先生にならお任せできると廉は直感した。
わざわざ遠く離れた方の病院を選んだ二人の決断を聞きながら、遥はいらいらしていた。
「市民病院なら車で五分、十分でしょう、どうしてそういう話になるの?」そう詰問され和枝が答えた。
「ねえ遥、ママの病気、がんなの」
遥は「ええっ!」と叫び、一瞬顔が真っ赤になった。
でもそれ以上取り乱すことはなく、さっきからやっていたレゴブロックのタイヤを嵌めていく作業をやめようとしなかった。
「一体何の話をしているか分かってるのか。そんなアホな遊びをしながら聞ける話じゃない」。廉は突然頭に血が上った。「ママの一大事なんだぞ」「ちゃんと聞いてるよ。それにアホな遊びじゃないし」
「口答えするな。何も分かってないくせに」
「何も教えてくれなかったじゃん、こんな大事なこと」
「……」
廉は二人をリビングに残し、玄関から飛び出していた。
「奈落だ、奈落。もう奈落だ」
当てもなく、夜道をただただ歩いた。等間隔に立つ街路灯が、通り過ぎるとき淡く冷たい影を地面につくった。
少し頭を冷やしてから廉が家に戻ると、和枝が遥に静かに話をしていた。
「遠くの病院になってしまってホントごめん。お見舞いだって来るだけで大変だし悪いなあと思っているよ。でもね、ママはどうしても治したいんだ、遥のためにも。
K大病院はがん治療の実績がたくさんあってね。それに看護とか病院の設備も充実しているの。一日でも早く戻って来たいからここを選んだんだ。ただね、確かに遠過ぎるよね。ママ、遥に辛い思いをさせるのだけが悲しい」
母親にしか出せない溶けるような優しい声音に、遥も「うん、うん」と耳を傾けていた。和枝にはもうひとつ、入院の前にやらなければならないことがあった。
ピアノの生徒さんを手放すのだ。治療が長期にわたるかもしれないのでやむを得なかった。
【前回の記事を読む】手術を前に、「娘からもらったステンドグラスを抱きしめたまま幾度も幾度も笑顔をつくろうとしていた」