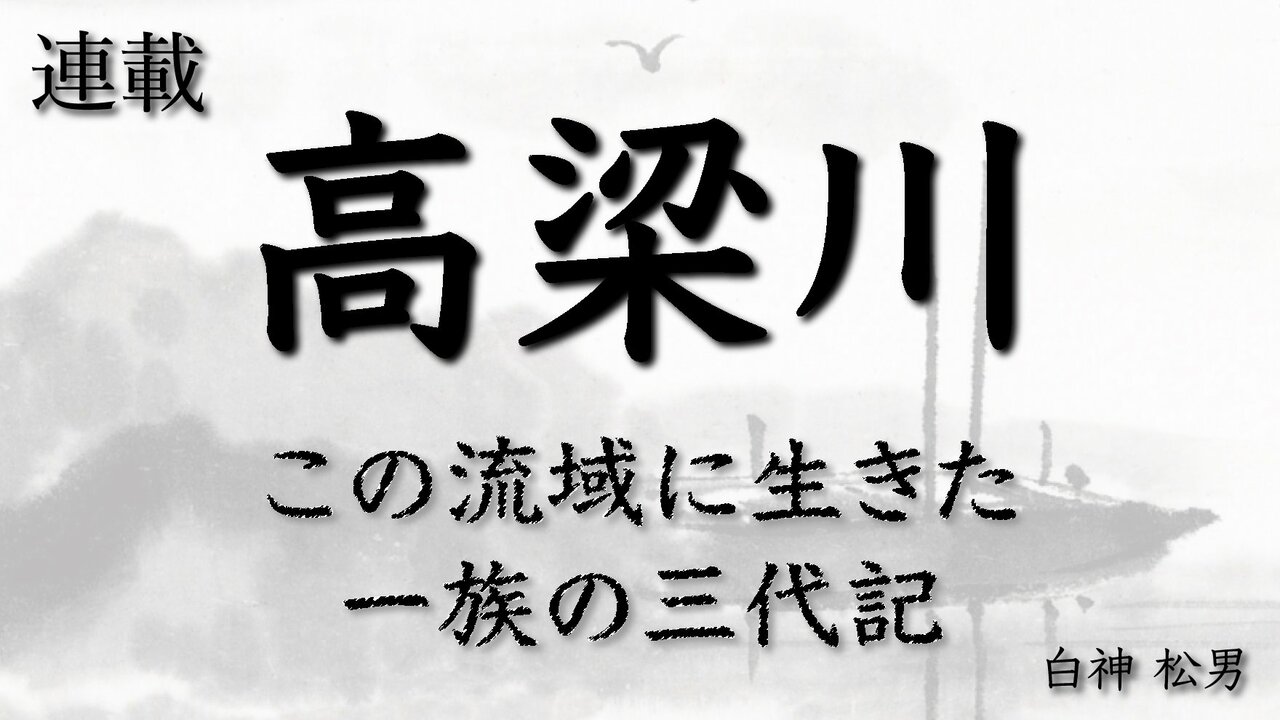第二部
十一
それから、歳月はたちまちの内に十数年が過ぎ、佐四郎は立派な若者になっていた。時代はまさに激動の幕末から明治維新へと大きな変革を遂げつつある頃だった。しかし、備中の片田舎では目に見える幕末の騒動に出くわすことも少なく、あまり実感はわかない。
とは言え、西国の主要道である山陽道が近くを通っているから、そこを長州藩の兵士が京を目指して集団で通過したりすると、その噂がすぐに広がり、ただならぬ雰囲気を感じたりする。
さらに、同じ山陽道の宿場町である川辺宿には、京へ上る同じ西国の藩士たちが度々宿泊して騒いだりしていた。そんな人たちの情報からも京や上方の状況が尾ひれをつけて広まったりする。そんな噂話で、みんな新しい時代の息吹を感じていた。
そんな頃の純之助の家では、弟の槌五郎と妹の幸が大病にかかり命を落とすこともある危ない幼少期を過ごしていた。そんな中、純之助は増えていく家族のために少しでも多くのお金を稼ぎたいと、庄屋の手伝いのかたわらで副業にも手を出し始めていたのである。
当時、川辺宿は高梁川沿いにあるため、大雨で水かさが増すと川渡りができない。そこで、旅人は川渡りが再開されるまでここに何日も宿泊しなければならない。そんなことで川辺宿は結構にぎわっていた。
その上に、高梁川には高瀬舟が運行しており、当時の交通や経済の大動脈としての役割を果たしていた。高瀬とは浅瀬のことを意味し、水深 の浅い河に対応して、船底を浅く扁平にして造られた舟を高瀬舟と言っ た。
主に、人の往来や綿花、酒、米、麦、薪などの農産物の運搬に使われていたが、ここ高梁川では、新見の南に吹屋という鉱山があり、そこで銅やベンガラが産出されていた。中でも、ベンガラは神社仏閣の朱の柱や建物に使われる染料として全国的にも吹屋はその主要産地だった。このベンガラの輸送に高瀬舟が使われたのである。
当時、ベンガラは吹屋から成羽川に下ろされ、そこから高梁川との合 流点である現高梁市の南にあった下倉の川港で積み替えられ、途中、川辺の川港を経由して河口の玉島港まで運ばれた。そこから、瀬戸内海経由で全国へと移送されたのである。ちなみに、下倉、川辺、玉島は高梁川における主要な川港であった。
このベンガラは、江戸期から明治にかけて、高瀬舟輸送でもっとも利益を上げた主要産品であり、その鉱山町として栄えた吹屋の町跡が、いまなお中国山地の奥深く現存している。いまでは町並みが文化遺産としてこの地の主要な観光地になり、当時の面影を残している。
それから、もうひとつ、これは第一部でも触れてあるが、この備中地域では綿花の栽培が盛んで、この地方で取れた綿は「備中綿」として全国的にも名が通っていた。この綿を育てるための肥料として北海道で獲れるニシンの粕が使われ、北前船によって運ばれてきていた。そして、 このような経済的に恵まれた産品や舟が往来することによって、高梁川の川港も大いに潤っていたのである。
純之助は、この川辺の川港で高瀬舟の交易に関する仕事にもかかわり始めた。それは、自分の耕作地で当時はやりの備中綿の栽培も手掛けており、綿花とその加工品の取引をこの川港で行っていたのである。
だから、自宅から一里ほどの川辺宿にもしばしば行き来していた。そんな中で、純之助は、川辺で知り合い同士のお茶の会を持つようになった。
当時は「茶の湯」をたしなむことが上品な趣味とされ、全国的にもはやっていた。その茶会は当地でも次第に評判を呼び、同業の庄屋や商人、武家や豪農クラスの人たちと交流する場になったのである。
実は、純之助が茶道を覚えたのは、姉の民のお陰である。姉は、最初趣味で始めた茶道や華道だったが、その内にどちらも師範の免状を持つまでに腕を上げた。純之助も、その感化を受けて自然と師範クラスの腕を持つほどになっていた。民が亡くなった後もその趣味は彼にとって役に立ったと言えるだろう。