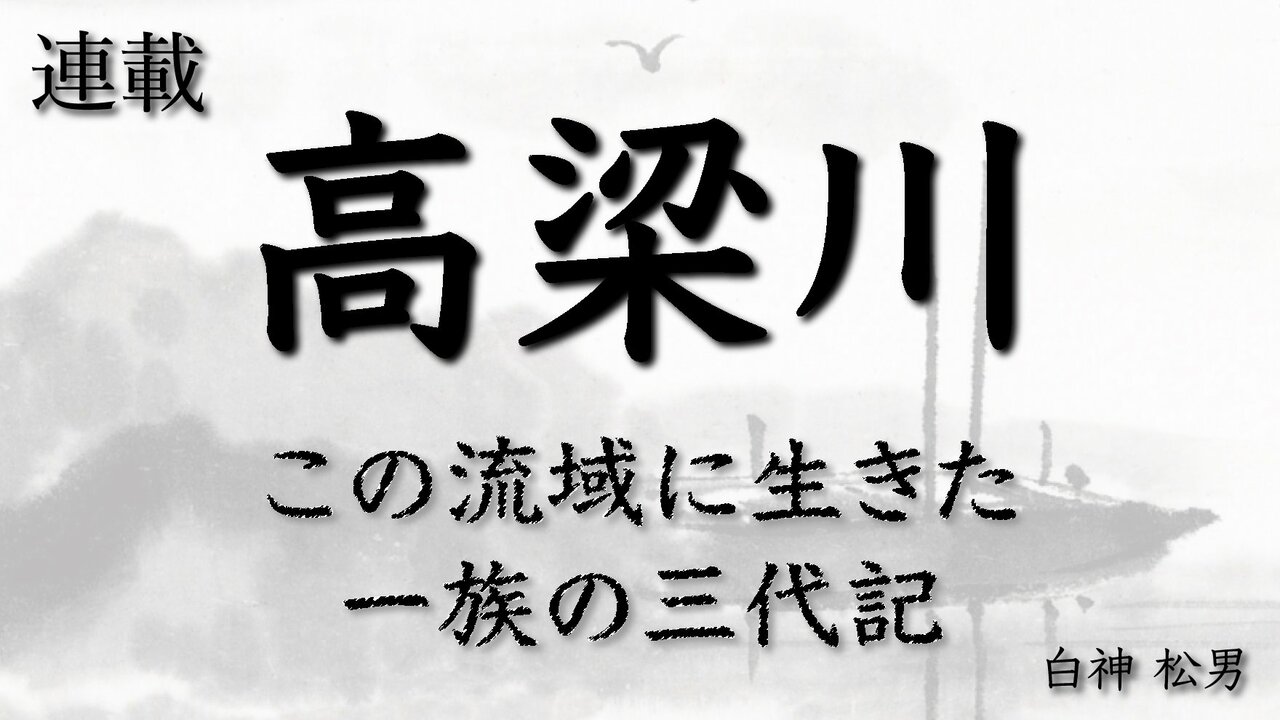第二部
十一
さて、話は変わるが、高梁川中流域の主要町であった高梁は、江戸時代には備中松山藩の城下町として栄えた。江戸期初代藩主となった水谷勝隆は、高瀬舟の交易性に目をつけ、これを上流の新見まで航路を広げたのである。同時に、彼は成羽藩から移ってきたこともあり、吹屋のベンガラを成羽川経由で高梁川から運び出す航路を開き、全国に販路を広 げて経済の繁栄に寄与したと言われる。
この貴重なベンガラとか、その他の交易品は、高梁南の下倉という川港に寄港した際、備中松山藩の検疫を受ける。そこで、藩より派遣されて検疫の業務に当たっていた役人の一人に渡辺修右衛門という藩士がいた。で、彼は、仕事柄頻繁に下流の川辺や上流の新見に同船して行き来していたのである。
そんなことから、純之助のいる川辺宿にも時々逗留することがあり、そこで、純之助らの開催していた茶会のことを聞きつけて、望んで茶の湯仲間となった。そして、ここで渡辺修右衛門との交際が始まったのである。しかも、純之助の人望のある穏やかな人間性が気に入られたのか、以後親しくつき合う間柄になった。
そんなある時、修右衛門が川辺にやってきてから、急に大雨が数日間降り続いて高梁に帰れなくなった。その時に開かれた茶会でいつものように同席し、丁度二人は隣り合わせに座り、話が弾んだのである。しばらくして茶会が終わった時、修右衛門は困惑した顔で言った。
「白河殿、この雨がいつまで続くか分からないが、拙者も長居するとお金が無くなりそうだ。何とか早くこの雨が止んでほしいのだが…」
「ああ、それならば、私の家に来て泊まって下さればうれしい。歓迎します」
「それは、うれしいことを言って下さる。ぜひともお願いしたい」
彼はほっとした表情でにこにこしながら頭を下げた。その後、しばらく茶席では世間話が続き、ひと時を過ごしてから、二人はなおも止まない雨の中を市場村の純之助宅に向かった。
考えてみれば、彼は、高瀬舟の交易を指導監督する立場の役人だ。同じ交易の仕事に関わる者としては、これぐらい都合のいい貴重な人はいない。「そんな人を自宅に泊め、恩を売っておけば、さらに親密な関係 が築ける」、純之助は内心大いに喜び、自宅に着くなり、すぐに妻の春に子細を告げ、歓待の用意をするように促したのであった。