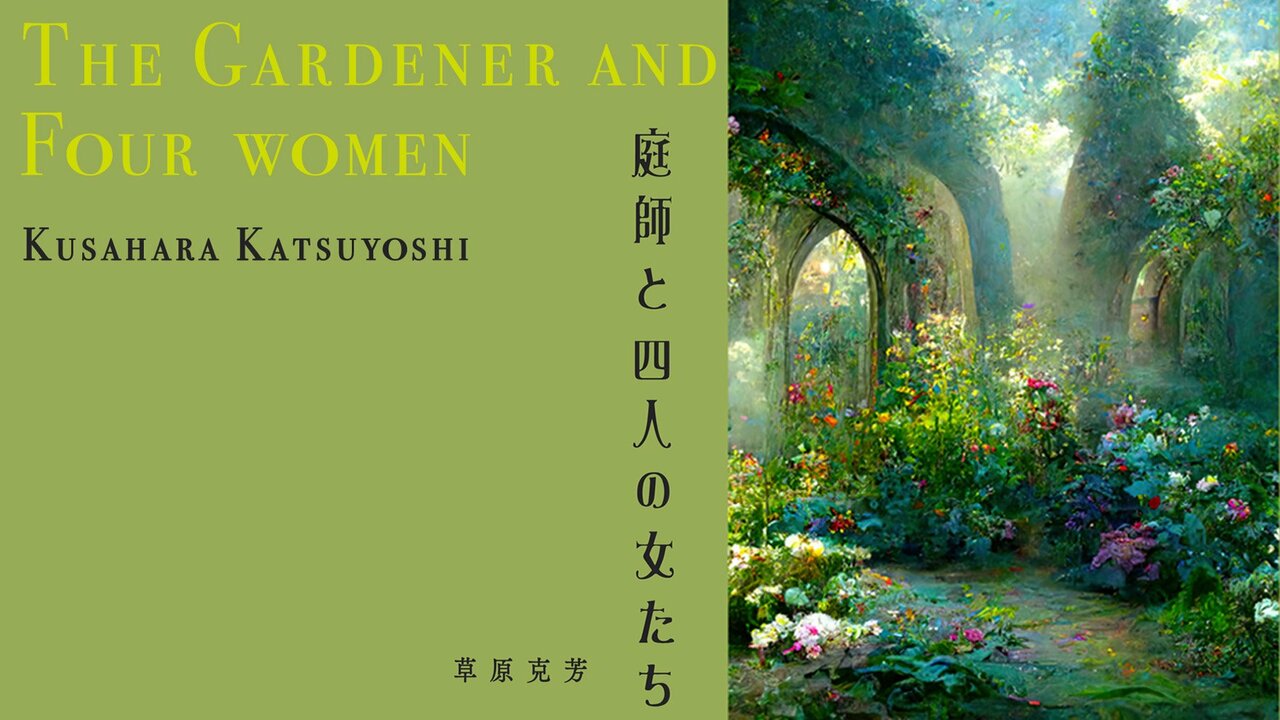庭師と四人の女たち
4
ふたたび庭師は、小さな紙袋を携えて、戻ってきた。
「鳶をやっていたってんなら、わかるよ。なかなかの身のこなしだわ」
マス江がしわがれた声でいった。
「私は、とても便利な人間ですよ、味方につけるとネ。他のことでもいろいろとお手伝いできることがあると思います」
そう言って庭師は女たちを見ると、おどけたように小首を傾げ、微笑みを浮かべた。
そして、紙袋から光沢を帯びた真紅の丸みのある塊を取り出し、一つ一つ、女たちの方へ渡した。ちょうど手のひらに入るほどの大きさだった。甘い匂いが、それとなく漂ってきた。
まず、近くにいた彩香の両手に、その鮮紅色の塊を握らせた。彩香はその充実したつややかな色合いに、目を輝かせた。
「なんの果物だい」マス江が覗き込んだ。
「小さな桃みたいだね」
「ネクタリンです。油桃ともいう」と庭師。
「あなたもどうぞ。たまたま午前中、六丁目の菜園から採ってきたものです」
庭師は袋田マス江にも、敬意を込めたような表情で、丁重に手渡した。
「あら、ありがと。なんとなく、あたしのだけ、ちょっと小さ目だけど」などと言いながらも、嬉し気だった。
次に黒崎耀子、幸田睦子と渡された。
「ああ、ネクタリンて、あの甘酸っぱいやつね」と睦子。
「名前のもとは、ギリシャの女神の美酒、ネクター、ネクタルが、由来らしい」
庭師は女たちの顔を見ながら、そのまま齧ってみせた。その動作はいささか野蛮にも見えたが、意図的に演出された何かのCMのワンシーンのようにも、思われた。
「店でも出せるわね、このネクタリン。色合いが何とも言えないわ」
睦子は爪で剥きながらいった。鮮紅色の皮の下の果肉そのものは、肉厚で淡い白黄色だった。種の赤味が、果肉の中にまで滲んでいる。
「赤すぎる夕陽みたい。水平線に沈んでゆくときのお日様」
彩香は、まだ手をつけていない果実を、指でつまんで陽に透かしている。
「わたし、こんな真っ赤なつるつるの可愛い夕陽を、セブ島のロケで見たことがあります」
「妙なこと言うわね。でも、いちおうは、海外ロケなんかも、やらされてるんだ」
耀子がけげんな顔つきで、彩香を見た。
「ちゃんと冷やして食べるとおいしいでしょう。車にもう一袋あるので、冷蔵庫にでも入れておいてください」
庭師は、真っ白な歯をネクタリンの実に突き立て、女たちの目を見ながら、ゆっくりと齧ってみせた。それから唇の周りの汁を、手の甲で拭った。この仕草はユーモラスで、わざと行儀悪く振る舞っているようにも見えた。
それから庭師は女たちから一人離れて、何かを確認するかのように、再び庭の中の散策を始めた。木陰のテーブルに置いた小皿には、太陽の光を受けた果実の種と皮とが散らばっていた。