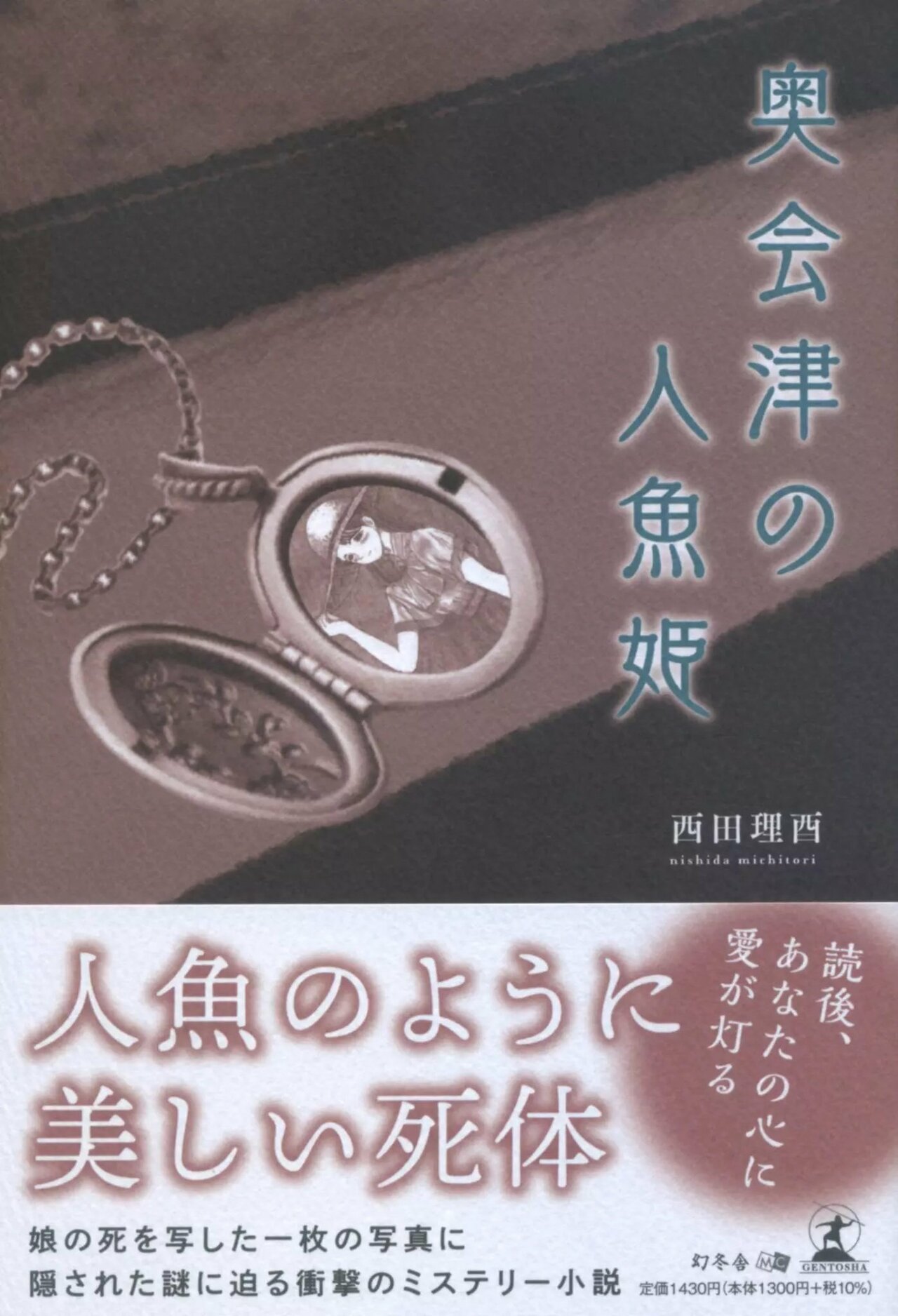ゆうべの晩餐で、千景が言った話が、鍛冶内の頭に甦った。
「乙音とはこの10年間、ほぼ何をするのも一緒の生活を送ってきた。だからあの子の考えていることは、俺には手に取るようにわかっていた。でもたまに、俺には読み取れない空白の時間が訪れることがあった。どこか遠くを見ながら、まるで魂が抜けたかのような空っぽの眼をして、笑顔を浮かべているのだ。
あの微笑みを俺は本で読んだことがある。ギリシャ彫刻の女神がたたえた中身のない笑み、アルカイックスマイルだ。その瞬間、乙音は乙音ではなくなる。いや、実はあれが本当の乙音で、俺が知っている乙音は実は別の誰かが演じている他人なのではないか。時々そんなことを思ったりもしていた」
そして苦虫を噛み潰したような顔で、さらに言葉を継いだ。
「でも俺は最近、あの子のことが根本的によくわからないと思うようになった。いや、その原因はあの子ではなく、俺自身の中にあるのかもしれない。俺の中に、あの子に対する疑念があるせいで、乙音のやること、言葉のあれこれが、今までのようにまっすぐに俺に入ってこなくなってしまったのだ。
10年間一緒にいて、こんなことは初めてだ。なのに俺が苦しんでいるそもそもの原因がどこにあるのかの見当すらついていない。早くこのトンネルを脱出せねば。そう思えば思うほど気ばかりが焦る。これはおそらく、俺の命の刻限との徒競走なのだ」