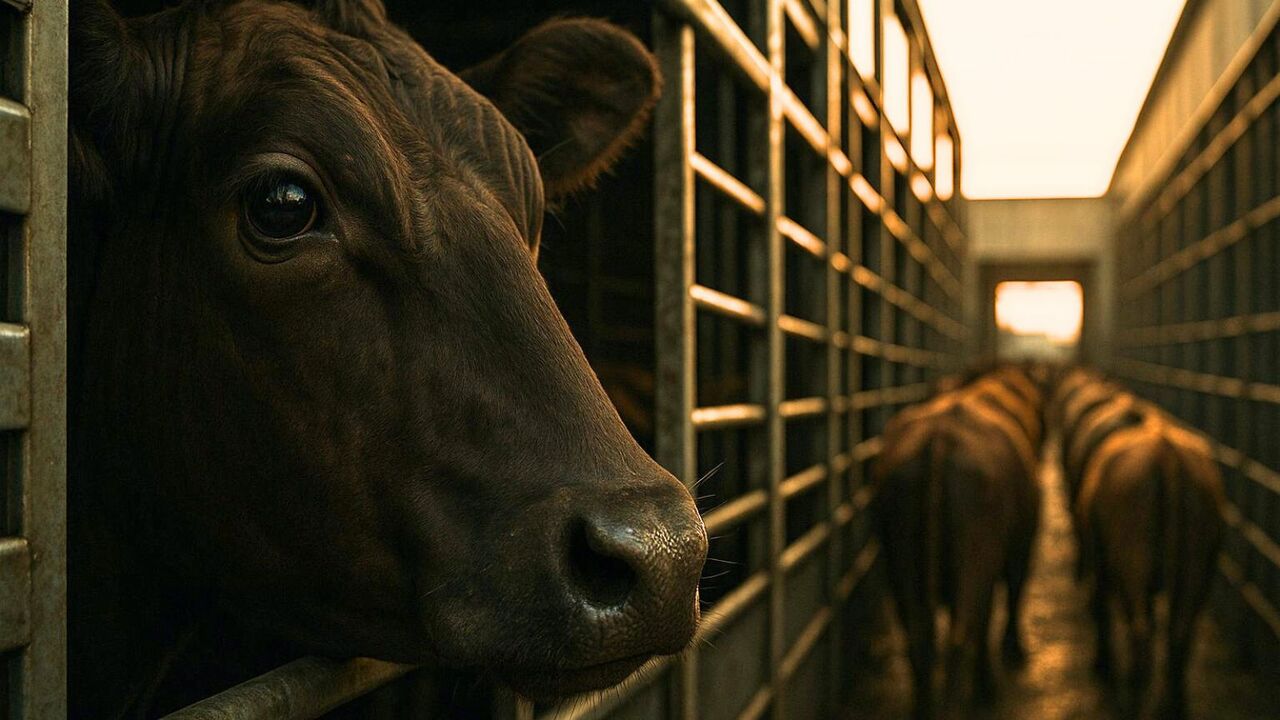安部公房は好んで壁を取り上げた。幼児期の半砂漠での原体験をもとに多くの作品を書いた。代表作『砂の女』(新潮社、19 8 1 年)、芥川賞の『壁』(新潮社、19 6 9 年)などがある。
「安部公房のばあい、この砂漠は同時に壁と言い直すことができる。砂漠と壁、それはちょうど万里の長城を築きあげているレンガが蒙古砂漠の土からなっているように、いわば同質素材からなる、同質の存在なのである。
目路をかぎるものといってははるかな地平線の外に何ひとつない広漠たる砂漠は、同時に、われわれのつい目前にあって、われわれの目をさえぎっている壁と同じものであり、目の前の壁は、同時に、目をさえぎる何もない砂漠と同じものなのだ、云いかえれば、壁によって仕切られた内部の空間と、壁の外側にひろがる外部の空間とは、まったく同質の素材からなる同質の空間ということになる。
この内部と外部との同質性の発見、同質であるがゆえに両者のたえまない相互浸透と自由自在な変換の可能性の発見そこにこそほかならぬ安部公房の独創性がある」
(佐々木基一「安部公房『壁』解説」19 6 9 年、新潮社より引用)。
養老孟司の『バカの壁』(新潮社、20 0 3 年)は有名である。ここでは、「つまり自分の知りたくないことについては自主的に情報遮断をしている。ここに壁が存在している」「ばかの壁とは人間がなにかを理解しようとする際、これ以上は理解できないという壁を意味している」と説明している。
さて、この壁を破るのは、ばかの人か、賢人なのか。どちらにせよ壁を作るのは同じである。
私は色即是空、空即是色で色と空の間に壁を観念的壁として存在を想定した。これは自由に行き来できうるのである。
死
取り上げるのは、死の壁である。誰もが避けられない生と死の間にある壁のことである。生命がなくなる時、生と死の間の壁が取り払われる。植物人間では呼吸と心拍が維持されうる。治療によって、目を覚ましたり、話せるようになることもある。
この際、壁はまだ存在する。脳死とは脳のすべてが働かなくなる状態で、人工呼吸器を外せばすぐに呼吸・心停止となり、医師の死の判定を待つだけである。呼吸・心停止、瞳孔散大、光反応なし、が死の判定である。
死亡診断書は医師が記入するが、診察していた患者が死亡し、24時間以上の場合は、死後診察の後に交付する。
24時間以内であれば、死後診察なしで死亡診断書を交付できるが、これは、例えば、当該患者の死亡に立ち会っていた別の医師から死亡状況の詳細を聴取できるなどのごく限られた場合である。病死、自然死では、その時点で生死の壁は取り払われる。
【前回の記事を読む】自由主義と共産主義との壁、社会生活における心の壁など様々な壁