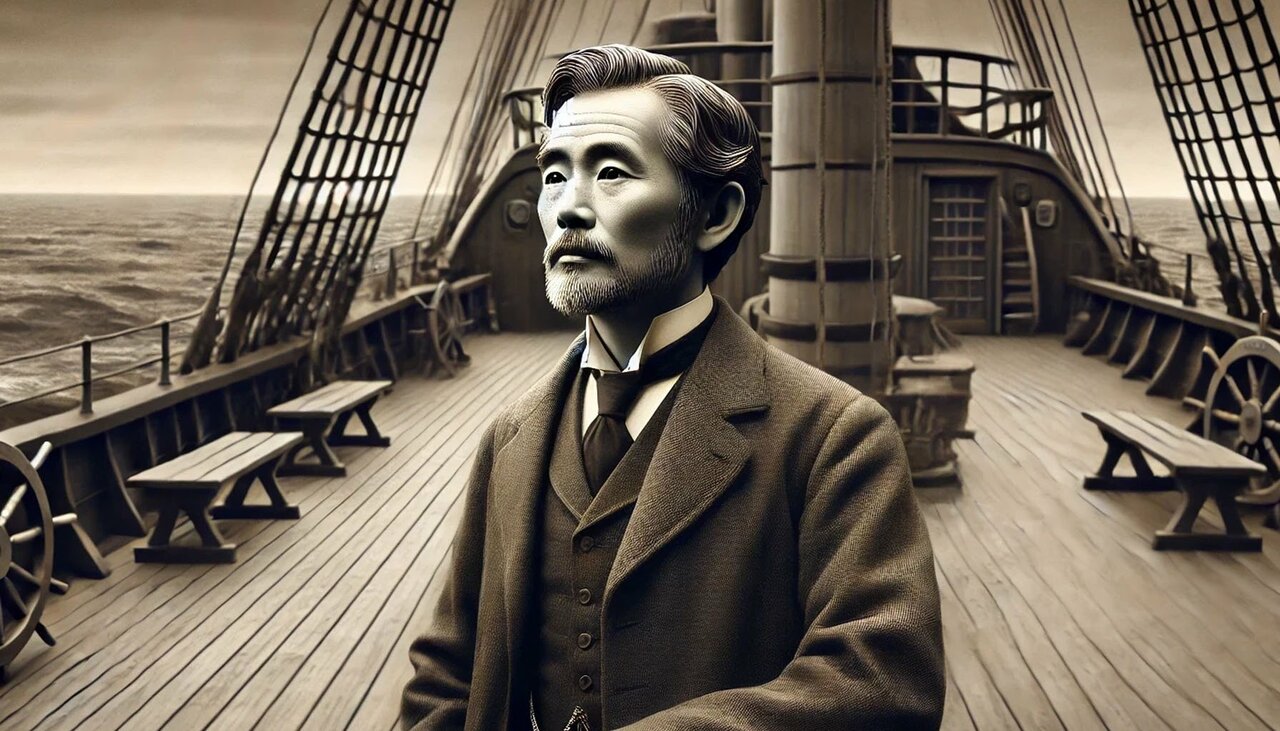第二章 カナダ赴任
カセットテープで曲を流すだけなので、皆ひたすら歌詞をノートに書いて、それを見ながら歌の練習をするのだ。六十代から上の日系カナダ人の世界がそこにあった。ほとんどの日系人は日本の歌は演歌のみと思っていたのか、紗季が赤い鳥の『竹田の子守唄』を歌うと、初めて演歌らしくない歌を聞いたのか、
「あれは演歌かいな?」と首を傾げられた。
その夜初めて「カナダのお父さん、お母さん」と後で呼ぶようになる林夫妻に出会ったのだった。向かい側に座った二人は、何だか気難しそうな雰囲気で少し緊張したが、
「今度の木曜日に家に遊びに来なさい」
と気軽に誘われ、名前と住所、電話番号を書いた紙を手渡された。
木曜日の夕方に二人で訪ねると、林夫妻は娘と三人で暮らしていた。家に入るとすぐに広いリビングで中を全部見渡せた。キッチンでは母娘が忙しそうに料理を作っていた。
「お腹空いただろう、食べてきな」
初対面の娘のジュデイに誘われ、ご馳走になった。
お父さんが釣った紅鮭の大きな塊を蒸したものに、千切りのショウガをカリカリになるくらいまでたっぷりのゴマ油で炒めたものと、醤油、青ネギの刻んだものをかけた豪快な料理に舌鼓を打った。
「うまい!」
「美味しい!」
と晃司と紗季が感嘆の声を上げると、家族みんな優しい目で笑った。
日系三世のジュデイは、日本語教育を受けていないのであまり日本語が得意ではなかったが、できるだけ日本語で話すようにしていた。ひらがなは読めるので、ひらがなで書いた歌詞を見ながら日本の歌を上手に歌えた。
お父さんの名前は正雄で紗季の父と同じ名前だった。娘四人に息子が一人いて、一番下の年の離れた娘の日本名が紗季と同じだったので益々親近感が湧いた。ジュデイの日本名はひろみで、晃司の妹と同じ名前だった。
それから毎週木曜日には夕食後に林の家に集まって、カラオケの練習に励んだ。週に一回はバンクーバーの町へ、お母さん、ジュデイ、後から友人になるひろ子たちと一緒にショッピングに出掛けた。
ジュデイは中国人の医師と結婚し二人の息子がいたが、離婚し実家に帰っていた。
ジュデイの息子たちは父親と暮らしていたが、よくジュデイを訪ねていたので顔見知りになった。下の息子は十四歳でまだ母親が恋しかったのかもしれない。驚いたのは、ジュデイが妊娠中に、夫の浮気でできた同じ年の男の子が「グランパー、グランマー」と言って、一緒に遊びに来ていることだった。