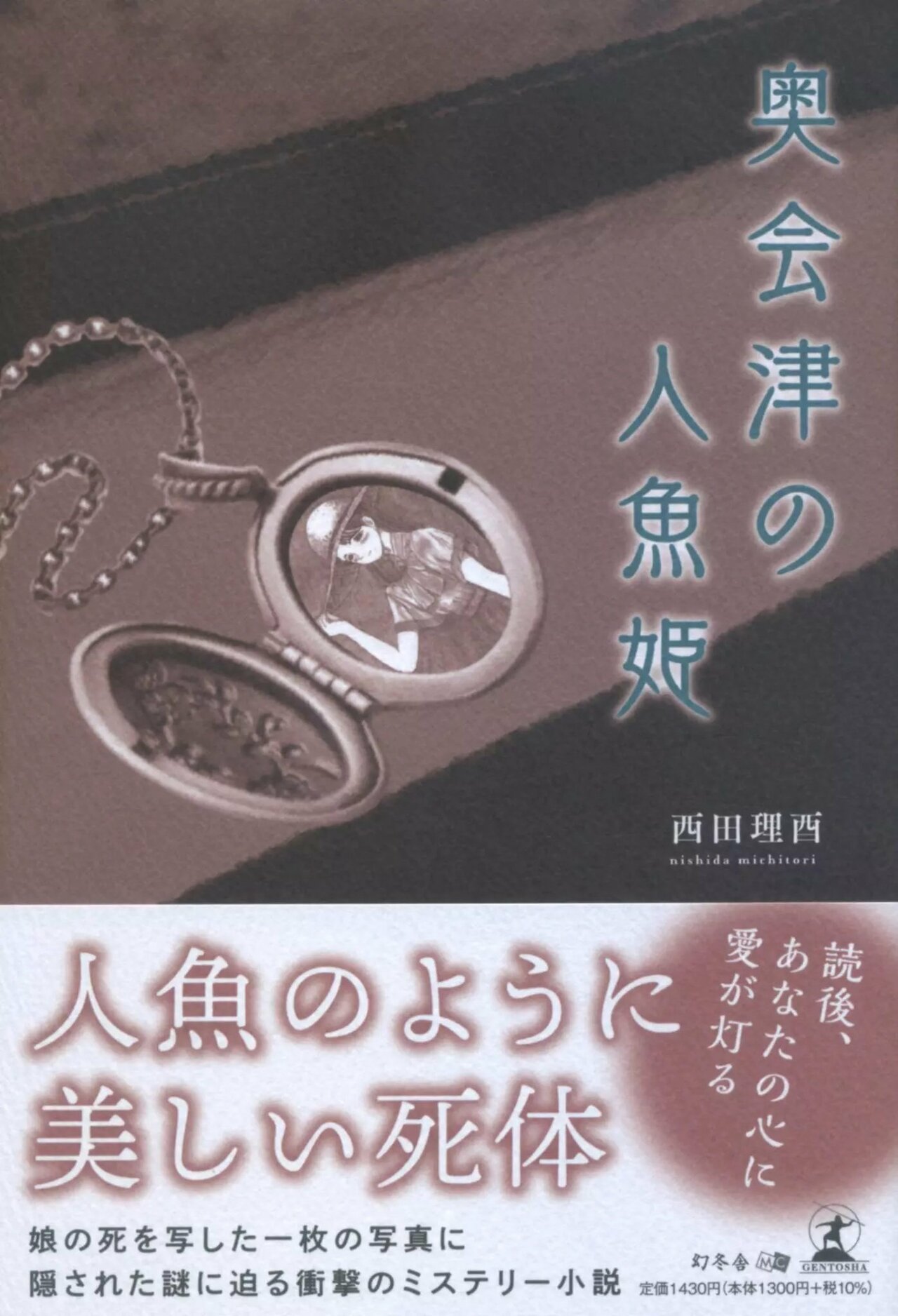「私と汐里はそれまで、食べ物の好き嫌いからお気に入りの服や見る番組、果ては聴いて心地良い音楽から感動した映画まで、まわりがびっくりするくらい好みがぴったりと同じだった。だからお互いにちぃちゃんが好きだと知っても、お互いにやっぱりなという感覚しかなかった。
ただあの日から一つだけ、前の日までとは違ったことが起きた。それはあの日以来、私と汐里はお互いを恋のライバルとして意識するようになったってことよ。だけど…………」
そこでさもおかしそうに乙音は声を上げて笑った。
「ふふ、考えてみればおかしな話よね。ちぃちゃんは当然ながらお母さんの旦那さんで、私たちにとって父親なのだから、恋の対象にはなりえないって二人ともわかってるのに、なぜか私たちは、恋のライバルとして相手を意識するようになったってことなんですもの。でも仕方ないわ。人間の感情なんて、理屈で割り切れるものじゃないんだから」
そしていつの間に用意していたのか、手元の小さなバスケットからサンドイッチを取り出すと「はい」と言って、二つのうちの一つを鍛冶内に差し出した。
「あの日も、こんなサンドイッチをみんなで食べたわ」鍛冶内はオールから解放される口実を与えられて、内心喜びながら、乙音からのサンドイッチをできるだけゆっくりと頬張った。
……この子が本当は汐里だったとしても、今の話に矛盾はないんだ。千景と同じ船に乗ったのが、実は乙音だったのかもしれないのだから……。
「一つ聞いてもいいかな? 乙音ちゃん」
乙音の側のサンドイッチが跡形もなくなったタイミングを見て、鍛冶内が乙音の顔を覗き込みながら言った。
「昔からよく知ってる俺から見ると、本当に不思議なんだが…………」
何を言うのだろうと乙音が、鍛冶内の顔をいぶかしげに見た。
「この際聞かせてくれ。千景のどこが良いんだ?」
すると乙音はぷっと吹き出して、声を立てて笑った。それは尋ねた鍛冶内の間が面白かったからだが、やがてひとしきり笑い終わると、乙音は真剣な顔つきになって、湖の彼方の光が集まってるあたりに視線の先を向けた。
そして「おじさまの答えになっているか、わからないけれど」と前置きした上で、乙音は言葉をひとつひとつ選ぶようにしながら話を始めた。