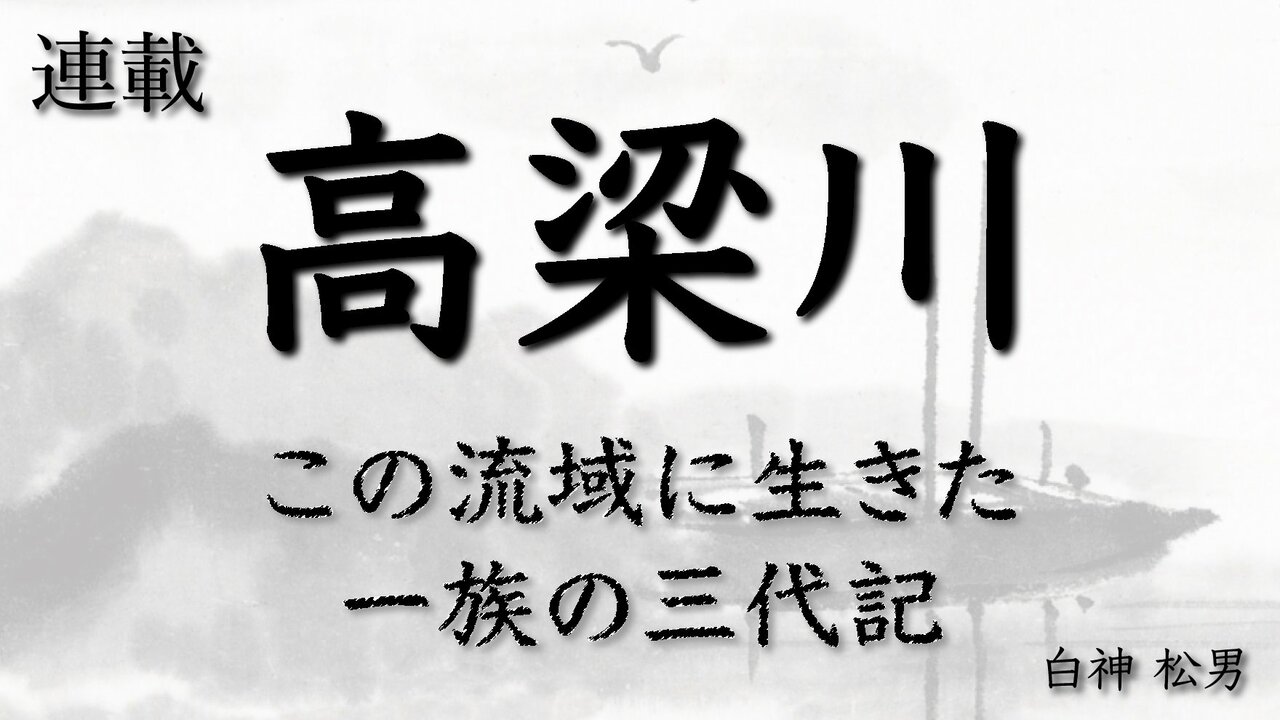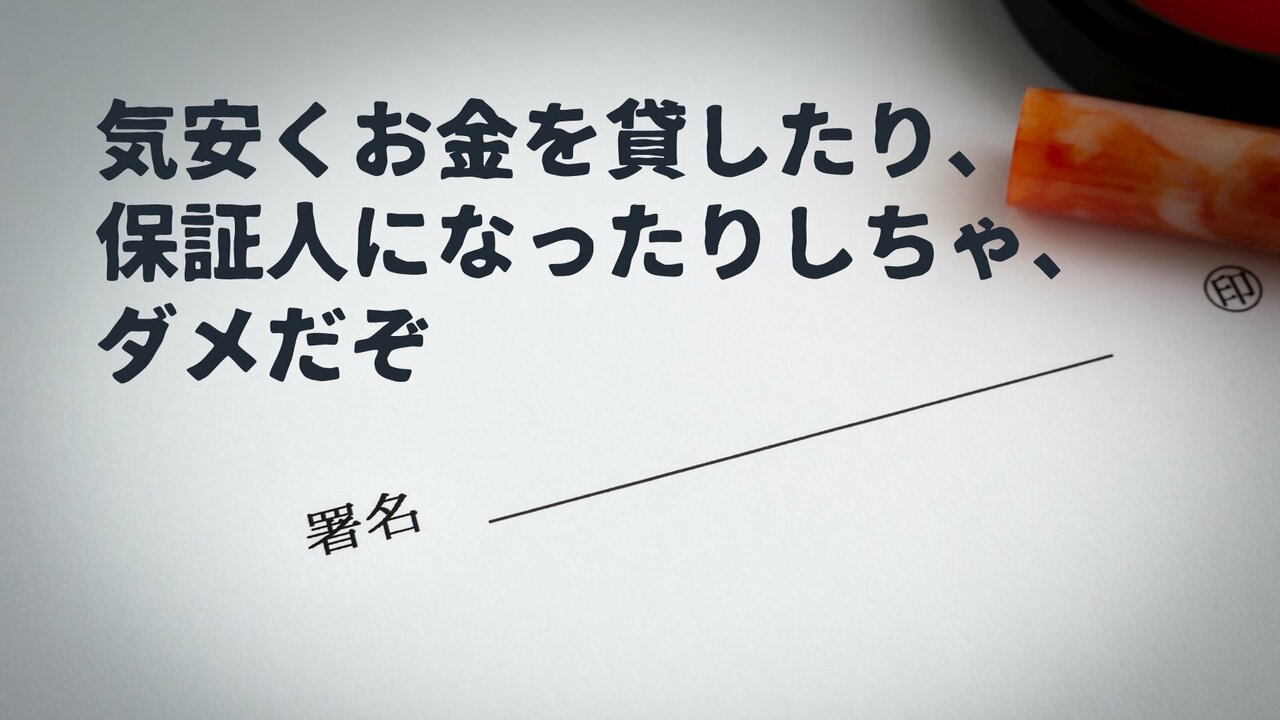第一部
九
天保年間に生まれた純之助は、無事に二十代の立派な青年に成長した。その成長とともに、日本はあの激動の幕末から明治維新の時代へと移っていくが、その間、純之助の家では、佐治衛門の妻、半が七十代の当時としては長寿を全うして亡くなっている。同時に、姉の民も相前後してこの世を去り、残されたのは、純之助と度助の二人の男たちだけとなった。
度助とはかなりな年齢差がある。しかも、度助は親代わりになって育ててくれたといってもいい存在だ。母親と姉を失い、もう血のつながった家族もいなくなった純之助にとっては、ただ一人の頼りになる身内である。
「度助どん、これからもそばにいて、どうぞよろしく頼みます」
寂しさと不安ひとしおの純之助は、深々と頭を下げて懇願したのだった。しかし、度助の本心は少し違った。「もう妻もいない。これ以上この家にいる理由もなくなった。できれば、どこか他所で働きたい」というのが本音だ。
とは言え、「まだ一本立ちのできてない義弟を置いては、どこにも行けない」という気持ちも強い。多分、親戚の人間であるという絆を感じていたからに違いない。そこで、度助は、純之助が結婚して家庭を持ち、一本立ちするまでは、この家に留まり共に生活することを誓ったのであった。
勿論、度助がここに腰を落ち着けていたのは経済的理由もあった。純之助は責任者ではないが、いま風に言えば、庄屋という会社の専務取締役みたいな地位にあり、安定した収入があったのだ。
度助もその下で補佐的な仕事を任されていた。しかも、この家には、先代から受け継いだかなりな資産があることも知っていたのである。
さて、若い純之助に任されたのは外回りの仕事だった。当時の庄屋が管轄する農民には、自作農と小作人の二つの場合があり、前者は自分で先祖代々引き継いでいる農地を持っている農民、その中でも、特に大きな土地を持っている農民は地主と呼ばれていた。
一方、後者の小作人とは自らの農地を持たない農民で、いずれも、決められた年貢米をお上に納めなければならない。その場合、「五公五民」といって、収穫の半分はお上に、そして残りの半分が自分のものになるというのが一般的だった。ただ、小作人の場合は、その他地主に借地料も払うことになる。
しかし、度々起こる干ばつや反対に水害などで収穫量も常に不安定だ。それに耕作地が隣り合う隣人同士に境界線のことでトラブルが生じたり、水利の争いも頻繁に起こる。また、農作業にまじめに取り組む人もいれば、熱心でない農民もいる。
そんなことから生じる様々な相談事に応じないといけないが、生来、育ちのいいお人好しタイプの純之助には、あまり適した仕事とはいえなかった。彼は金銭に困っている小作人などを見ると、すぐに同情して小銭を工面してやったり、借金の連帯保証人になってみたり面倒見が良過ぎるところがあったのだ。そんな気前良さが、年配の義兄をやきもきさせたのだった。
「純之助どん、そんなに気安くお金を貸したり、保証人になったりしちゃ、ダメだぞ。もう、庄屋の主は本家に移ったんだから、親父の時みたいな多くの収入はないし、それに、金貸しはもうしてないんだぞ」「貸した金は返してくれる当てもないし、保証人になった借金はいつか自分にかかってくる。二度としちゃ、ダメだ」と、きつく諭される純之助だが、困った人を見ては、すぐ同情してしまうその性格は容易には改まりそうにない。