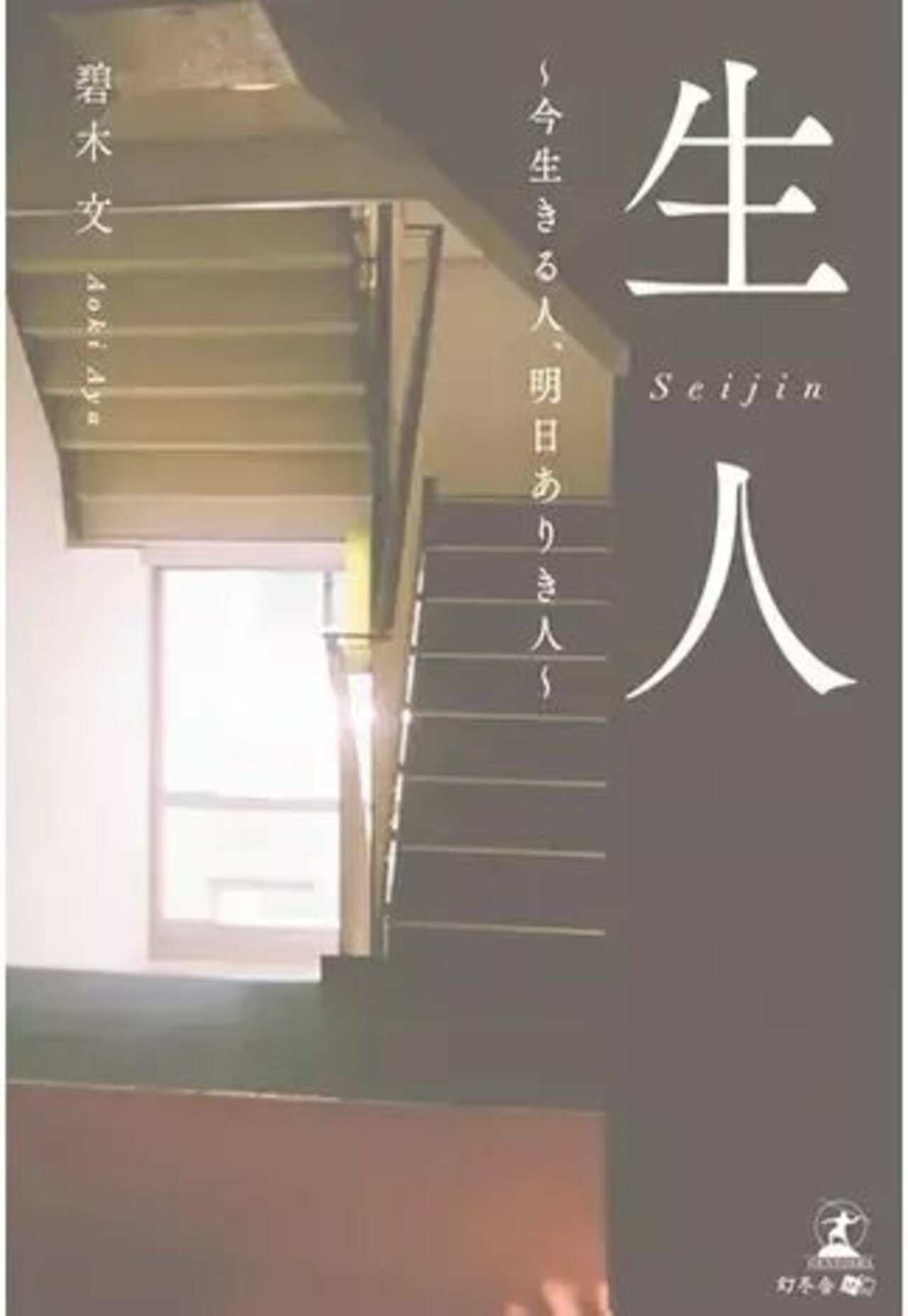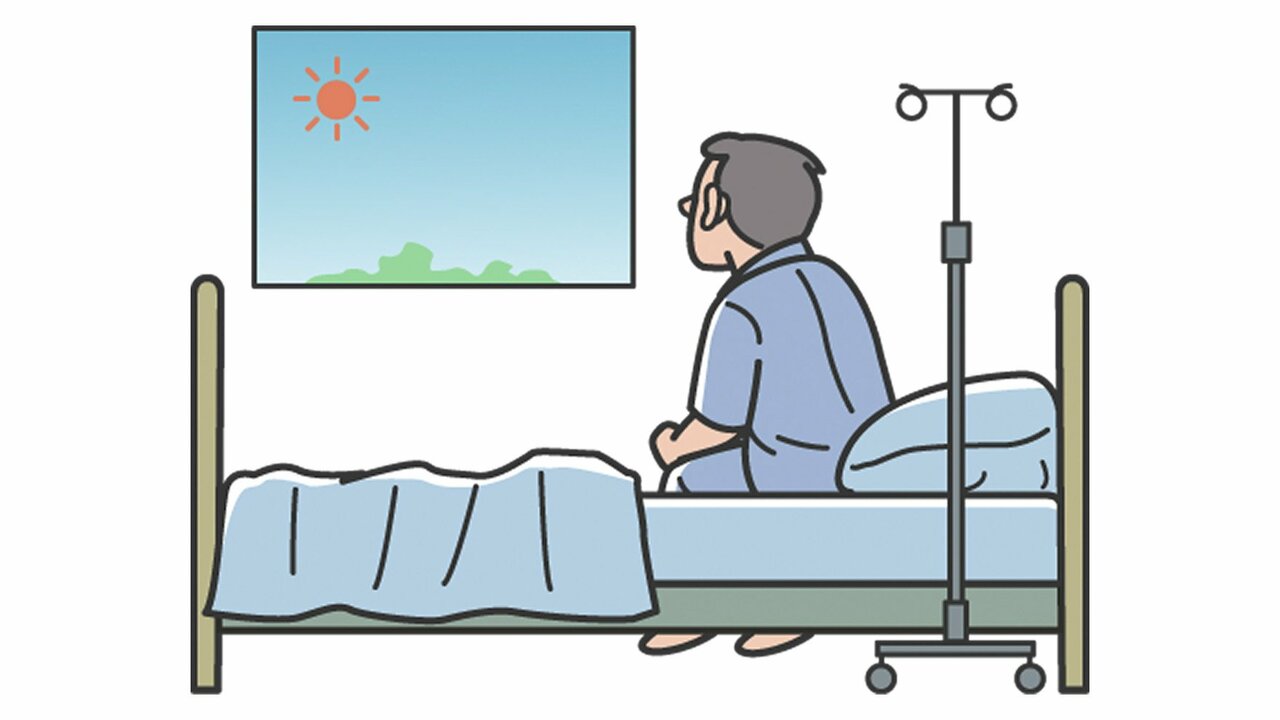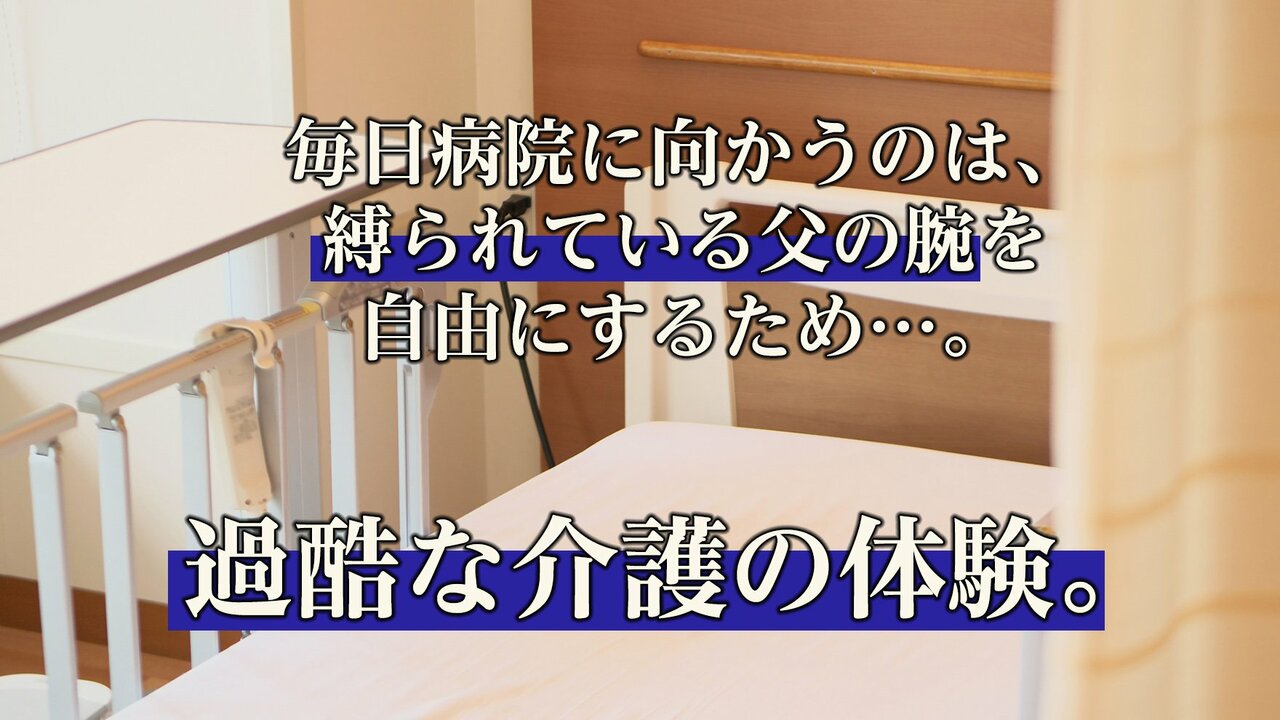日本での脳卒中や心筋梗塞で倒れた老人に対する、医療や介護システムは、ここ三十年たっても何も変わらない。あのどうしようもなく見捨てられた悲惨な惨状は何も変わらないのである。知る人ぞ知る光景である。
誰かにしかわからない過失が多いことだろう。もし訴えて死人が生人に戻るなら、そうもするだろうが、出来ない。
悔しいことに訴訟なんて、そんな余力も残っていない。
大きなお世話だが、病院や施設と連携している葬儀社はやめておこう。高額の場合が多い。
現在は皆家族葬かもしれないが。
生人は、亡くなった大切な人にもう一度だけ会いたいなどと言ったりする。
自分にはそうは思えない。
一度だけ会えてどうするのだ。会えたなら、二度も三度も会いたくなるだろう。
もっと会いたくなるだろう。
生人はそんな欲の深いものだろう。
生人はわがままであり、自分本位であり、満足をしない。
あるいは、人に流され、自分を持てなく、依存をする。
幸せは束の間で、不平不満がつのるばかり。こんな自分に誰がしたのか。自分である。
誰もいない、暑さ寒さも感じない。
ただだだっ広い平坦な場所に、ポツンとひとり立ち尽くしている自分の姿が遠くに見えた。
「仕方ない」と、生人は言う。死ぬのは仕方ないと。
確かに人が死ぬのは仕方ないことだろうが、そうは言ってほしくなかった。
年をとればとるほど、その言葉を当たり前のように使う生人がいる。
当たり前の意味などわかりもしないが。また、それも生人それぞれということだ。
結局のところ自分の介護生活は十年にわたった。
新しく綺麗だった家も何十年も経てばゴミ屋敷と化してゆく。
元気なうちに断捨離だとか、終活だとか、そんなことを真面目に言う生人たちがたくさんいるが、そんなことは突然起きたりするもので、間に合わないことの方が多い。
老いても明日があるだろうと思っているのが生人である。
かつてたくさんの生人が出入りし、彩りがあり賑わいのあった家屋も、誰もいなくなり老朽化しゴミ屋敷となった。ひとり取り残されて号泣した。
これをひとりきりで、どうしろというのだ。
残された大きな箱の中は膨大な量の宝と思い出の品とガラクタがごちゃ混ぜ状態である。
自分の心に憎悪が生まれた。