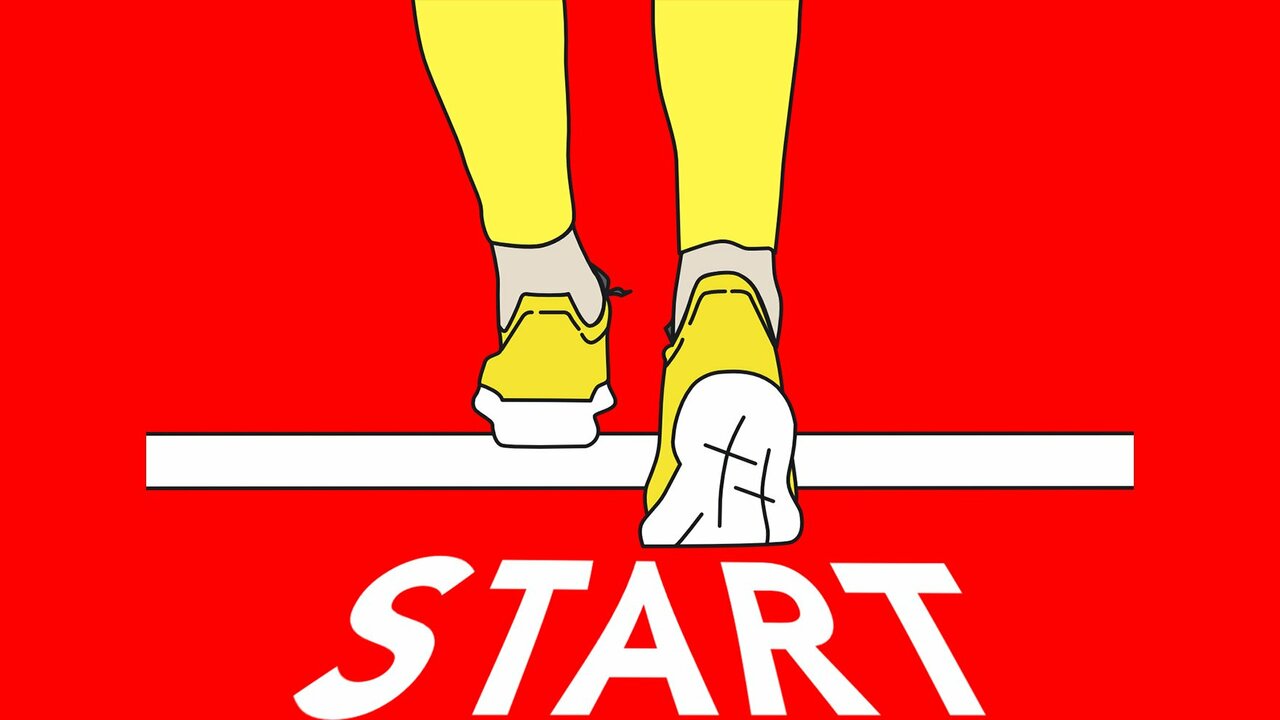一
「はい、お待ちどうさん」
夏生の前に肉団子定食が置かれた。楕円形のプラスチック皿に盛られた料理が湯気を立てている。
湯気を吸い込むと甘酸っぱい香りが鼻腔を突いた。ピンポン玉くらいの肉団子が五つ、オレンジ色の人参や緑のピーマン、熱が通って透明感が出始めた白い玉ねぎが茶色い餡に絡まって艶々と光っている。
「いただきます」
夏生は肉団子にかぶり付いた。表面に程よい弾力を感じたが中は柔らかだった。半球になった肉団子が口の中に落ちる。熱い。ハフハフと口から肉団子の温度を息といっしょに吐いた。乱切りの人参と、くし切りの玉ねぎは、大きなかたまりに見える。
おっちゃんの調理時間は数分だったが果たして野菜に十分熱が通っているのか。夏生は野菜を頬ばった。うぐっ、熱さのために野菜を口の中で右に左に動かしながらも野菜を噛む。人参も玉ねぎも歯応えは柔らかく、二度、三度噛むと飲み込んでしまう。夏生はネギ類など香りの強い野菜が苦手だが、甘酢餡に絡められた玉ねぎはうっすら甘く美味かった。
二人が食べ終わると、おっちゃんが夏生に話しかけてきた。
「自分は新入生かぁ。いつ、こっちに来たんや」
「はあ、今日です」
「そうかぁ。西山君、バイトさんよろしゅう頼むで」
バイトさん頼むでとは、早く新人を見つけてこいという意味だと分かった。おっちゃんは、夏生をギュッと見つめてからニコッと笑った。
店の外はすっかり夜になっていた。西山の言うとおり、定食は夏生の腹を十分に満たしている。肉団子定食三百五十円、覚えやすい値段だ。
「美味かったやろ。そんでぇ、勘のいい自分ならもうわかったと思うけど、あの店、今バイト探してんねん。俺の他にあと二人いるんやけど、三人ではなかなかきついねん。バイト代は高いとはいえんけど、飯も食えるしなぁ。自分、あっこの店でバイトしてみいひんか」
やっぱりきたか、と夏生は思った。西山の口調は「嫌なら別にかめへんで」という、フッと吹いたら簡単に次のところへ飛んでいってしまいそうな軽さがあった。
「やります」
口の中に肉団子の甘酸っぱさを感じながら、夏生はあっさりと返事した。返事しながら、天国飯店でアルバイトすることが初めから用意されていたかのように感じた。生活の歯車が一つできた。