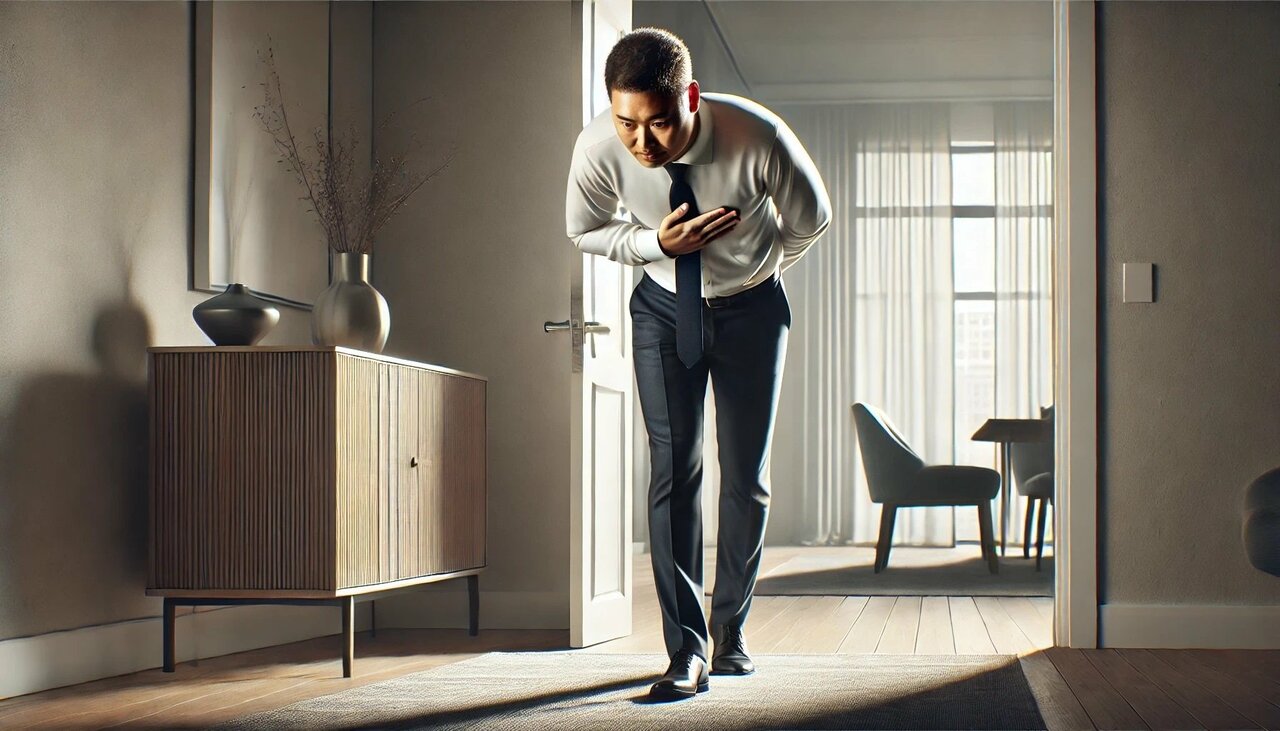落とし穴
タカシの家には何百年も続いてきた家業がある。その名も穴掘り屋。
ピンとこない人も多いであろう。それもそのはず、ほとんど公になったことがない職業だからだ。
先祖代々受け継がれた田舎の広大な敷地に次々と穴を掘る。それが穴掘り屋の仕事だ。ただ闇雲に掘るわけではない。掘るべき時に掘るべき場所を掘るのだ。やがて穴は自然と塞がるのが通例で、短い時には数週間、長い時には数十年なんてこともある。そのため何百年もの間、脈々と家業が続いても敷地が穴だらけになることはなかった。
穴掘り屋には息子のタカシ以外に後継者がいないこともあり、タカシは小さな頃から当たり前のように家業の手伝いをしてきた。学校が休みの日には、よく穴を掘っては幾ばくかの小遣いをもらった。
もちろん小遣いをもらえることも嬉しかったが、何よりも両親の喜ぶ顔を見ると心の底から沸き上がる喜びがあった。子どもとは親を喜ばせたいと頑張るものだ。
そんな穏やかな日々に変化が訪れたのは、タカシが高校卒業を控えた冬の終わり頃であった。跡取りは学校を卒業するとともに家業に専念するのが代々の習わしで、タカシも例外ではなかった。
もうすぐ春だというのに、新たな季節の訪れが予感できないほど寒さが厳しい土曜日の朝、コタツでのほほんとミカンを食べるタカシに、珍しく父親が真面目な顔で話しかけてきた。
「なぁ、タカシ……」
タカシはミカンを食べる手をピタリと止め、父親の方を見る。
「家業に専念する前に話しておかなければならないことがあるんだ……」
父親のただならぬ雰囲気にタカシの丸まっていた背中はピンと伸び、それを見届けたかのように父親は淡々と重みのある声で話を始めた。
「落ち着いてよく聞いてほしい。普段私たちが掘っている穴は、ただの穴ではない。人生の落とし穴なるものなんだ。他人の不運を生み出しているとでもいうのが適当だろうか……」
思ってもみない突然の告白に口をポカンと開けるタカシを父親は外へと連れ出した。敷地内に点在する穴を避けながら二人は足早に歩いていく。いつの間にか父親よりも大きくなったタカシが追うその背中は、何だかいつもよりも遠く感じた。
「父さん、一体どこに向かっているの?」
問いかけが聞こえていないかのごとく何も言わずにスタスタと前を行く父親の姿に、タカシはそれ以上声をかけられず、黙ってついていくほかなかった。
無言のまましばらく進むと、父親は急に立ち止まり地面を指さして言った。
「ほら、見てごらん。これは今日の作業で掘る予定の場所だ」
「ふーん……ここが今日掘る場所なのか……」
何も察する気配のないタカシに父親はしびれを切らしたかのように促す。
「ほらほら、よく見てごらん。地面にデコボコがあるだろう? 文字に見えないかい?」
言われるがまま、タカシは目をこらして見た。