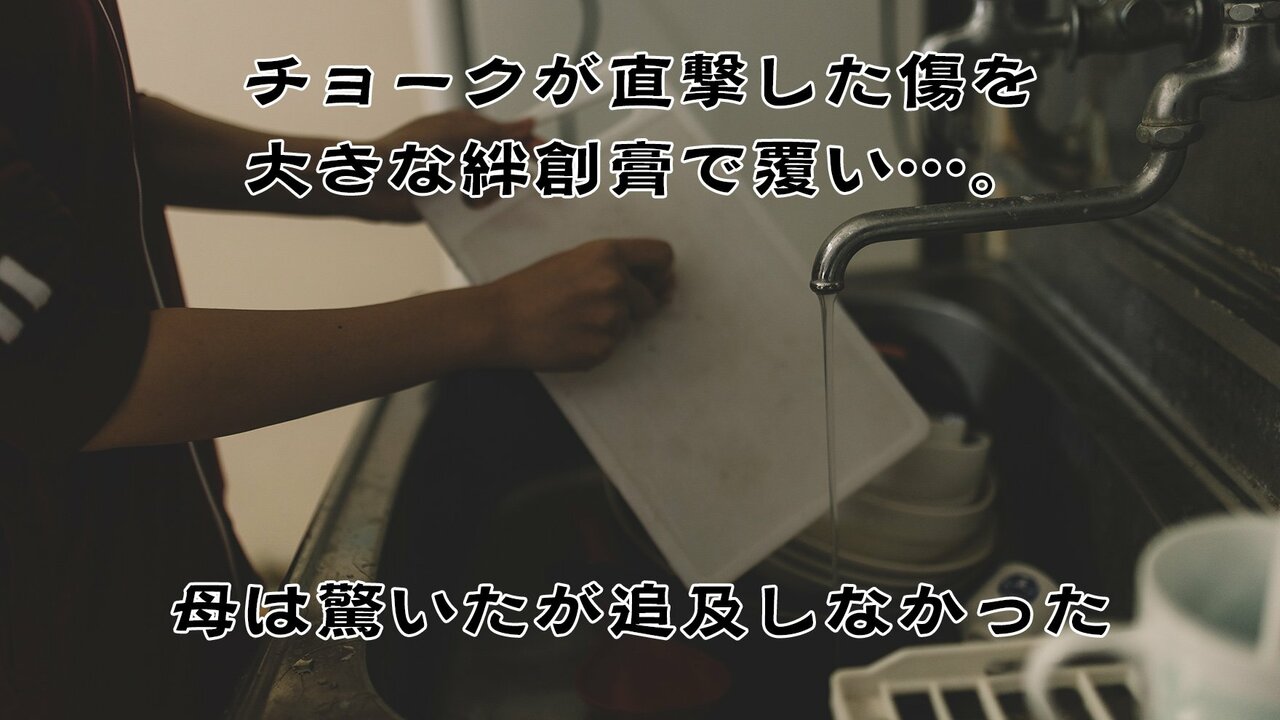「ああ、あの弁当の事?」
「見てらんない」
「そうじゃなくて」
「何がさ」
「ああするのが一番なんだって」
純太は自分の行動を正当化しようとした。
「私、純太みたいに強くないから。私ってさ、意外と打たれ弱い。あんな事されて、それを抗議もしないで、犬食いするなんて。相当キモイんですけど。有り得ない。そんなことされたら学校なんか登校拒否だし、美紀ちゃんみたいに学校行けない」
と言った。
「女子は陰険だからな」
純太は入学早々に、女子のいじめにあって学校に来なくなった北島美紀の事を言った。自己都合により登校できなくなったと教師が言ったが、二人は黙ってそれぞれの考えに耽っていた。
「私だったら消えたくなる」
純太は保健の佐伯との会話を思い出した。本当にそんな立場になってもそう言えるのか。
『いじめなんかで死んだりしない』
と言った自分の言葉を肯定するように、そんないじめなんか、
「すぐに馴れるさ、気にしてなきゃ」
と言った。
純太の言葉に綾乃の顔は死刑の判決でも下りたかのように一瞬凍りついた。そして、抱いていたクマの体にしがみついた。
「私さあ、部活辞めちゃったの」
愛の告白のようにそっと綾乃は言った。
「え、ああ。そう。でも何で。コンクールもう直ぐだろ?」
「それが問題でさ」
コンクールに向かって、万年二位の吹奏楽部は今年こそ優勝だという望みをかけていた。
「部員一人ひとりの意識改革、とか言ってさ」
「うん」
「そりゃまあね。体力も大事よ。だからって急に体力作りだか何だか知らないけど、グラウンド走らされたり、放課後も一番遅くまで練習、練習、練習。私もう限界きちゃった」
「うん」
綾乃はしばらくクマの耳を引っ張ったり、鼻先をなでたりして気持ちを整理しているようだった。