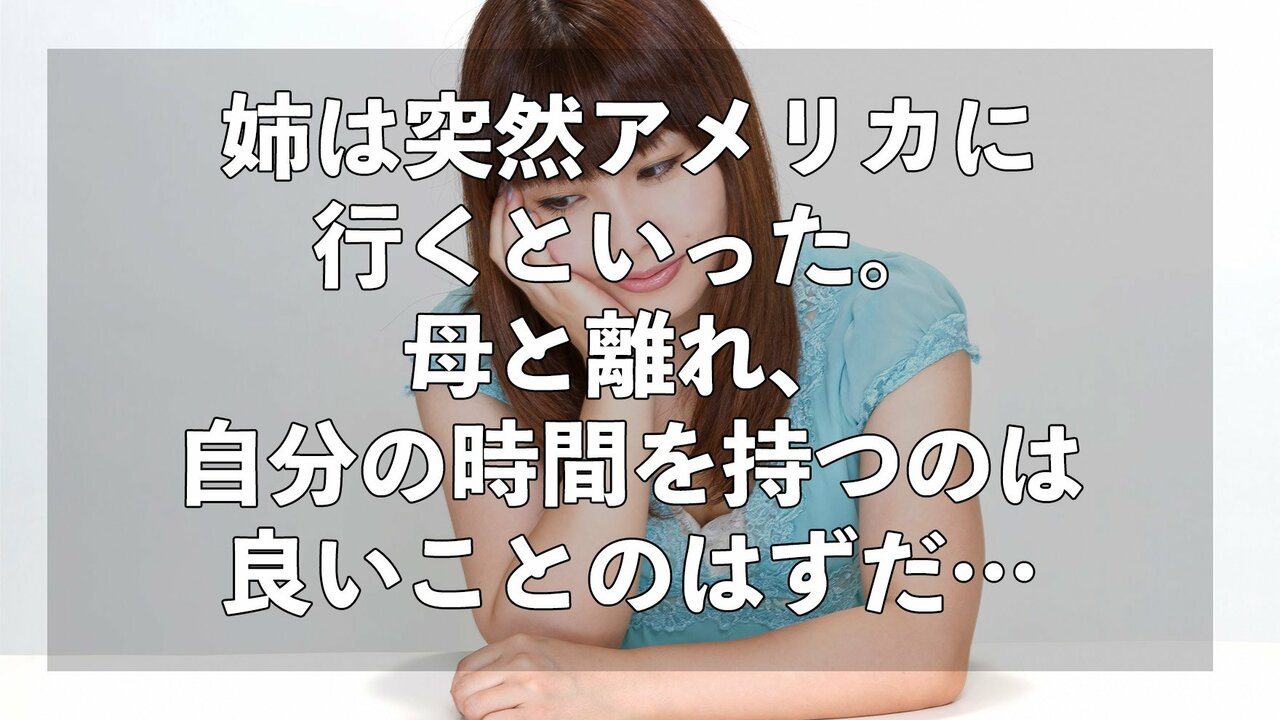第三章 亡くしたもの
すると亜希子はおもむろに、何かのパンフレットを取り出した。
「来月からアメリカに二年間、研修に行くからね」
郁子は話題が変わって少しホッとしていた。ところがそれも束の間、先ほどよりも深くなった亜希子の心の闇に共鳴する何かに心を揺さぶられて、郁子はまるで船酔いの時のような気持ち悪さを感じていた。
亜希子はもしかしたら行きたいばかりの気持ちでアメリカ行きを承諾したのではないのかもしれない、と郁子は咄嗟に思った。
そもそも亜希子が看護師になる決心をしたのは、亜希子なりに父邦夫を思ってのことではないだろうか。亜希子が将来の進路を考えなければならなかった、ちょうどその頃、父邦夫は自身が経営する会社の第一線を退いて自宅療養となった。それを受けての看護師なのだとしたら、珍しく母佐知子の反対を押し切った亜希子の選択も郁子の腑に落ちるのだった。
だからこそ郁子は、母佐知子の執拗さに腹を立てていた。こうまでして亜希子に看護師を辞めさせようとするのは、何故なのだろうか。
亜希子は度々のお見合いも断り、こうして二年間という長期の海外研修に行こうとしている。たとえ二年間とはいえ母佐知子の元から離れて、自分だけの時間を持てるのはきっといいことのはずだ。郁子はそう思いたかった。
他のことなら、そして違うタイミングなら、亜希子を手助けする術もきっとあるのにと思うと、郁子は歯噛みをするしかなかった。出会えるはずだった我が子を何の前触れもなく喪い、更なる妊娠に得体のしれない恐怖すらを感じている今の郁子にとって、そんなゆとりなどあろうはずもなかった。