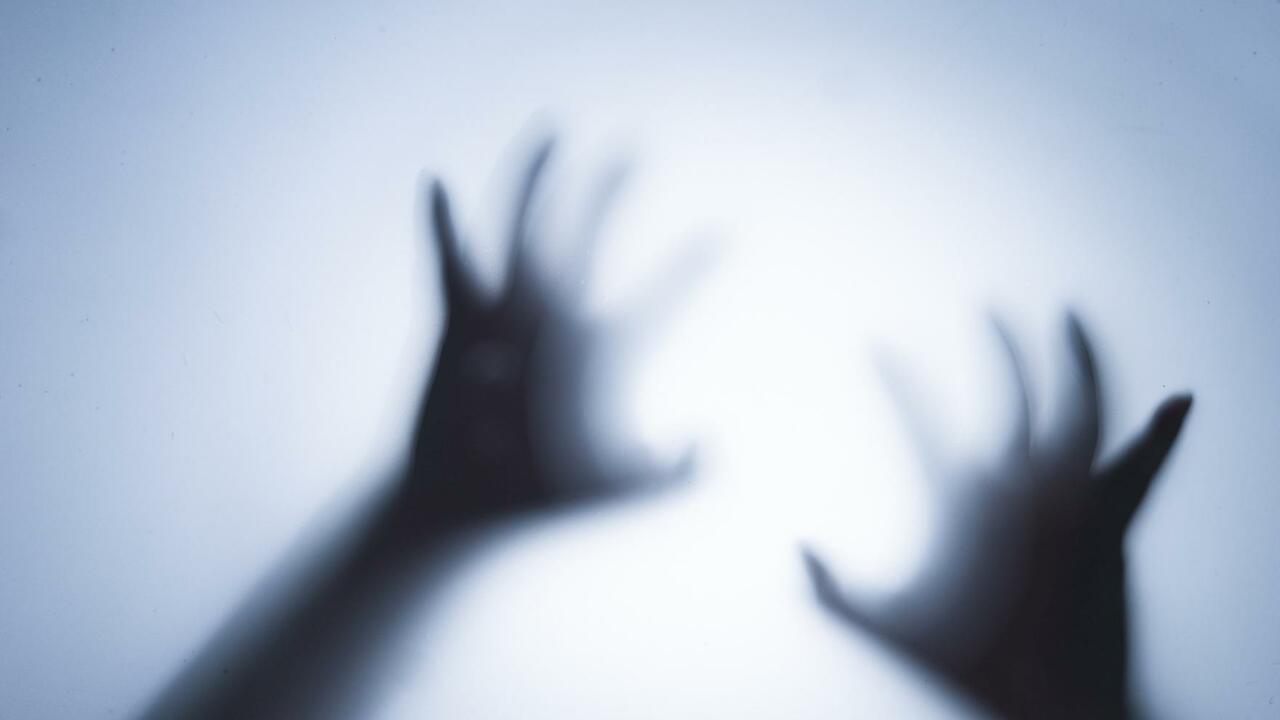二、牛李の党争
入れ替わりに部屋に入ったのは春鈴、喜びを隠しきれない笑顔を李徳裕に向けた。
「北方の寒い戦地での長いお勤めご苦労さまでした」
「春鈴、そなたの顔を見るのも久しぶり、変わりなかったか?」
それまで険しかった李徳裕の顔が和んだ。
「はい、お元気な殿のお顔が見られ嬉しゅうございます……。刻限も遅く、お疲れでしょうから、寝所の方にお食事を用意させますが、よろしいでしょうか」
「そうしてくれ」
「暖かい茶も用意させます」
と、春鈴は部屋を出た。
久々に屋敷へ戻った懐かしさから、李徳裕は扉を開け中庭の見える回廊に出た。目を引いたのは庭の中央に据えられた灰白色の巨石、大小不規則な窪みや突起が絡み合う複雑な造形を呈していた。
暗闇の中でも白く浮かび出る大きな石は太湖石と呼ばれ、父、李吉甫が遠く太湖の畔から運ばせた奇岩、石の地肌は長い年月を波に穿かれ特異な凹凸を形作り出し、光の差し込む角度、眺める方向や時間、その時々の見る人の心境で、恐ろしい妖怪にも慈悲深い観音にも姿を変えていた。
李徳裕は子供の頃から昼と夜では見え方の違い、他では目にできない奇怪な造形の太湖石を見るのが好きだった。
「今晩は何に見えるかな……」
と、胸の内で呟き、月光に照らされた巨石を見詰めたが、その夜の太湖石からは、何も生まれず何も連想できなかった。
乾いた風が首筋を撫で、襟元に手を当てた時、微かな甘い香りが匂うかに思われ、振り向くと白い裙に薄桃色の衫を纏って微笑む春鈴と目が合った。
「お食事の御支度が整いました」
「居たのか」
「申し訳ありません、お邪魔してはいけないと思い、声をお掛けしませんでした」
その夜、李徳裕は春鈴の酌で久々に西域の葡萄酒を口にした。心地好い酔いが緊張を解し、戦場で荒んだ心を春鈴の白い柔肌が包むように癒してくれた。
安心の表情を浮かべ、腕の中で小さく寝息を立てる春鈴を見ながらも、李徳裕の脳裏を巡るのは、皇帝交代の機に牛僧孺や李宗閔ら抑藩政策反対派が勢力を延ばそうとする動きだった。