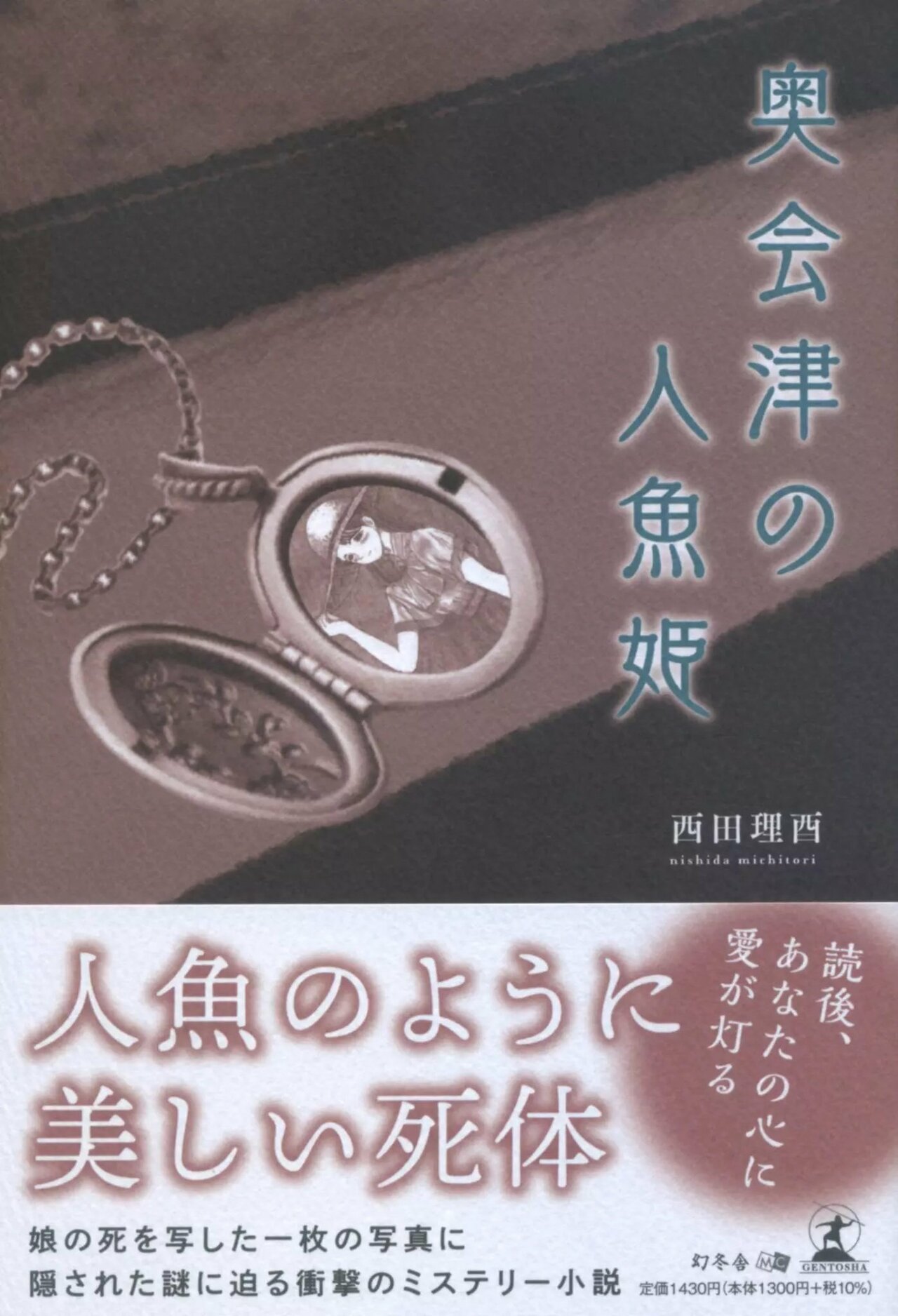……言い寄る男はたくさんいたのに、汐里はまったく関心がなかった。本人が話していたように、やはり付き合っていた相手がいたということか……。
「柳瀬には確か、ソースカツ丼のうまい店があったよな」
タブレットで検索しながら鍛冶内はつぶやいた。その後、観光案内ページを頼りに岩に張り付いて建っているお寺や観音堂などを見て回りながら、鍛冶内は柳瀬の古い町並みをぶらぶらと楽しんだ。
付き合ってる人がいた……。明るい子……。記憶が飛ぶ……。鍛冶内は長い待ち時間を経てやっと乗り込んだ帰りの列車の中で、印刷所で聞いてきたことを繰り返し考えていた。
付き合ってる人がいたという汐里の弁は、迷惑な相手を遠ざけるために、たまに女性が口にする言葉だ。明るい子という印象は、千景の持っている冷ややかな汐里のイメージからはほど遠いようにも思われるが、新しい環境の中で、人間は自分の良い部分を見せようとする生き物だから、案外矛盾はしていないのかもしれない。
「それにしても…………」
と、鍛冶内は思った。記憶が飛ぶとは、一体どういうことなのだろう。あるいは高校時代からシンナーか何かの薬物を、千景や乙音の知らないアパートの自室でやっていて、その後遺症でもあるのだろうか。
長山駅に着いて、まだ陽が高いのを見た鍛冶内は、今さらながら、駅の表側に設置されている、長山町の観光案内地図をしげしげと見た。
「長山の温泉を制覇でもするか」
竜神湖の方角に向かう坂の途中に、もう一つの共同浴場「鶴の湯」がある。日頃の運動不足は否めず、少し坂を上っただけで息が切れている鍛冶内は、その余分にかいた汗を流してもらうべく、財布を掻き回して小銭を取り出すと、こちらも無人の温泉場、鶴の湯の戸をくぐった。亀の湯よりも少しだけ全体的に狭く、古いたたずまいの鶴の湯には、珍しく先客がいた。
まだ20代だろうか。愛嬌のある日焼けした丸顔の男が、5人ほどで満杯の湯船を広々占領していたが、鍛冶内の顔を見て慌てて自分の陣地を狭くした。
「町外の方ですね。ここはシャンプーもボディソープも備え付けがなく、自前なんですよ。良ければどうぞ」と言いながら、自分の道具カゴを鍛冶内に勧めてくれた。
鍛冶内は、きびきびとした立ち振る舞いのこの男に好感を持った。