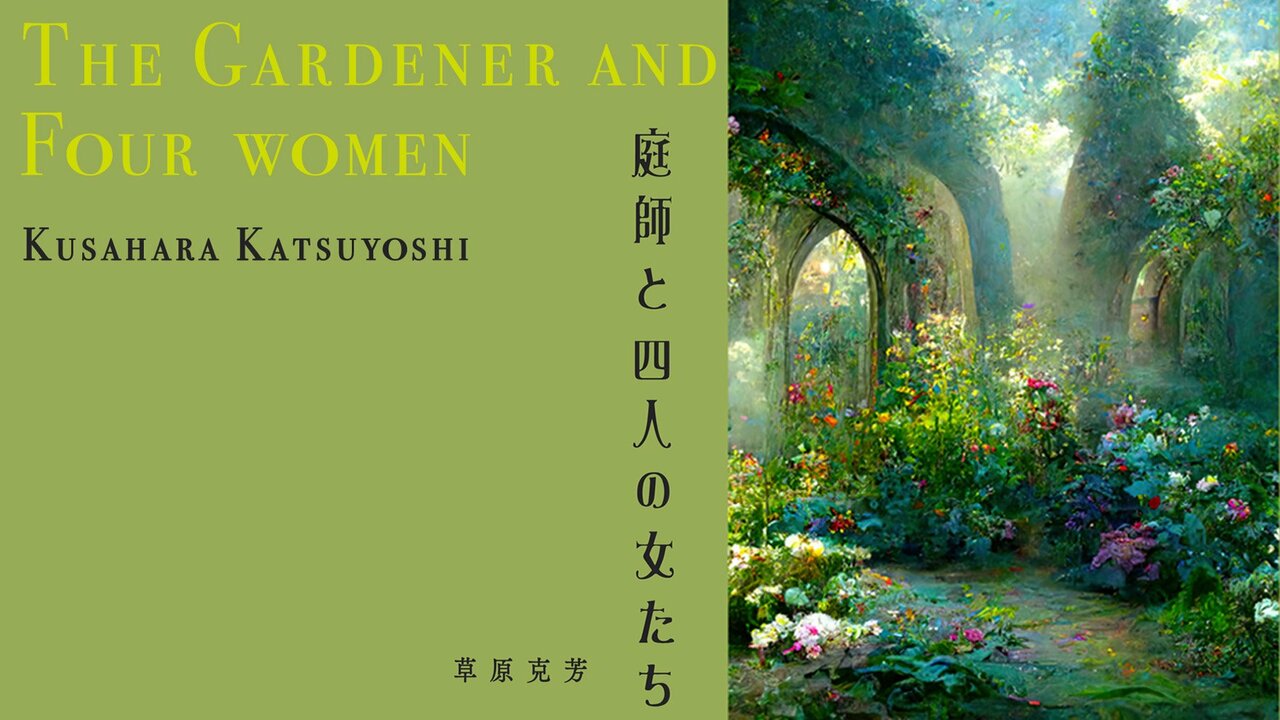庭師と四人の女たち
3
「そういえば、庭師が来るんだってね」
マス江は顎をしゃくった。黒崎耀子と袋田マス江は、それとなく距離を置いて座っていた。
客同士の相性というのは、難しい。それは睦子もよく承知しているつもりだった。こちらもまた、昆虫や蜥蜴や野鳥たちと同様、治外法権なのだった。
「どうすりゃ、すっきりと見栄えがするもんかねえ。あたしだって、地域住民なんだから、好みを言う権利はあるだろ?」
「そうそう。何かいいアイディア、あるかしら」
キッチンの前の店主は、グラスを洗いながら顔を上げた。マス江は太った体を捻って、片手で変てこなひさしを作って、庭の方を覗き込むポーズをとった。
「まずあの毛羽立った棕櫚はさっぱりして欲しいもんだねえ。あと、バナナの木。あんな、でかい象の耳みたいな葉っぱ、邪魔っ気だよ。端っこにある温室もねえ、壊れてて、お化けでも棲みついてるみたいだよ。こういうことは、最初のイメージが大切だわ」
「そう。最初のイメージ、庭の第一印象ね、わかるわ。よくわかる」
――と、そのとき扉が開いた。
「おろろ、噂をすれば影だよ」
マス江が舌打ちするように言った。道路の明るい外光を背景に、白い夏の帽子を被りながら現れたのは、葉山彩香であった。どことなく足元がふらついているのは、底の厚いサンダルのせいばかりでもないらしい。
「あらどうしたのさ、彩香ちゃん。そんな浮かない顔しちゃって」
彩香は白い夏向きの帽子を置いて、しばらく直立不動で何も言わず上を向き、鼻をひくひくさせた。
「どうしたのよ。言ってごらんよ」
そっと肩に手を置かれると、彩香は我慢しきれなくなったように
「辰郎に、辰郎に……」
と言って、みるみる大きな目を涙でいっぱいにした。
「女がいたんです」
一瞬、間があった。年かさの女たちは、目を合わせた。
「だァから、言わないこっちゃァないよ。あたしの直感は当たるんだ」
とマス江がうそぶいた。放心状態の彩香は、いまにも倒れそうな風情だった。
「彼に、別の生活があったんです。わたしの知らないところに、もうひとつの生活が。歯ブラシも二つ、マグカップも二つ、Tシャツも同じプリントのやつが二つ、枕もお揃いの色違いの枕が二つ。来年は結婚しようねって言ってくれてたのに。そういっていたのに。わたし、裏切られたんです!」