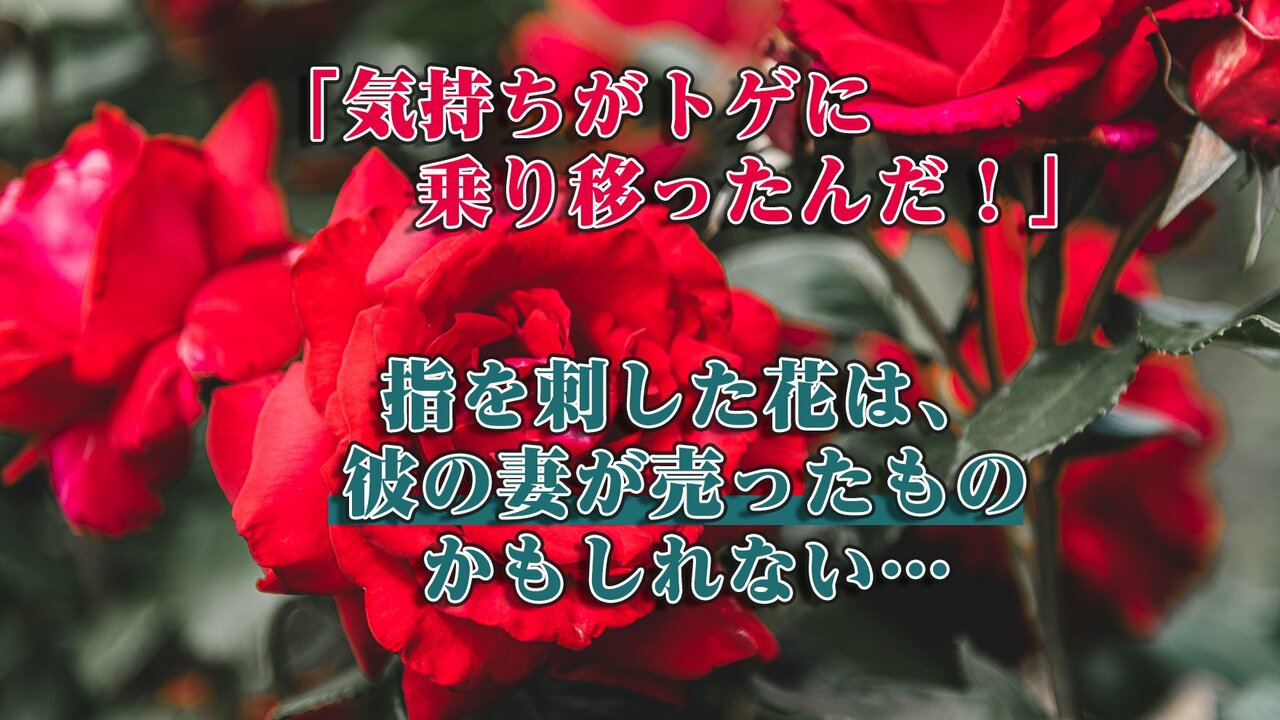花の棘
「花と野菜は同じってこともないでしょう」
孝介の声は歯切れが悪い。
よし子は聞かれたくはないのだろうと、若い人の方へ回った。
「あれ、およしさん、指に絆創膏なんか貼って、切ったの?」
「料理のうまい人が切るわけないだろ」
「じゃあ、噛まれたんだ」
「すっぽんかよ」
「お前も色気がないなあ」
「棘が刺さったのよ、あのお花の棘」
よし子が指さしたところには紫や白い小花が野趣の風情で活けられた篭があった。
「あっ! あの花、国道の花屋で買ったんでしょ。主任の奥さんが居るんだ」
「何言ってんだよ、お前酔っぱらったんだよ!」
「気持ちが棘に乗り移ったんだなあ」
「やめろ! やめろ!」
「知りもしないこと言うな!」
「いや知ってるよ、俺、見たもん。美人だぜー」
言い出しっぺの男を止めるみんなの慌てようがあまりにも真剣だったので、その場の雰囲気は却って収拾がつかなくなった。
酔いの戯言が、指の傷より深い痛みとなってよし子を刺した。
棘を刺した指の傷は一週間もするとすっかり治っていた。けれども気持ちの中に落ちた棘はなかなか抜き取ることができなかった。
よし子にとって一番のショックは孝介とよし子のことが若い人たちの間でも事実として知られていたことだった。人の口に戸は立てられないとはよく言ったものだ。
孝介の妻が花屋でパートをしている。そこの花がよし子の棘になった。恨まれてるんじゃないのかと言われたこと。慌てて止めた若者。
自分ではいろんなことを我慢して気をつけて暮らしているのに、噂だけは面白半分に先立ってゆく。