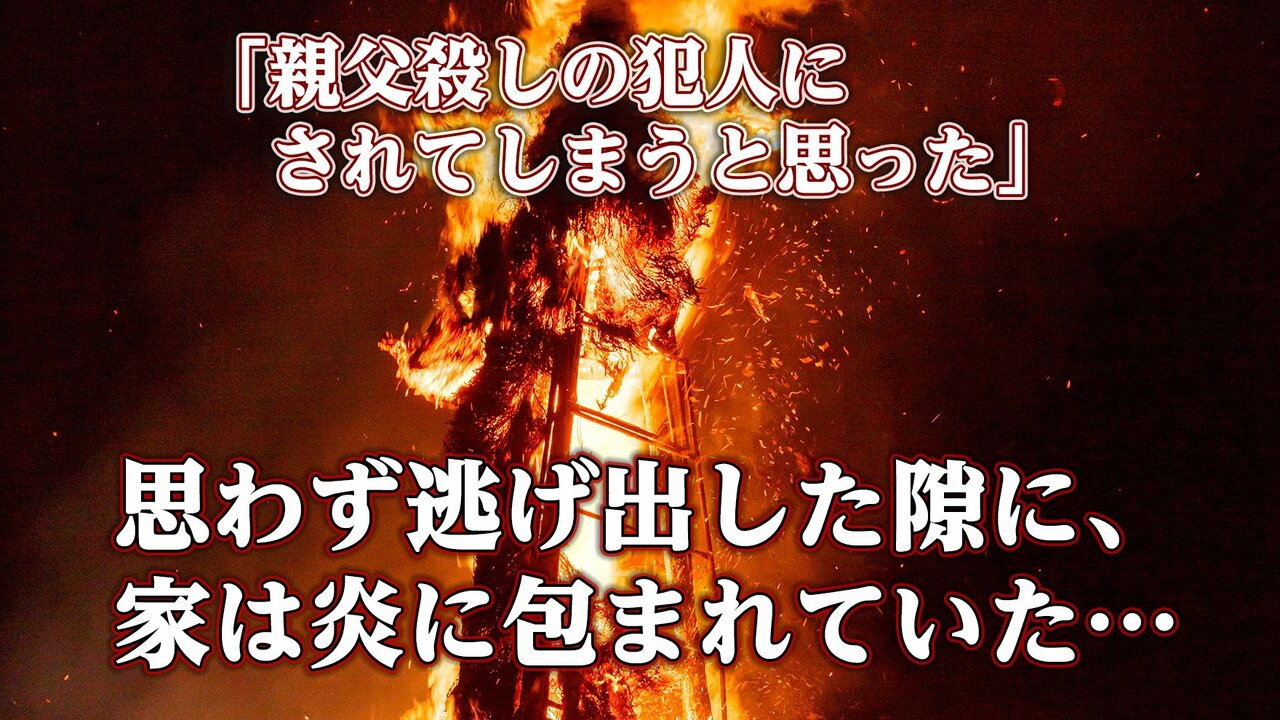Ⅰ レッドの章
依頼人
早いものであの夏の合宿から足掛け四年の月日が経っていた。
拘置所のガラス越しに久し振りに会う正次は以前より痩せた印象だった。久しく日光不足とみえて顔色が悪い。学生時代から痩せてひょろっとした男ではあったが、彼の記憶にある裕福に育ったお坊ちゃんの雰囲気は影をひそめ、表情は暗く目には絶望の色が現れていた。
彼は国選弁護人は全く頼りにならないと言った。彼の無実を信じず、父親殺しを大人しく認めた方が有利だと言う。そしてその動機は彼の恋人を父親が盗んだからだと申し立てて裁判官の同情を買った方がいい、などと言うのだ。
「それは本当なのか? 親父さんが君の恋人を盗んだというのは?」
掛川が尋ねると正次はしぶしぶながらそんなことがあったと認めた。
「親父はその女のことでお袋と仲違いし、お袋は家を出て行った。でもそんなことで親父を殺したりはしない。それに火事の直前に親父は今までのことを水に流して和解したいと言ってきたんだ。親父の会社に入れと言おうとしていたのかも知れない。
常々親父は、僕は柔すぎて気性の荒い海の男相手の海運業には向かないと言い、仕事は継がせないつもりだと周りにも公言していた。君も覚えているかも知れないが、僕は卒業後の身の振り方が決まらず、一年留年して、卒業後もその後新しく出来た大学の研究科に籍を置いていた。
でも親父と仲違いしたり、親のすねかじりにも嫌気がさして勉学を断念し、親父のコネには頼らず独力で銀行関係の仕事を見つけて勤め始めた。
それをどういう風の吹き回しか、親父は寄越した手紙に『結局信じられるのは身内だけだ、他人は信用ならん』と書いてきた。僕は長い間義絶状態だったから親父が何を考えているのか全く分からなかった。
僕は迷ったが結局親父に会いに行くことにした。でも家に着いてみると親父は二階の居間の暖炉の前で倒れて死んでいた」
「それはいつのことだ?」
「一昨年の十一月五日午後八時四十分、いや四十五分くらいだったかも知れん。
親父は午後八時半に鶴前の家に来いと書いてきたが、僕は遅れて行ったんだ。事件当夜親父は町の中心街にある例の和洋折衷の大きな家に一人で住んでいた。
お袋は親父に女性問題が起きて親父と喧嘩して以来、家を出て福知山の親戚宅に行ったきりだった。住み込みの女中は休みの日で不在だった」
「家の玄関は施錠されていなかったのか?」
「玄関は開いていた。でも普段はお袋がいたし女中もいた。女中は昼も夜も鍵をきちんと閉めていた。でもあの日は二人ともいなかったんだ」
神林禎一郎が一人でその家にいることを知っていた誰かが犯人だと正次は言う。
犯人として誰か思い当たる人物がいないか問いかけると彼は首をかしげて、「家の事情を知っていた人間は複数いたかも知れない。親父の会社や取引先の人々、近隣の人々もあの家によく来て飲み食いしていたからね」と言った。
だがそれだからと言ってこれが怪しいと断言出来る人物は今の時点ではいない。