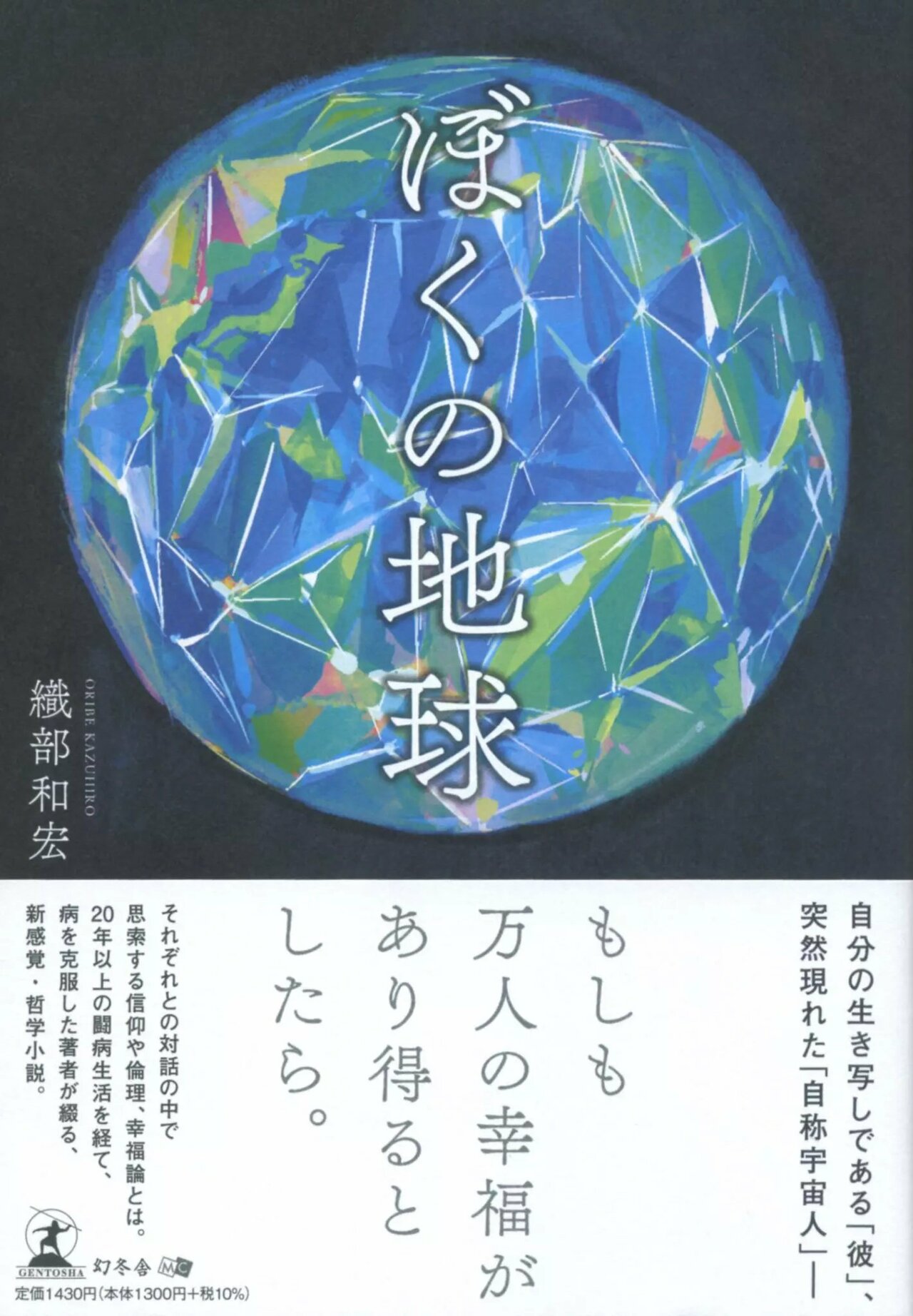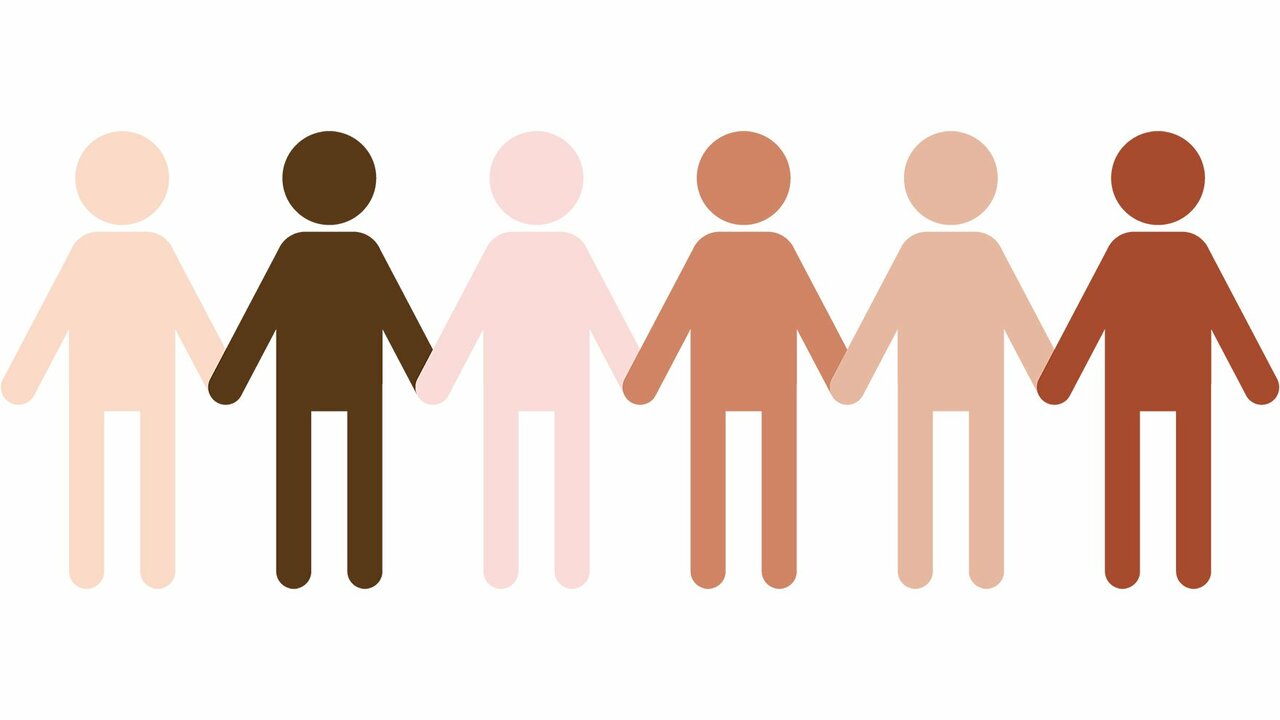「好き」の対象とは、それが何であれ、それは個性の分身である。したがってそれが否定されれば、個性はその瞬間死ぬ。しかし不思議なことに、取引を優先させる者(そもそも彼には「好き」があるのか?)にこそ社会的関心は寄せられる。
ここで問われているのは「如何に生きるか」であるので、容易には譲歩できない箇所でもある。
もし人生が事実の積み重ねによって出来上がっているのであれば、それは、信頼できる客観的な数値によってのみ最終判断が下されることになる。しかし、人生は認識によって構成されていると考えるのであれば、その主体が、その人生をどのように総括するかによって、それが直ちに彼の最終的判断となる。
つまり「(彼が)それでいいと言えばそれでいい」のである。
「何を」ではなく「如何に」
ここで「好き」が選択肢の確保をその目的としていることが、おおよそ理解することができる。「好き」を模索する少年少女は、「好き」を知ることで自分の人生の選択肢を広げようとしているのだ。
選択肢とは何か?
可能性のことである。
ここで青春が復活する。私と彼は同じような青春時代を送ったのだ。なるほど、そこには不登校もあったかもしれない。選択肢を奪われることの、戸惑いと不安。彼の言うとおりだ。すべての負は肯定されなければならない。
何のために?
存在のために。
では負とは何か?
それは日常に散在するすべての不都合のことである。
私も彼も、その環境故に、またその性質故に、また不登校経験後は、克服されなければならないその過去故に、平均とは異なる青春を歩むこととなった。
16歳にしてすでに、「今」は常に「過去」と一体化しており、負の特別枠に組み込まれた時間は、社会的に有効な結果が一定期間内に示されない限りは、そのフリーズされた状態から解放されることはなかった。