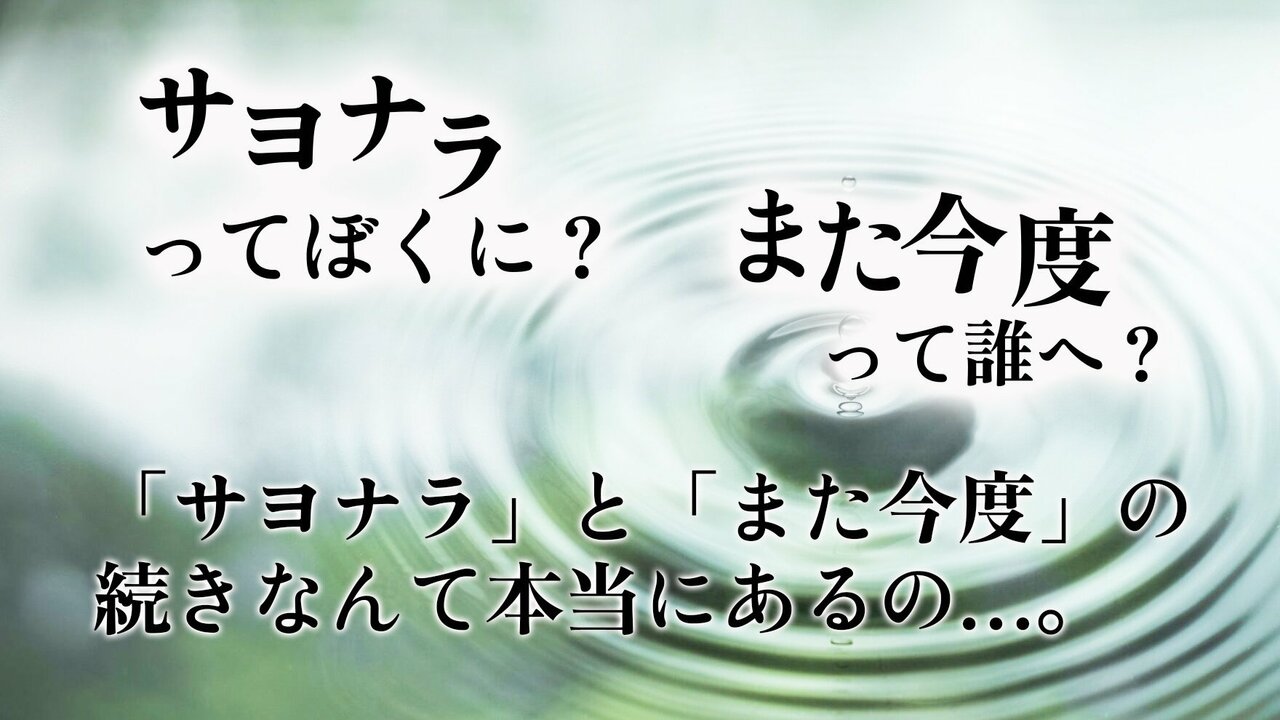何という喜びでしょう。
葉の縁にぶら下がりながらであっても、見ようとして見れば、たくさんのことがわかってくるものです。目をつぶっていたときには気付きもしなかったものごとが、すべてがすべて新鮮なまま俄かに押し寄せてきて、ひとしずくの心はいっぺんに彩られていきました。ひとしずくはことばにならない感嘆の声を幾度となく漏らしました。
植物の葉にしても、いろいろな形の、いろいろな色があるということを、ひとしずくはこのとき初めて知りました。あれほど恐れていた地の底も、朽葉に蔽われふかふかとしていて、居心地は悪くなさそうでした。自分の目で見て知るということが、どれほどの光をもたらすのか。ひとしずくは、この先もずっとずっと、この喜びを忘れることはありませんでした。
ひとしずくは、視界に広がるすべてのことに夢中でした。それが何であるか、何者であるかなどはひとしずくにとって、大した問題ではありません。ただ、この世界にはこういうものがあるのだ、こういう音があるのだ、こういう香りがあるのだと知ることができるだけで、それだけでひとしずくは十分嬉しかったのです。
「目をひらいているほうが、面白い」
ひとしずくはにっこりとほほえみました。
とはいえ、ひとしずくが見つめている世界は、重なり合ったクマザサの葉陰から見える景色だけでした。彼が体感し得る世界など、ほんの些細なものでしかありません。視界の限りを己の世界と区切ることの危うさもあります。ひとしずくの視界の外にこそ、世界はどこまでも広がっていて、ひとしずくを今か今かと待ち構えているのです。
ひとしずくは、これからどこへ向かおうかしらと考えていました。好奇心やそのエネルギーは、泉のようにとめどなく、滾々(こんこん)とからだの内から湧き出てきます。しかし、それらの力を向ける先がまだ定まらぬがために、ひとしずくは葉の縁につかまりながら曲芸のようにからだをゆらして落ち着かずにいるのでした。