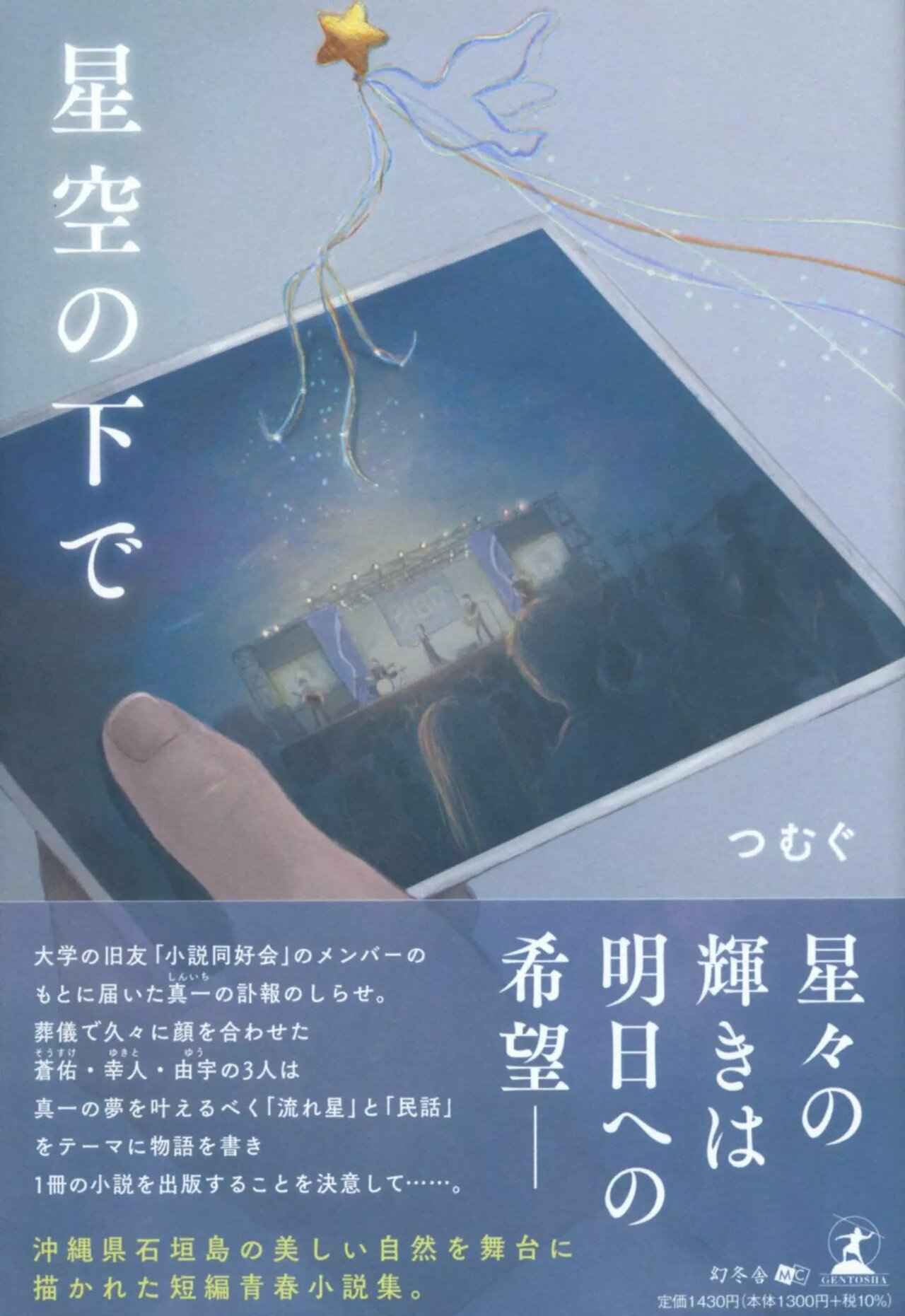3
「陶芸の世界には、『あわい』という言葉があります」
陶芸教室「アトリエ」では、本焼きを終えた作品を塾生のみんなで鑑賞する会を設けている。他の作品を鑑賞することで、目利き力を鍛えることができるからだと泉先生は言う。でも、塾生のみんなが何よりも楽しみにしているのは、泉先生の陶芸講話だ。いつもは口下手な先生だが、このときだけは、声のトーンが高くなり饒舌になる。生き生きとした先生の姿が頭に浮かんでくる。私は、いつものように点字ディスプレイとボイスレコーダーで、先生の話を記録している。
「皆さんは、この漢字をどう読みますか?」と、泉先生。
私の席の隣に座る佳代さんが、私の手を取って、自然の「自」と「ら」をなぞってくれた。
「これは……みずから、と読むんじゃないのかい?」
「いや、おのずから、とも読めるよ」
塾生たちが口々に「おのずから」と「みずから」を半信半疑で言う。泉先生は、嬉しそうな声で話を続けた。
「どちらも正解です! しかし、陶芸の世界では、これら二つは対比として用いられます。
『おのずから』とは、自然が成すことを言います。自然現象のことです。例えば、雨が多い日と晴れが続いた日に完成した作品が見せる顔は違います。反対に、『みずから』とは、私たち人間が作為的に行うことを言います。例えば、成形するときに、私たちの頭の中には、イメージが浮かんできます。そして、そのイメージに少しでも近づけようと作為的に土をコントロールするわけです。」
先生は、いよいよ話の核心に触れるときには、決まって一呼吸おいてから、辺りが静寂に包まれたあと、静かに言葉を贈る。
「『おのずから』と『みずから』の二つの存在が、互いに張り合い、調和する。そして、影響し合うことを総称して『あわい』と呼ぶのです。陶造形も人間と同じように、張り合う存在がいるからこそ、より美しく、より生き生きと生まれくる。みなさんも、そう思いませんか?」
泉先生の話が終わると、工房中に拍手が沸き起こった。