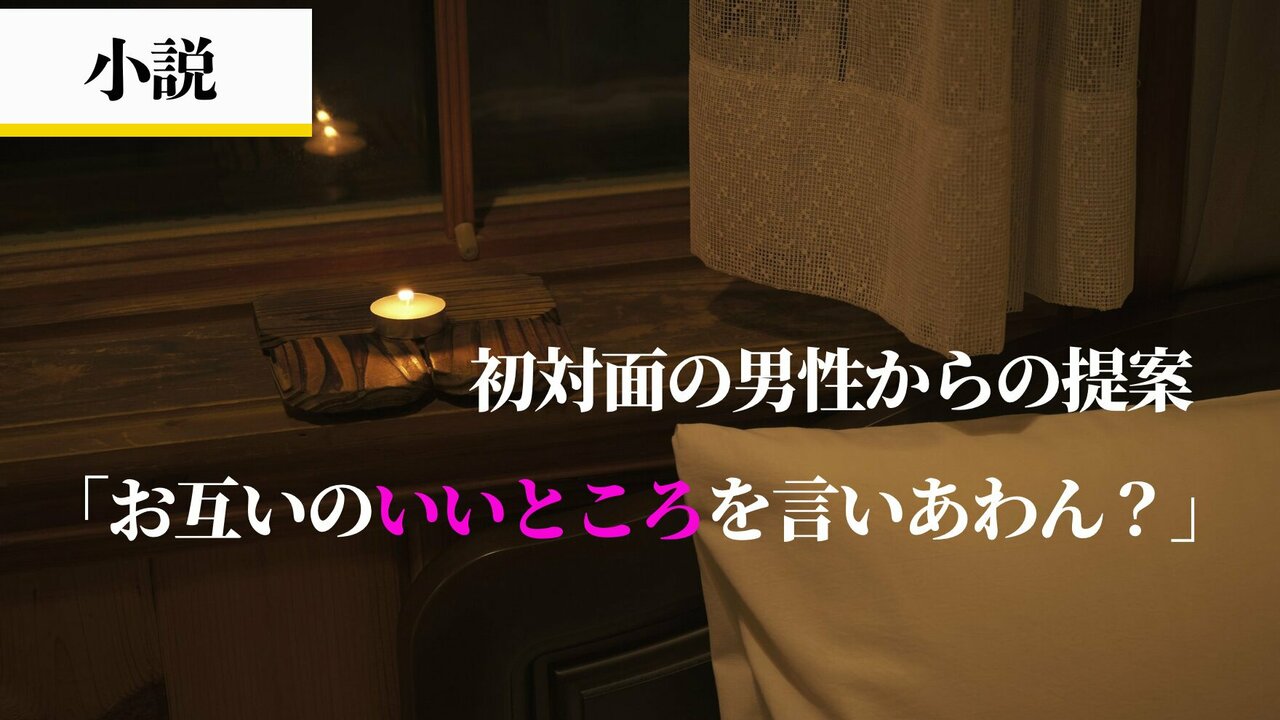飛燕日記
ぞんざいに身に着けたバスローブは、脱がされて床に折り重なった。背伸びをして痛いほどに顔を上に向けると、絡めとられるようなキスをされる。手が絶妙なタッチで背筋を這い、膝から力が抜けそうになった。今まで何十人もの女性にこうして触れてきたのだろう。人のいいところを知りつくしたような、慣れた愛撫だった。
「どこが気持ちいい?」
冷えたシーツで身体を休め、火照りを鎮めたかった。中は隙間なく密着し、擦れる箇所すべてが熱を持っている。呼吸も精いっぱいなのに、どうしてほしいかとか、気持ちいいかと聞かれて、恥ずかしさでどうにかなりそうだった。
焦れたように、ねえ、ともう一突きされて嬌声を上げた。黙っていればまた急かされる。言葉にならない声で答えると、再びピストン運動がはじまった。逃れられない熱に懐柔されていく。もう何度いっただろうか。身体中で泡のような快楽が弾け続け、感度はとっくにおかしくなっていた。
この行為ははじめてではないのに、まったくいつもと違う。彼は次第に動きを速めていった。体温が、呼吸が、重なって混ざりあう。荒波のような快楽に揉まれ、不安と激情に飲みこまれた。やめてとも、もっとともわからない声を上げてしがみついた。腕をほどかれ、腰に指を突き立てられる。鳥肌が立った。彼は私を見下ろしながら果て、私もまた達した。いつの間にか目を閉じていた。半身を起こすと、大の字で寝ていた彼に腕を引かれる。
「気持ちよかった?」
これが演技だと思っているのだろうか。頷くと、また会ってくれるかと聞かれた。それにも、うんと答える。さらに、なんでと聞かれた。酸欠と快楽の余韻で頭が回らない。けれど、よほど問題が起こらないかぎり、そうするように感じた。
「大きかったから」
そう言うとなぜか、タツマさんは少し傷ついていた。家に帰ってから、逆に連絡を切られるかもしれないと危ぶんだが、それから二週間後に会った時には、なぜか職場の名刺をくれたのだった。年が明けると再びマキさんと会うようになり、タツマさんとも月一か二で会い続けた。それだけ運動すれば空腹になるのは当たり前で、食事に行く相手を探すのも当然だった。