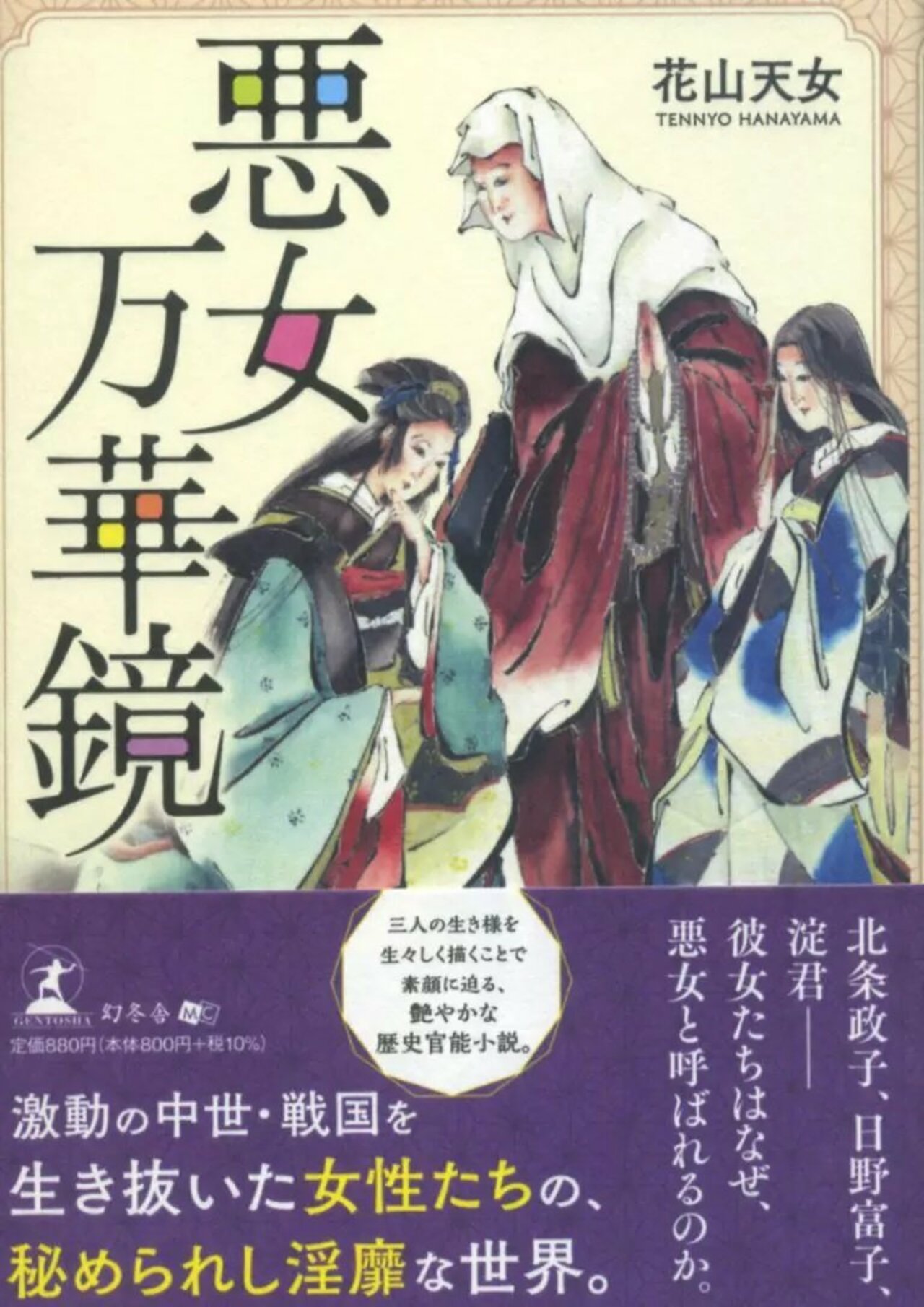「ヒ~ッヒ~ッ、あああッ…ヒ~ッ」
糸を引くような女囚の泣き声が山塞の牢内から空しく暗闇に消えていく。外の濃い闇には、小絶えていた雪が再び降り注ぎ、御所内のお牢の庇に積もったそれが物憂げな音を立て中庭に落ちた。
あろうことか、亀の前はその白い肌を荒縄で括くくられて、天井の太く煤けた梁から、高小手縛り(後手に縛る際に手首を平行にしないで十字に組んで縛り上げる)で井戸の釣瓶さながら玩奔のように吊り下げられ、かろうじて片方の足で床を支えながら、肉体は前後左右に揺らいでいる。
女囚は亀甲縛りの丸裸に剥かれ、麻縄はほどよく膨らんだ乳房を上下に締め上げ、その為か中央の双の蕾は大きく突き出して喘いでいる。外の冷たさとは無縁、妖しげな脂粉の香りでご牢内はむせ返るばかり、はや咎人の全身からは大粒の汗が滴り落ちて、縄化粧の柔肌をヌメヌメと照り輝かせている。
その赤縄は臍下三寸で恥じらうようにして、僅かな潤みをみせる花門を菱形に飾っていた。さらに、軟らかそうにそよぐ繊毛の花門を前に押し出すようにして、別の荒縄がもう一方の足を極限まで広げさせ天井の梁から吊り下がっている。牢主は一本の赤い越中褌を取り出し片足の吊り下がった秘所を覆ってやった。せめてもの心使いのつもりであろうか。
「おほほ、このいやらしい淫売女はもう気分を出しているのかえ、そなたは、どんな男の股座の白い縮毛を見てさえ、怪しからん気を起こすほど淫奔なくせに、ほかにもまだ間男の一人や二人がないという法はあるまい。今までたんと上様に可愛がっていただいたのかえ、ええツ、けなるい(うらやましい)ことじゃ、肖かりたや、肖りたや」
牢主の政子は妖しい湯文字姿で亀の前を睨め付けたが、その姿はにっくき女囚を裁くために現れた白蛇明神さながらであった。
(何という女だ、これ程恥ずかしい目にあわされても、少しも容色が衰えないばかりか、蒼いほど白い肌がいっそう光沢を増し、さわるとベットリと脂肪がつきそうじゃ)