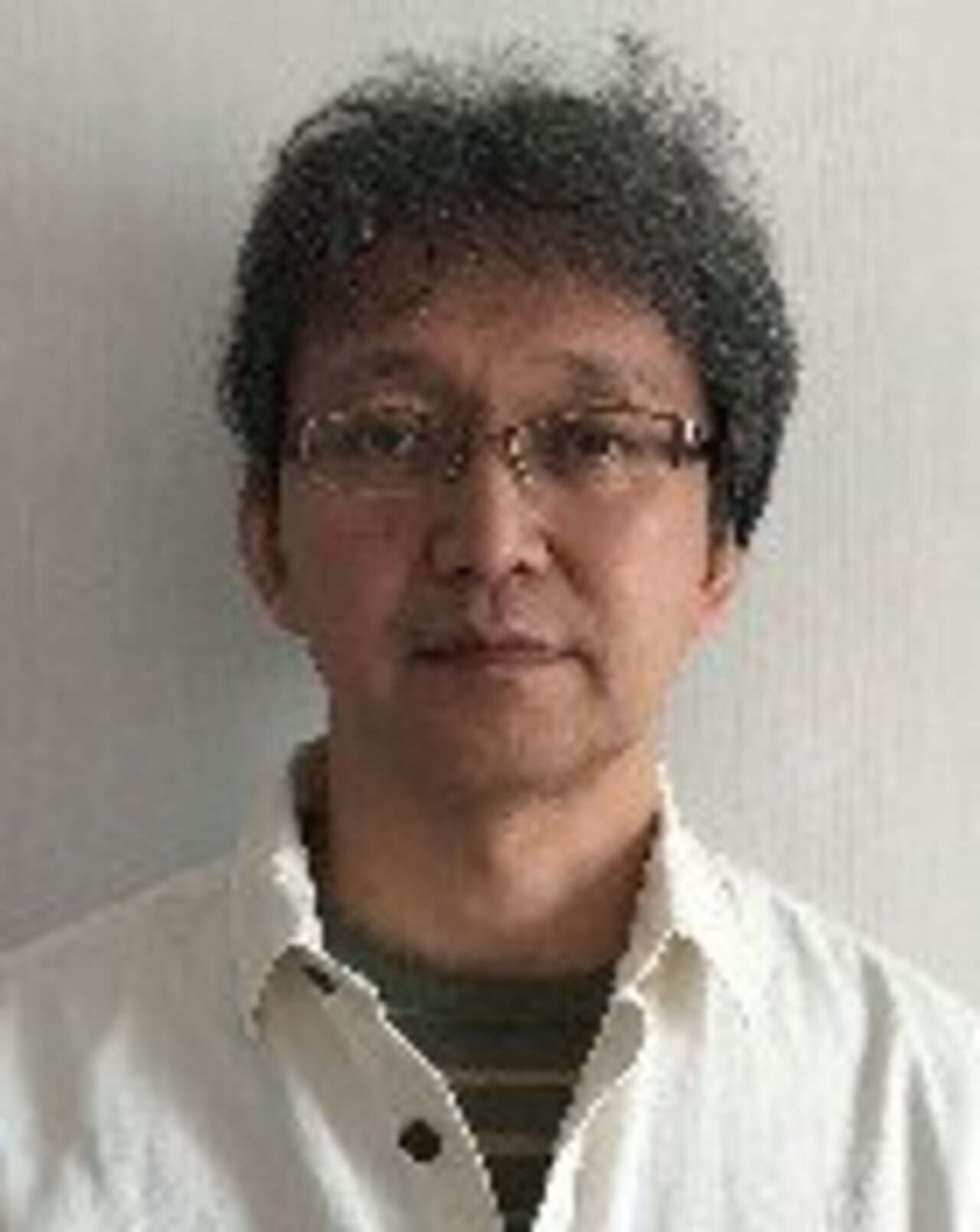「ものすごくいい時間を過ごせたってこと?」
「うん、そうねえ、何かに体ごと持っていかれている感じ。あんなの初めてかな。拍手受けてお辞儀した瞬間、思わずピアノの金色のロゴを確認しちゃった」
「これがBösendorfer(ベーゼンドルファー)かって?」
「そうなの」
ベーゼンドルファーで弾いたショパンの幻想ポロネーズが和枝と自分を急速に近づけてくれている、と廉は感じていた。和枝の音は廉にとって、真っ直ぐ心に届く大好きな音になっていた。
和枝は仙川にキャンパスがある音楽大学のピアノ科出身だった。演奏家としての名声を求めバリバリ進んでいく技巧派タイプではなく、競争の世界からは少し距離を置き、自身の音をじっくり練り上げていくタイプのピアニストなのではないかと廉は勝手にイメージしていた。
現実には和枝が、卒業一年後に「よこはま音楽コンクール」でモーツァルトのソナタ14番を弾いて一位を獲ったことは知っていたが、廉のイメージはあくまでも求道者的なピアニスト像だった。そしてそういう人の演奏を、この先も傍らでずっと聴いていきたいと思った。
翌日、和枝から二次予選通過の知らせがあった。本選は三週間後、大阪フェスティバルホールで開かれ、和枝を含め十人が舞台に立った。その日の夕方、仕事中の廉に大阪の和枝から電話が入る。
「うーん入賞はなかった。まあ、入選できただけでも褒めてください」
笑って通そうとしたようだが、涙で声が途切れた。大阪と東京の距離を、廉はもどかしく思った。