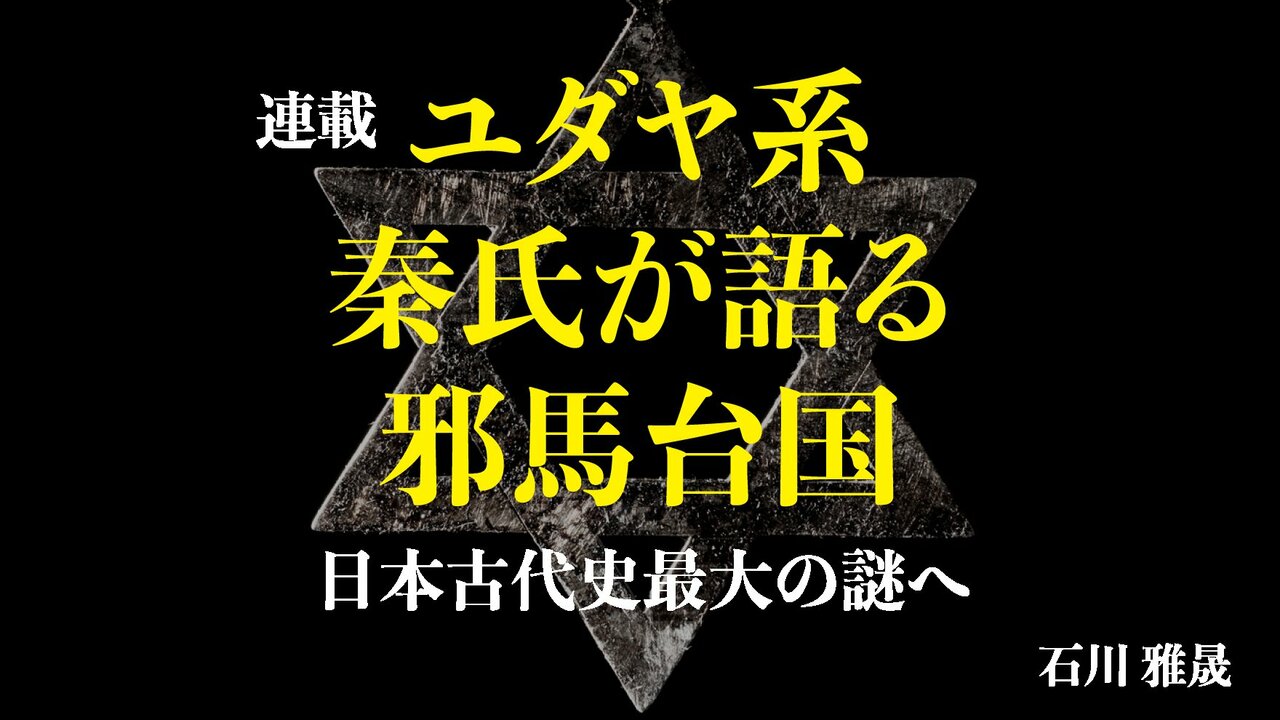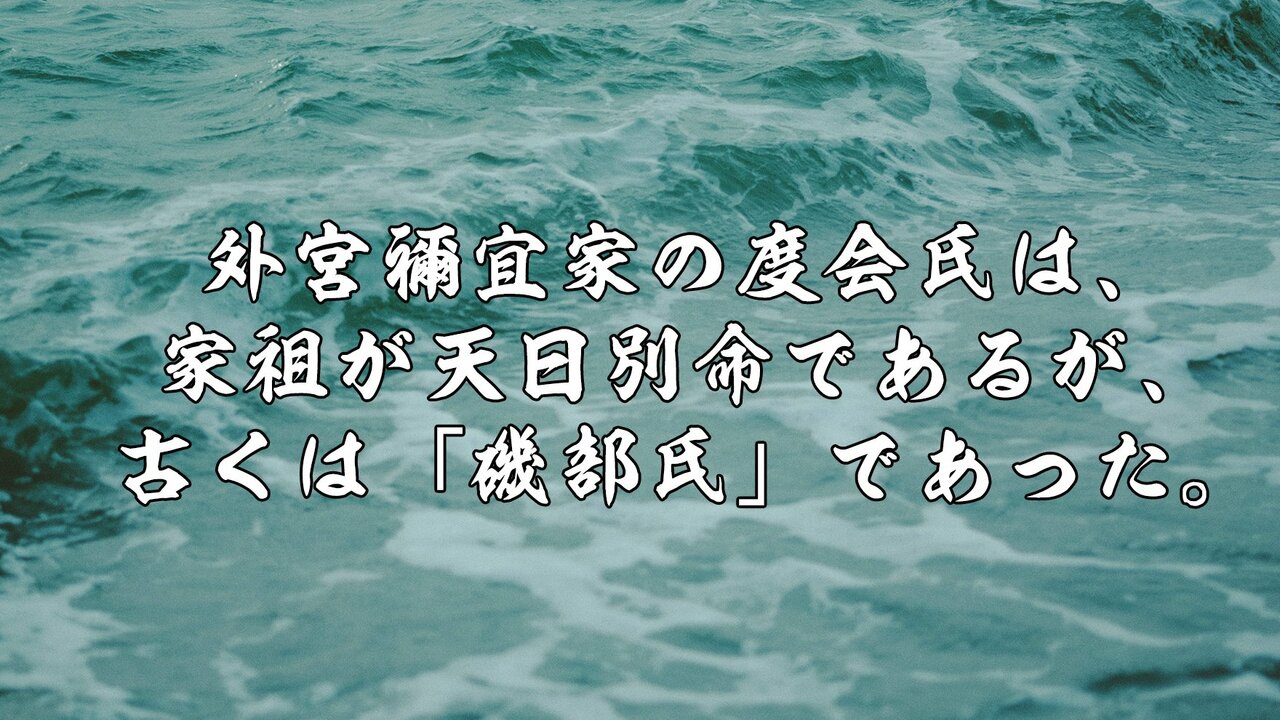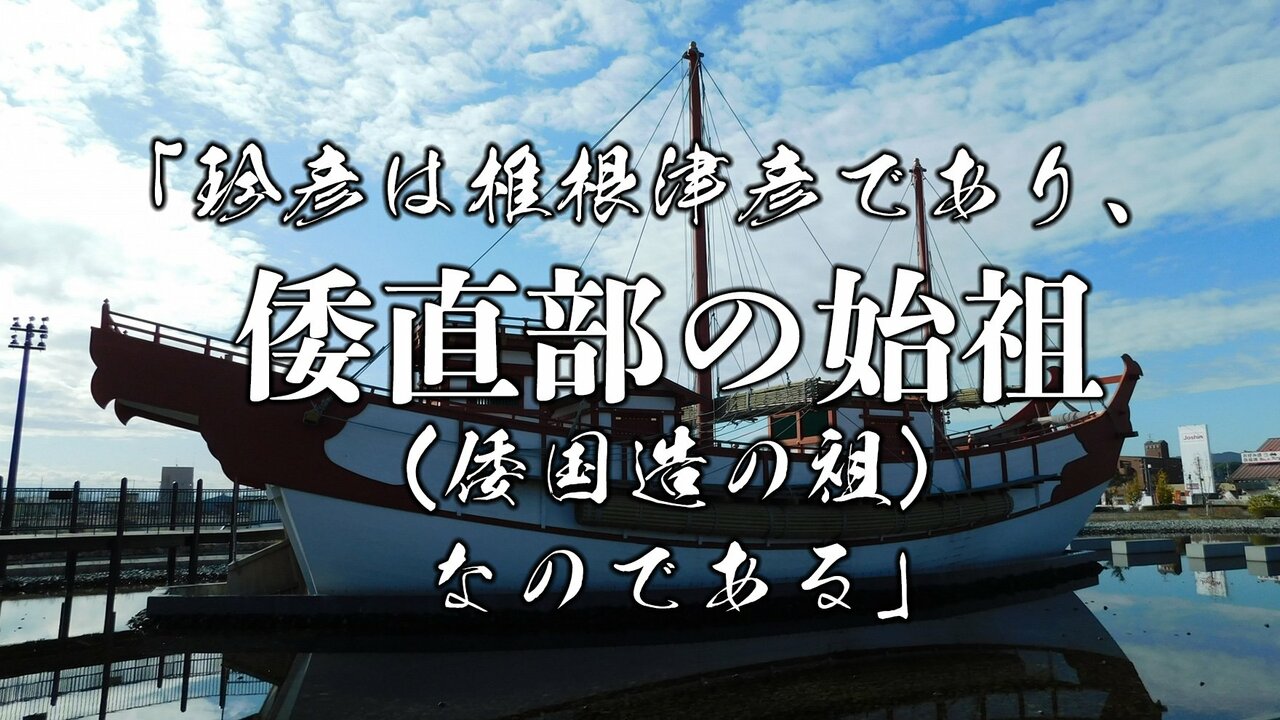第一章 伊都国と日向神話
6.伊都国から出土した三種の神器
さて阿曇目などの話の続きであるが、山幸彦(山の民)はさまざまな試練を乗り越え、最終的には海の民を味方にする。その方法はやはり婚姻関係による関係強化であった。
海神の娘二人との結婚で、二代にわたって閨閥を強化した天孫族は、阿曇目の海人族の取り込みに成功するのである。海人族の首長と婚姻関係をもつことによって、その配下の人々の使役権までも手に入れたことになる。
その後に起こった出雲との国譲り戦には、兵站物資や兵士の海上輸送に、大きな利益をもたらすことになる。つまり、日本海や瀬戸内海の制海権を確保したことを意味するのである。
阿曇目は阿曇族ばかりでなく、久米一族にも見られる。神武天皇が皇后を選ぶときに、久米氏が登場してくる。野に遊ぶ七人の媛女(おとめ)のなかの一人を神武が見染たので、大久米命が仲介役をしたのである。
ところがその「伊須氣余理比賣(いすけよりひめ)」に、逆に質問された。「どうしてそんなに「鯨(さ)ける利目(とめ )」をしているのか、と。目の周りの入れ墨で、目が割けたように見えたからである。
ここに大久米命、答へて歌ひけらく、
媛女(をとめ)に 直(ただ)に遇(あ)はむと 我(わ)が鯨ける利目
とうたひき。故、その媛子(をとめ)、「仕へ奉らむ。」と白しき。
このようにして、伊須氣余理比賣は神武の皇后になったのだが、大久米命の割けた目は、大和盆地の女性にはたいへんな驚きであったのだ。
大久米命が神武天皇の側近であったのには、理由がある。「神武東征」の最終局面において、軍事的貢献が大きかったからであった。熊野から回り込んで奈良盆地の東側に出た神武軍は、大和国宇陀郡に根を張る兄弟と戦うことになる。
神武に対しては、兄は武闘派、弟は和睦派であった。この兄を攻めたのが、二人の武将であった。
「ここに大伴連等(おほとものむらじら)の祖(おや)、道(みち)の臣(おみ)の命、久米 直等(くめのあたへら)の祖、大久米命の二人」として登場するが、大久米命の目の周りは、海人族に特徴的な阿曇目をしていたのである。
大伴氏も久米氏も、初期の大王に仕えた軍事氏族として、勇名を馳せるのである。ここでは大伴氏と久米氏は同列に扱われているが、しかしのちには大伴氏が大王家筆頭の軍事氏族になっていく。
奈良盆地における豪族の配置を見ても、三輪山の天皇家にとっては、北に物部氏・南に大伴氏を置いて、軍事優先の布陣を完成させるのである。
一方の久米氏は三輪から少し離れた、畝傍山の南西に居住地が割り振られて、他の豪族たちに囲まれるような位置を占めることになる。
自然に大伴氏は、久米氏をリードする形になって、久米一族・海人族の総元締めのような立場になる。後世の大伴家持の歌にも、最古の軍事氏族としてのプライドが感じられるのである。久米氏との関係でも、古くからの血縁関係があったのであろう。
『万葉集』巻第十八(4094)に載る、大伴家持の作である。
「陸奥国(みちのくのくに)に金(くがね)を出(い)だす詔書を賀ほく歌一首 并(あわ)せて短歌」の中の、大伴家に伝わる伝承を詠った部分である。
大伴(おほとも)の 遠つ神祖(かむおや)の その名をば 大久米主(おほくめぬし)と負(お)ひ持ちて 仕(つか)へし官(つかさ) 海行かば 水漬(みづ)く屍(かばね) 山行かば 草生(む)す屍 大君(おほきみ)の 辺(へ)にこそ死なめ 顧(かへり)みは せじと言立(ことだ)て ますらをの 清きその名を 古(いにしへ)よ 今の現(うつつ)に 流さへる 祖(おや)の子どもそ 大伴(おほとも)と 佐伯(さへき)の氏(うぢ)は 人の祖の 立つる言立(ことだ)て 人の子は 祖の名絶たず 大君に まつろふものと 言ひ継(つ)げる 言(こと)の官(つかさ)そ 梓弓(あづさゆみ) 手に取り持ちて 剣大刀(つるぎたち) 腰(こし)に取り佩(は)き 朝守(あさまも)り 夕(ゆふ)の守(まも)りに 大君の 御門(みかど)の守(まも)り 我(われ)をおきて 人はあらじと いや立て 思ひし増(ま)さる 大君の 命(みこと)の幸(さき)の〈一に云ふ、「を」〉聞けば貴(たふと)み〈一に云ふ、「貴くしあれば」〉
引用部分の最初に、大伴と大久米の関係が詠われている。「大伴の 遠い祖先の その名を 大久米主と 呼ばれて 奉仕した職柄」であると、大伴の先祖が大久米の主人筋と呼ばれた、過去の軍事組織の伝承を語っている。
家持まで伝えられてきたのは、その昔、大伴氏が海人族の久米氏を配下にもっていた、という事実であると思われる。
また別途、佐伯氏とも軍事協力関係があったと言い伝え、大君の御門の守りを厳しくせよと戒めている。
軍事組織が上意下達構造になるのは、指示命令系統を厳格にするため、やむを得ないことである。大伴と久米もそのような上下関係に組込まれていった事実が、この長歌には反映されているのである。
(ここは、大伴氏と久米氏の関係を後述する、とした部分である。)