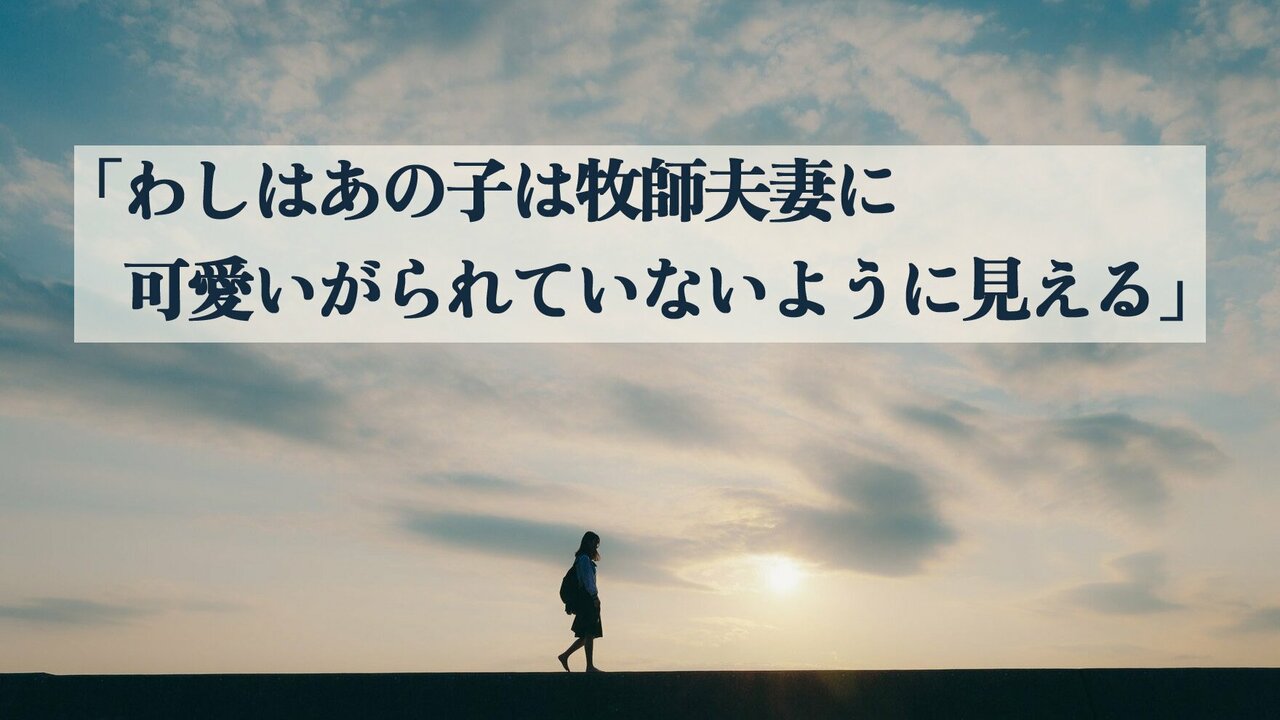第一部 銀の画鋲
「カトリーヌの謎の言葉」
「ワルツさんは、一篇の詩さえ書かない詩人だよ」
カトリーヌは僕の眉間を撫でた。僕にはとっくにわかっていたよ、カトリーヌ。ワルツさんは、星を見て銀の画鋲とか言ったり、風の中に答えがあるとか言って、日がな一日木枯らしの中に立って、風邪をひいたりする。
「心の中に溢れるほどの透明な言葉を持っているんだ。でもあの人は語らない。口にしたり文字にしたりする必要がないほどあの人は遥かな場所にいる。でも、私はワルツさんの書いた詩を一度でいいから読んでみたいと思うよ」
僕は眠さをこらえてゆっくり瞬きをした。
僕たちが本屋に戻ると、牧師さんはもう帰ったあとだった。扉を開けるなりカトリーヌはワルツさんに尋ねた。
「ワルツさん、牧師さんは私のことで来たんでしょう」
ワルツさんは本から目を上げて丸縁眼鏡を外しカトリーヌを見つめた。牧師さんはワルツさんに頼んだそうだ。人手の足りない慈善学校が、カトリーヌが来ることを望んでいる。だから、ワルツさんにカトリーヌを説得してほしいって。
「カトリーヌ、そんなにこの島が好きなのか」
「じいさん、私はここにいたいの」
「そうか」
ワルツさんは深くうなずいて、窓際に近寄った。
「ここはなにもない島だ。舞踏会もバザーもない。サーカスも見られない。そんな島じゃ。それでもカトリーヌはここがいいと言うんだな」
「私はついこの間までこの緑の扉を開けることができなかったんだ。この扉の前に立つたびに、棚に並んでいる本を見てみたいって思ってた。でもね、ミルク瓶を割ったおかげでワルツさんとも話ができるようになった。本当はもっと早くにここに来たかった」
「本がこんなにたくさんあって、私はここにいるとクラクラするほどなんだ。あの本も読みたい、この本もって、本たちが私に語りかけてくるんだ。読んでほしい。私はここよって」
本が自分を呼ぶなんて、カトリーヌはまったく奇妙な女の子だ。でも、昼寝を邪魔された僕は眠たくて仕方がない。部屋の隅で丸くなった僕の耳からふたりの話し声は次第に消えていった。