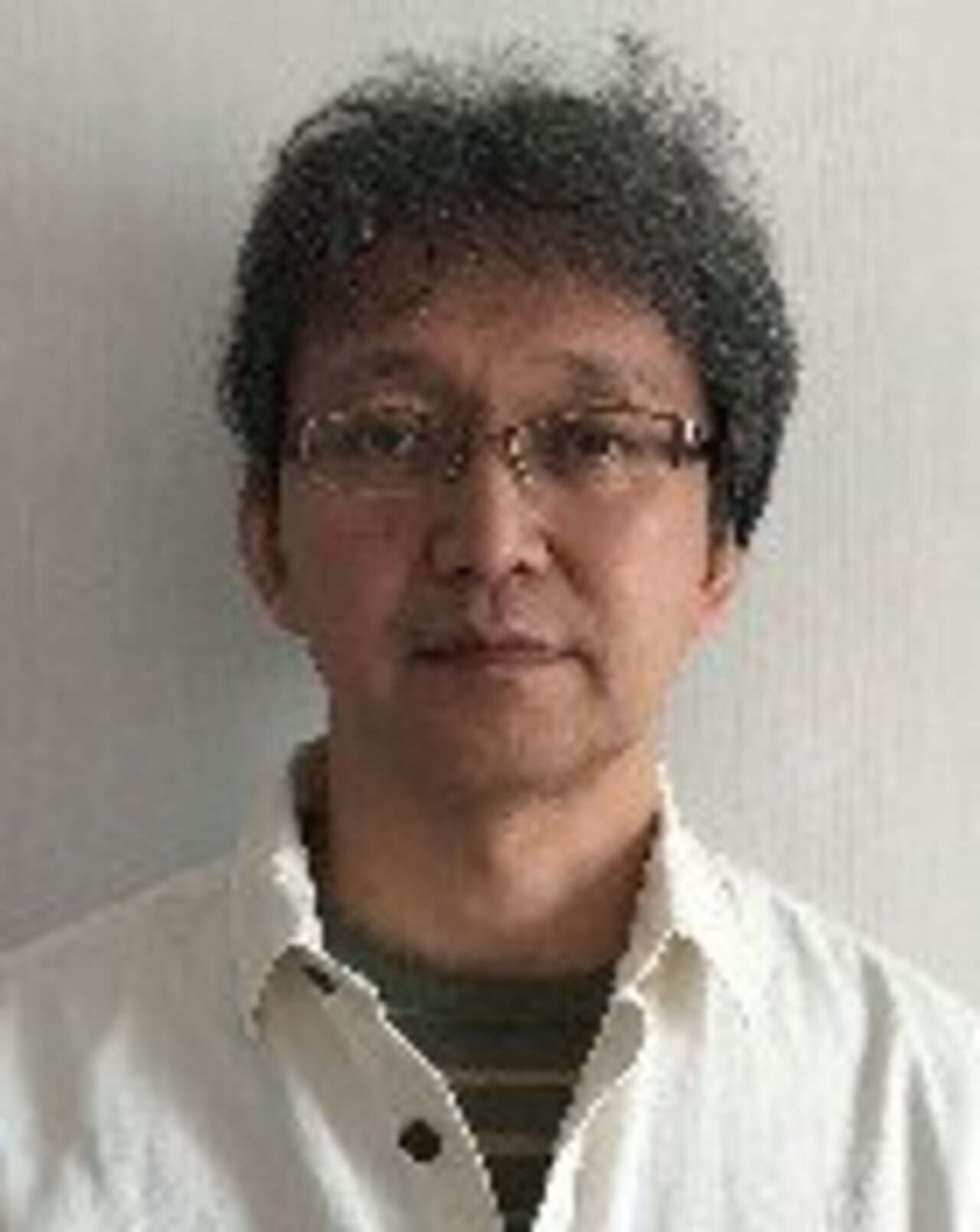和枝と廉は十七年前の一九九三年の元日、鎌倉の佐助に住む共通の友人である木南理子の紹介で知り合った。木南宅に招待されていた二人。東京・中野の会社の独身寮から来た廉は約束の時間に着いていたが、高森和枝は優に三十分遅刻して玄関に飛び込んで来た。
「ごめんなさ~い! でもシフォンケーキ作ってきたので許してください」
と屈託のない笑顔を振りまいてテーブルにケーキを置き、廉の斜め向かいの席に着いた。廉はその瞬間
「これはいい!」
と一も二もなく嬉しくなっていた。
余談になるが、和枝は三姉妹の末っ子で、廉はそこからさらに十年ほどさかのぼる大学時代、長女の高森真咲とはすでに知り合っていた。東京から来た男子四人と鎌倉に住む女子四人が、同じく木南宅に集まる「合コン」の席だった。
廉には、きょう会う和枝が、その合コンで特に印象に残った「あの真咲さん」の妹と分かっていたので、内心かなり期待はしていた。とはいえ、こんな場面でいつも心を曇らせる自分の脚の事情を素通りできるわけはなかった。期待が大きければ尚のことだった。廉は、和枝が脚のことに気付く瞬間が怖くてたまらなかった。
昼食をいただいた後、彼女のピアノ演奏を聴こうと、二階に上がることになった。廉が先に立って階段に足を掛けたとき、後ろから和枝が言った。
「あれ、足しびれちゃった?」
何の曇りもない天真爛漫な響きだった。
「うん、ちょっと左脚が悪くてね」
廉は自分でも意外なくらいすんなり答えていた。
「花火みたいな柄の、その靴下いいなぁ」。
足元で和枝の声が続く。
「そう? ありがと」
「ポロシャツの襟を立てているのと花火の靴下が、きょうのおしゃれポイントってわけ?」
とぼけた和枝の質問に、階段を上がりながら思わず笑ってしまった。ピアノに向かった和枝は、譜面立て越しに真っ直ぐ廉を見ていた。廉の不安に気付かないふりをするのではなく、その目は
「脚のことですか? 問題にしていません」
と語ってくれていた。