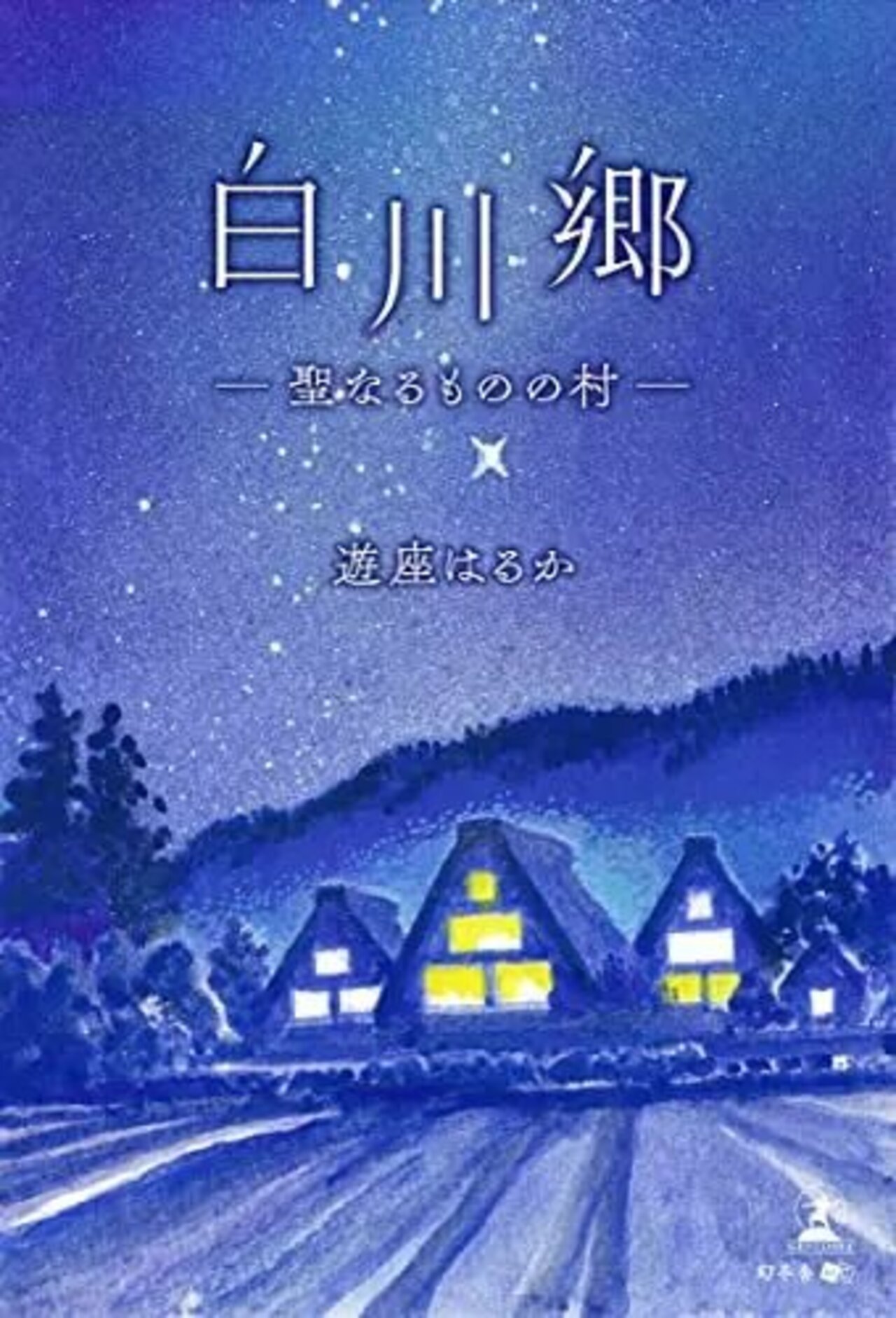篠原がまだいろいろ尋ねたい様子だったからか、奥さんは河田家の仏間でお茶をご馳走してくれた。そこに河田家の主人の河田裕也がやってきて、篠原のきょろきょろ仏間を見回しながらの質問に答えてくれた。
「こちらの仏壇は大きいですね。東京の僕の部屋くらいあるなあ。漆や金箔も豪華ですね。こんな仏壇、見たことないです」
「ここらは、浄土真宗やで。仏壇はどの家も大きいやさ」
「はあ。白川郷って、みなさん、大変なお金持ちだったんですね」
「そんなわけないさ。貧乏、貧乏の、下々の村や。オレは、口べらしで、親戚に出されたで。ほんの四十年くらい前のことや。オレはよ、東京で暮らしとってもこの村に帰りてえってばっかり思っとったな。そやけど、そこで高校まで出してもらえて、就職して、それでこの人と出会って結婚したんやさ。結婚して一年もたたんうちに、親父が倒れてな。そんで跡取りがおらんで、村に戻ってこいってことになったんや。この人も賛成してくれたでな、そんで戻ってこられた。
東京にいた時は、秋になるとな、ここの祭りの笛や太鼓の音がどうしても聞こえてくるんや。叔父さんに『祭りの笛が聞こえる』って言っても『そんなことない、聞こえない』って言われる。でも、毎年必ず、秋になると聞こえとったな。ここに戻ってこられて、毎年、本物の祭りの笛を聞くことが出来る。こんな日がオレにもくるなんて、思ってもみなんだなあ」
「はあ、そうですか。でも、江戸時代の末に、こんな大きくて銘木を使った立派な家が建てられたってことは、その頃は豊かだったということではないですか?」
「銘木いうてもな、ここは山の中や、木はどんだけでもあるで」
なかなか話が噛み合わなかったが、篠原は図々しく一時間近く居座って、あれこれ白川郷のことを聞き続けたのだった。