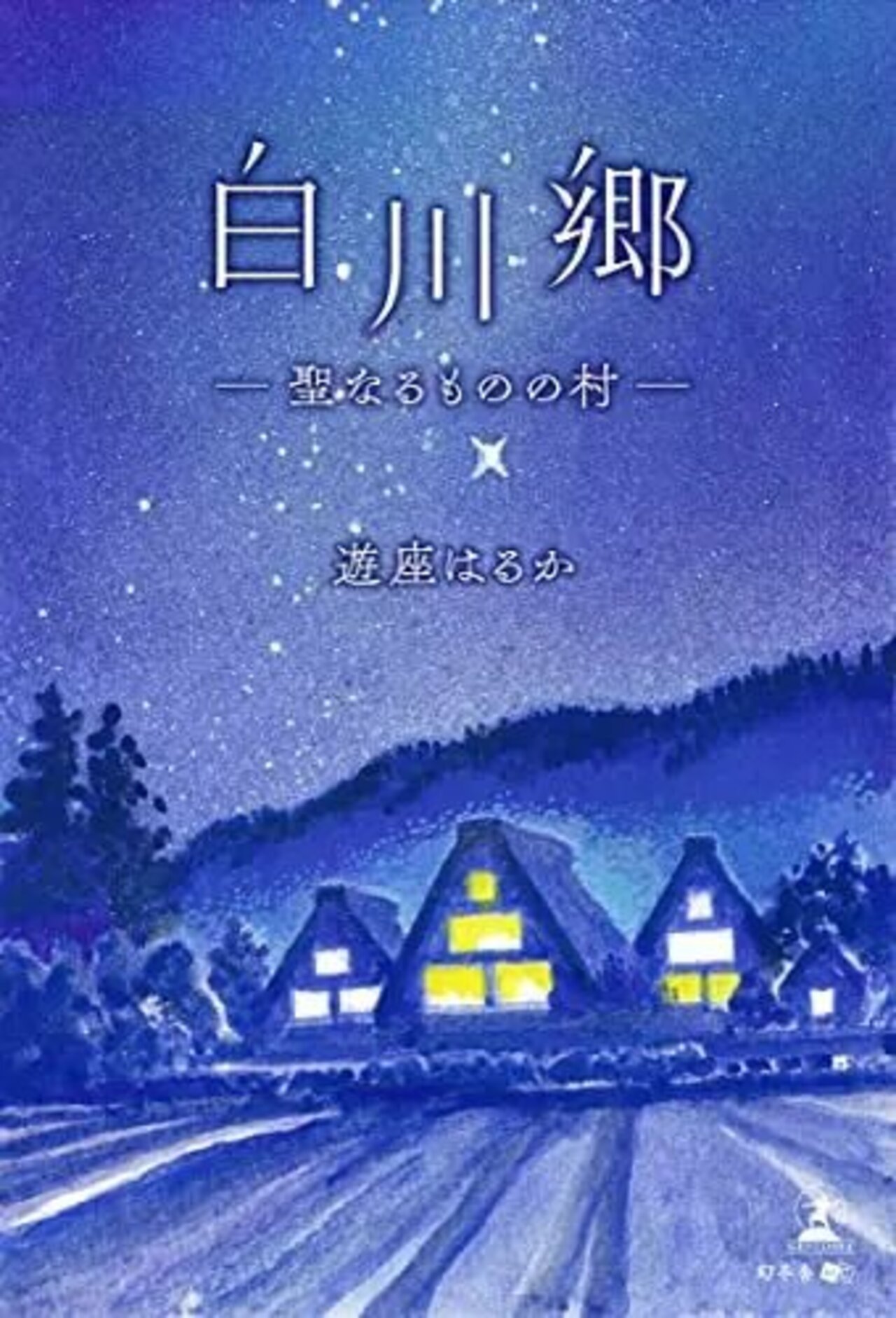1
七月の暑い盛りだった。毎朝新聞の記者、篠原准一は、長期取材をしている白川郷から飛騨支局のある高山市に戻ろうとしていた。たまたま車検の月で、車はすでに工場に預けてあったので、高山にはバスで戻ることにした。
バスは普通の乗り合いバスだが、客のほとんどが世界遺産の合掌集落を見に来る観光客の往復用なので、席は指定席になっていた。しかも夏休みが始まっていたから、ほぼ満席だった。出発間際に乗り込むと、篠原の席は窓際で、通路側には人がもう座っていた。大柄で姿勢のいいお爺さんだった。
「すみません、奥の席なんですけど」
「ああ、どうぞ。このバスの席は狭いですね」
機嫌よく席を立ち、篠原を奥に座らせてくれた。全然言葉になまりがないので、観光客だろう、と思った。すると、
「これから、日赤に、家内の見舞いに行きます」
話しかけてきた。
「高山の日赤ですか? 奥さんが、入院なさってるのですか?」
「ええ、ちょっとまずい状態なんですよ。肝臓癌でね。手遅れで手術も出来ない。先月入院して、それからほとんど毎日、こうしてバスで見舞いに通っています」
けっこう踏み込んだ内容まで話すのだった。篠原は返事のしようもなくて、黙ってうなずいていた。すると突然お爺さんは話題を変えた。
「わたし、いくつに見えますか?」
篠原はお爺さんを見つめた。お爺さんは大柄で姿勢もいいし、顔立ちもはっきりしていて、皺もない。五分刈りの髪も白というより灰色だった。
「七十才くらいですか?」
「いやいや、八十七才。白川郷に、六十二年間、暮らしましたよ。伊島といいます」
「ほんとですか?」
篠原は正直に驚いて言った。いったい村で何をしている人なのだろうか? それに、白川郷に六十二年間、暮らしました、というのは村の人たちがあまり口にしない言い方のように思えた。白川郷ではほとんどみんな代々暮らしている人ばかりだから、自身だけの居住年数を口にする人はいなかったのだ。それでいよいよ、このお爺さんは村のどういう人なのかと篠原は思った。すると篠原の疑問は、すぐにお爺さんにわかったようだった。