「ニューヨーク・シティ」からバスでニューハンプシャー州コンコードに着いた。ニューハンプシャー州は、ニューイングランド地方の一つで、アメリカ西部開拓のはるか前の時代、北東部地域がまだイギリスの植民地だったときに、イギリスとの訣別の意思を最初に表明した十三植民地の一つとして知られる。九十二パーセントが白人、ヒスパニック系が三パーセント、アジア系二パーセント、黒人一パーセントの州だ。
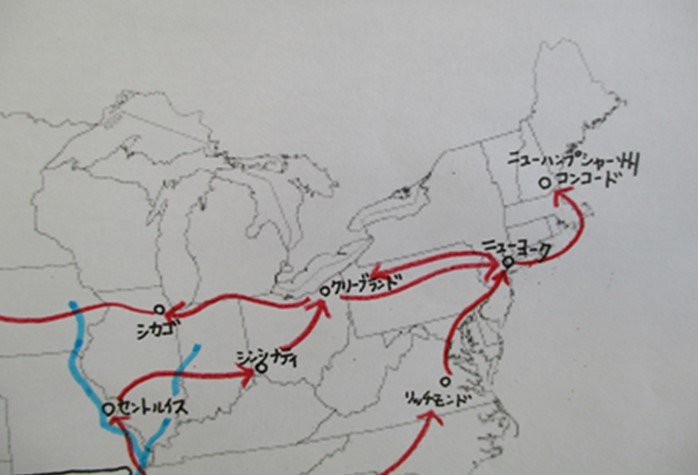
「アメリカ人としてのアイデンティティがしっかりと存在している州だ。」
ということを何人もの現地の人から聞いていた。コンコードはニューハンプシャー州の州都だが、広々とした荒野の中にポツンとある街といった印象だ。
バスから降りると、今度の学校の校長先生が迎えに来ていた。中年白髪の、厚い丸レンズの眼鏡をかけた女性だった。
彼女は、
「ミズ・マックアルーン」
と言った。この家では、
「ビヴァリーと呼んで。」
と言った。とても優しそうな雰囲気を持ち、長旅の労をねぎらってくれた。一時間ほど車の中でどんな話をしたのか記憶にないほど疲れていたように思う。ただよく質問され、コンコードの街のことや、これから向かうペナコックのことを話されていたことだけはぼんやりと覚えている。
着いた先は彼女の自宅だった。もうすでに夜の十時を過ぎ、辺りはもう真っ暗闇だった。家の外観や庭はどんな感じだったかわからないまま、リビングを案内された。そこに、夫のトムと二人の留学生がいた。簡単な自己紹介をして、部屋に荷物を置き、そのままベッドに寝かせてもらった。初めて会う人の、初めての家、そして個室のベッド。なぜかよく眠れた。夢など見ず、ノンレム睡眠が何時間もずっと続いているような爆睡だった。
翌朝、早速学校に向かった。そこは「ペナコック・ワシントン・ホワイトスクール」という小学校だった。ティーチャーズルームに案内され、一通り自己紹介をし、握手を交わして、校内を歩いた。言うまでもなく、注目の的だった。日本人が来たというよりは、
「アジア人だ。」
という印象を持たれたにちがいない。子どもたちの視線を四方八方から感じながら、
「私は日本人である。」
ということをどう教えようか考えていた。子どもたちは、だいたい日本がどこにあるのかさえ知らないだろう。この州のアジア人はたったの「二パーセント」しかいないのだ。昨日バスから降りて今日ここに来るまでに当然のことながらアジア人を見かけたことはなかった。
この学校の校舎も例外に漏れずレンガ造りの平屋の建物だった。

校長室で、今後の予定や時間割の概略を決め、ミズ・マックアルーンは、
「必要に応じて学年ごとに先生たちと話し合って授業の中で日本のことをたくさん教えて欲しい。」
と言ってくれた。まずは、授業の準備のための時間を一週間もらった。一人ティーチャーズルームで準備をしていると、来る先生、来る先生から声をかけられたり、こちらからもコピー機の使い方や教材の場所を聞いたりしながら、少しずつ学校の先生たちと話ができるようになり、そこの雰囲気になじんでいくことができた。















