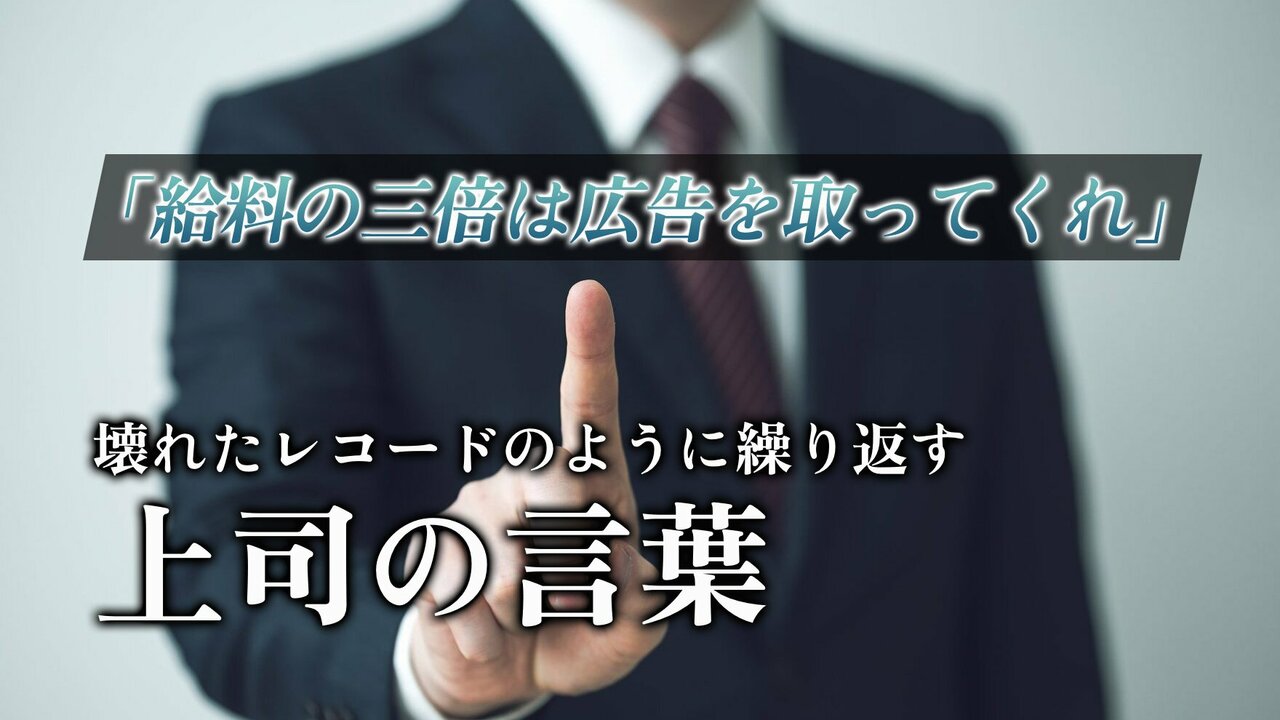第一章 晴美と精神障がい者
4
自転車を漕いでいると、心地良い風が頬に触れる。
晴美が就職して半年が経つ。急に会社の締めつけがきつくなってきた。中川営業部長から、「そろそろ、給料の三倍は広告を取ってくれ」と言われた。給料は十七万だから五十一万は取らないといけない。五十一万、五十一万、五十一万と頭の中で壊れたレコードのように繰り返してくる。断然、晴美の体に余計な力が加わってくる。が、空回りばかりだ。
パーマ屋の広告を頂いたことがあった。白黒の七万円の広告だ。女性店長はその効果を調べた。
晴美はカットをしてもらった。「はい、一人」と、店長はノートに書いた。二週間経って、晴美はその店に行った。顧客は晴美一人だったそうだ。彼女は「あなた、一人」と厳しい口調で口を尖らせて言った。その後、そのパーマ屋からは相手にしてもらえなくなった。
晴美は初めて思った。広告効果って果たしてあるのだろうか――。
中川営業部長に訊いてみた。
「それは難しい問題だね。まあ、永遠のテーマといっていいね」
広告は顧客へのメッセージであり、それはどの程度顧客の心に染み込んでいくかは全く分からないのだ。が、口コミだけで店が繁昌していくのにも限りがある。それなりに広告を出さないと、顧客から忘れられる可能性がある。いってみれば、その弱みにつけ込んでいくのが、広告の営業マンなのだ。
晴美は自分の仕事の限界に気がついた。それががんじがらめに体を締めつけてくる。そして、五万円ぐらいなら取れないことはないが、給料の三倍を取ることの難しさを思い知るのだった。中川営業部長は「今月も駄目か。一体、いつになったら三倍取れるのか」と月ごとにますます口調がきつくなってくる。
晴美は徐々に体がしんどくなってきた。自転車を漕ぐ足の力も弱くなる。それでも晴美は歯をくいしばって漕ぐ。もう師走だ。街にはジングルベルの軽やかなメロディーが流れている。クリスマスムード一色だ。しかし、晴美の心はその雰囲気とは正反対に虚ろなのだ。
「あぁ、今日は疲れた――」
帰宅した晴美は自室に直行し、布団を出してそのまま倒れてしまった。
「あれ、帰ってきたのかい」
母親は晴美の足音に気がつき、そう声を掛けた。もちろん、晴美は返事ができなかった。その微妙な変化を母親は見落とさなかった。娘の部屋へ行った。そして見た。大の字になって倒れている娘の姿を――。
「どうしたの、晴ちゃん!」
母親は晴美の体に触れ、つい大声になってしまった。
晴美は、
「疲れたの。今日は眠らせて――」
「体は大丈夫なの。平気なの」
母親は晴美の体をゆっくりと摩った。
「寝たら、元気になるわ」
晴美も母親に心配をかけないように言った。