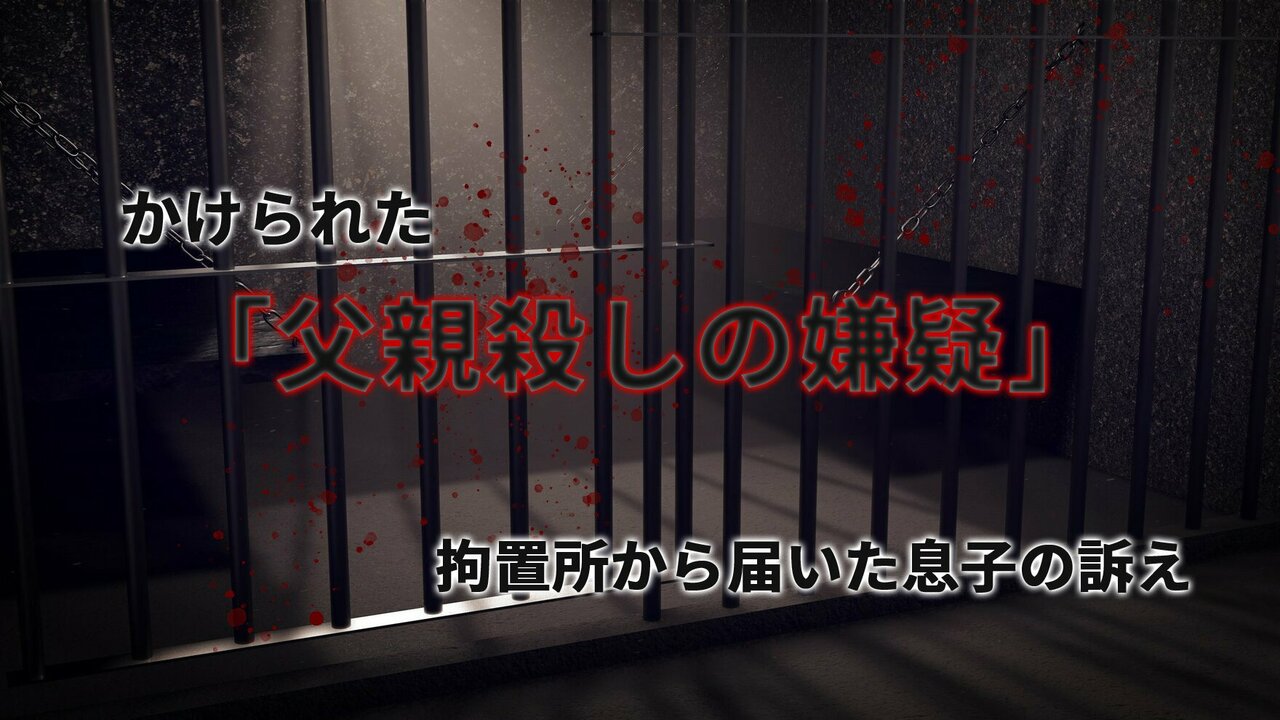Ⅰ レッドの章
メモワール序章
あれから余りにも時が経ち、きっと物事が現実よりも何倍も美化されて甦ってくるのだと人は笑うだろう。だがあれが僕の単なる思い込み、或いは身勝手な想像だけではない証拠に、それを記そうとすると胸の疼きばかりではなく、前歯の痛みも告白せねばならなくなる。
僕の人生の最も美しくあるべき思い出が、何とも散文的なものに成り下がってしまったのは、僕の不徳の致すところで誰のせいでもない。失った歯はそれ以降ずっと僕の頭痛の種となり、今ではまともな歯を持った自分が想像さえ出来ないくらいだ。
それにもかかわらずそれは紛れもなく僕の青春の時間を占領し、人を思うことの切なさ、美しさと残酷さを初めて僕に教え、その後の僕の人生を方向付ける大きな転換点となったことは掛け値なしの真実だった。さもなければ頭に霜を置き、背骨も前かがみになってきた今でも、あのひとのことを思うとこんなにも心臓が高鳴り、胸がやるせなくなるはずがない。
実を言うと僕がまだ現役時代のある時期に偶然僕は彼女の消息を知った。結局彼女は全国的な名声は手に入れなかったが、一時期名乗っていた芸名を捨てて本名に戻っていた。僕に彼女の住所を教えたのは中学の同窓生で、彼によると彼女は一度結婚したが別れて、そのころは神戸でジャズ喫茶をやっているという話だった。今でもきれいで魅力的だとその男は言った。かれこれ三十年も前の話だ。
正直に告白すると僕もマルグリット・デュラスの若き日の中国人の恋人のように、彼女に電話を掛けて「あなたを愛していた、そしてこれからもずっと愛し続けます」と告白しようかと迷わなかったと言えば嘘になる。
だが結局僕はそうしなかった。デュラスの恋人と違って、僕は彼女が僕のことを覚えてくれている自信がなかった。当然だ、愛を告白したことすらなかったのだから。