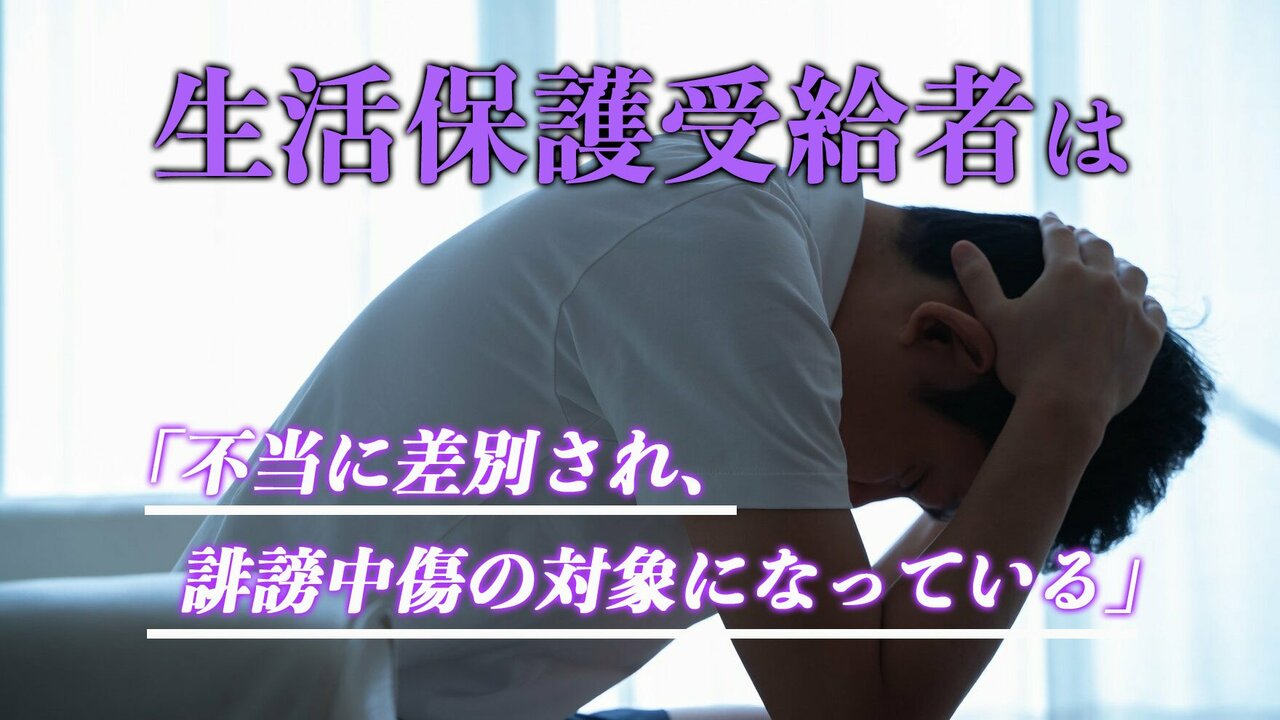積雪
悠希が死亡したと知らされた日の夜、真田は莉子に電話をかけた。番号は警察署で交換していたが、そのときは莉子が動揺と悲しみの涙に暮れていたため、十分な会話ができずにいた。
そのときに唯一わかったのは、過去に莉子が一度だけ悠希の家を訪れており、それは引っ越し祝いと称して少人数で行われた飲み会のときで、その際に莉子が道順を間違えないようにと住所を登録していたという事実だった。それを聞いたとき、悠希の身体が誰にも見つからず朽ち果てていく様子を、真田は一瞬間だけ妄想した。
遺書を残さなかった悠希の最期に一番近くにいた人物から、何としてでも話を聞かなければならない。その一心で真田は、莉子との対話を再び試みた。そんな彼の意図を察したのか、莉子は2コールで着信に答え、先ほど会った時とは全く異なる冷静なトーンで通話に応じた。
「会社が急に倒産になって、失業保険も受けられないかもしれないから、生活保護について知っていることを教えて欲しいって、まずメッセージが送られてきました」
莉子から告げられた、我が子の身に起こっていた惨劇と、それを知らされずにいた自分に、真田は大きなショックを受けた。脳みそがぐらつき、眩暈が起きるのがわかった。
悠希の勤め先は小さなベンチャー企業で以前から風前の灯の状態であり、ついに先月末に全社員に一斉メールで倒産通告がなされ、社長は現在も行方をくらましているとのことだった。
悠希には、一人暮らしをしている親しい友達が少なく、結婚をしている者も多かった。その中で現状把握と相談相手として選ばれたのが莉子だった。彼女は母子家庭で育ち、兄妹も多く経済的に困窮しており、学生時代は家族で公的な支援を受けていたという。
「私の家が保護を受けていたことは、友達だと悠希ちゃんにだけしか話していません。だからたぶん彼女も、私に連絡したのだと思います」
数年ぶりに悠希と電話をした莉子はまず、両親に近況を報告することを促した。しかし、彼らが三年前に離婚したことと、母親は再婚し父親は年金のみを頼って一人で暮らしていることを聞くと、事態の複雑さと悠希の感情を察して、両親に関してはそれ以上の言及をしなかったという。
「それで私からすぐに電話をして、とりあえず区役所に相談するように伝えました。でも、もう電話の段階で断られてしまったそうで……」
どうやら悠希は、最低限の情報はインターネットで調べていたようだった。それでどこに連絡すべきか、何を行うべきかわかっていたが、区役所の職員に電話口で冷たくあしらわれてしまっていた。