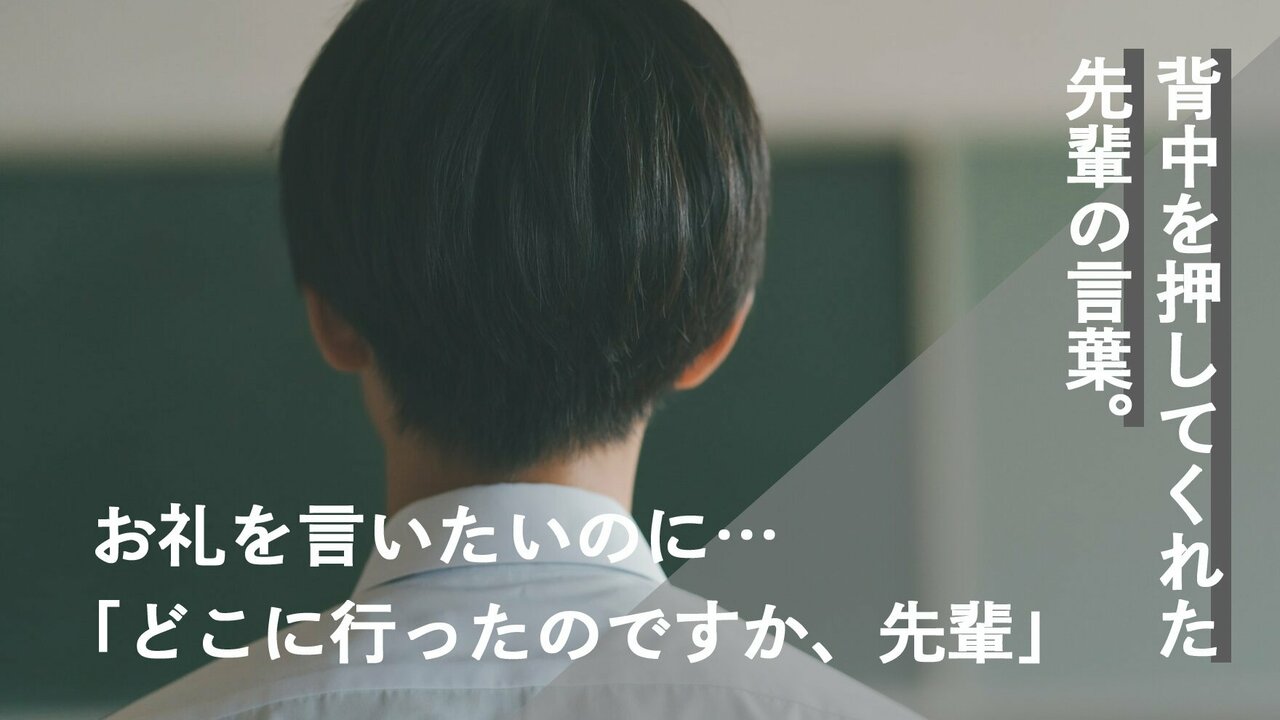第一部 第一章「二つの星の恋」 ゆきと
6
夏は別れを惜しみながら、何度も振り返る。沖縄の夏が長いのは、きっと寂しがり屋の夏のせいだ。淑やかな秋は、すぐそこまで来ていた。
行方不明となった先輩の捜索は、一か月ほどこの町をざわつかせた。ある者は、「死に場所を求めて、この町を出て行ったんじゃないか」、「大学受験で溜まっていたストレスが爆発して気でも狂って失踪したんじゃないのか」などの根拠のないことを面白半分で言い回っていた。
僕は、あの日の和人先輩の背中が、何度もフラッシュバックして、あのときの自分を殴りたい衝動に襲われる。「何かできたはずだろ!」と、心が叫んでいる──。それでも、秋には高校サッカー県大会があり、僕たちのチームは、それに向けて練習をするしかなかった。
和人先輩の両親は、「和人は、後輩たちが活躍してくれることを、いつも願っていました」と、練習を続けてほしい旨を学校側にお願いしていた。和人先輩の両親は、自身のクリニックを一か月の間、休業して先輩の捜索をしていた。だけれど、このまま休業を続けるわけにもいかず、営業を再開した。
「じっくりと仲間を見るんだ」和人先輩に言われた言葉が僕の背中を押す。
僕は、じっくりと仲間を見る。すると、今まで知らなかったことが少しずつ見えてきた。副キャプテンの吉澤は、ピリピリしていた僕をかばって、後輩の不満のはけ口になってくれていたこと。ボランチの池村は、実は映像研究部と掛け持ちでサッカーをしていたこと。将来は、テレビに携わる職業を目指しているそうだ。
その他にも、みんなが輝いている瞬間はたくさんあって、そう感じると、和人先輩が言ったように、このチームでサッカーができていることは、「奇跡」なんだと心の底から思えた。そして、小林にも会いに行った。
小林は病院近くの公園でボールを蹴っていた。僕は、コーラを小林に渡した。試合終わりに、よくそれを飲んでいたことを知っていたから。
「ごめんな、お前のこと何も知らずに、ひどいこと言っていたこと。本当にごめん」僕は、ベンチに座る小林の正面に立ち、頭を下げた。小林はうろたえながら、
「俺の方こそ、ごめん。お前のこと、『うぜえ』なんて言って。本当はありがたかったんだ。あのときの俺は、母ちゃんが入院していることを言い訳にして、『しょうがないだろ』って自分で自分をあきらめていた。本当は、お前が言っていたように、テキトーだったんだよ。自分に対しても──。だから、お前に喝を入れてもらって感謝しているんだ。ありがとう」
小林もベンチから立って、お互いに顔を見合わせた。なんか全身に鳥肌が立つような、恥ずかしい気持ちになって、笑った。小林も同じく笑った。
和人先輩がいたら、すぐにでもお礼に行きたかった。だけど……どこに行ったのですか?
──先輩。