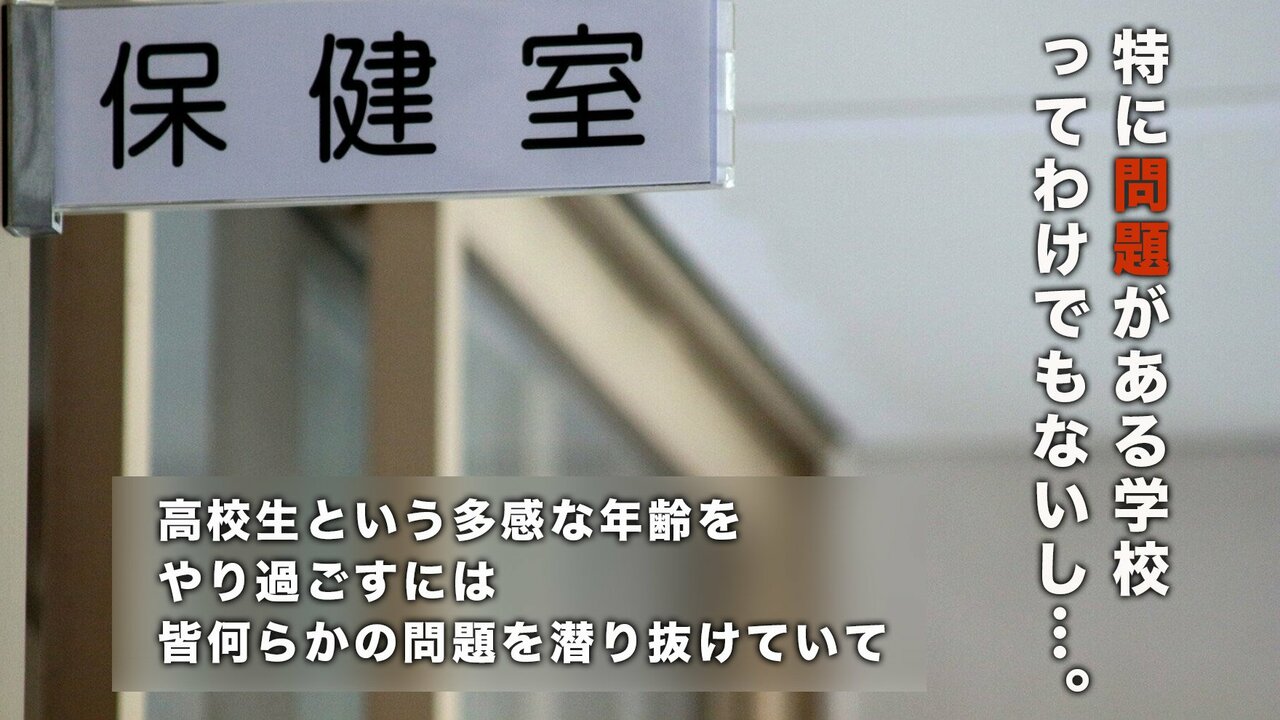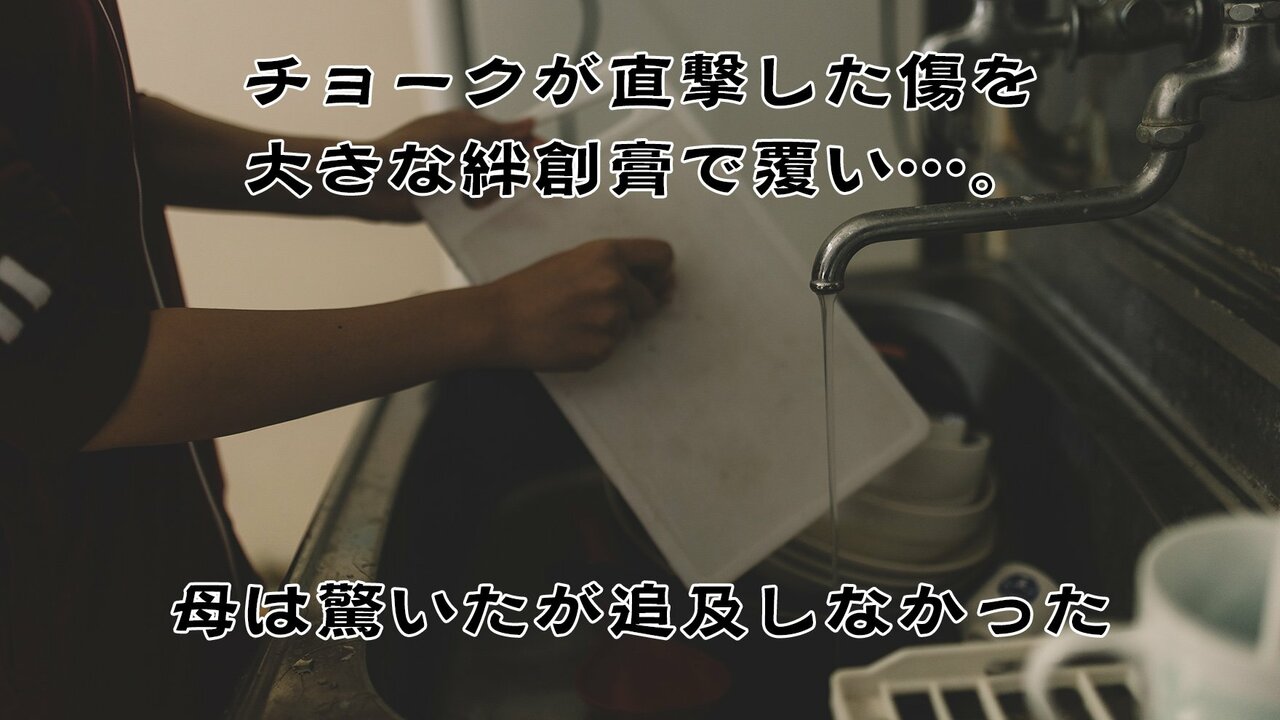成長という木
純太はそのままトイレに駆け込んだ。お腹の調子はチョークが額に当たったショックのせいか、また痛みがなくなっていた。トイレの個室にこもってパンツを下ろした。白いパンツに黄色いシミが付いていた。緊張から緩んだ肛門から下痢便が少し出てしまったようだ。
(やばい)という思いが体中に駆け巡った。ズボンを脱いでパンツを手にして臭いを嗅いだ。下痢便の酸っぱい臭いが鼻に来た。汚れたまま履く気が起こらず、下着を着けずズボンをじかに履いた。ポリエステルと綿でできている生地は思ったよりごわごわしていなかった。それでも無防備な下半身なのが気になった。こんな状態を知られたら格好の餌食だ。
手洗い場でパンツをごしごし洗った。洗いながら、何故今日に限って白いブリーフなんか履いてきたのかと後悔した。アキラたちに所構わずズボンを引き下げられるようになって、履くパンツには気を付けていた。一度白いブリーフの時
「こいつ、きもいな。じじいのパンツ履いてら」
と言われて以来、しゃれた色のボクサー型にしている。トランクスだともろにズボンと一緒になって脱げてしまうからだ。小さな事だが大事な事だ。二、三回ゆすいだ後で臭いを嗅いだが、臭いはもうしなかった。ただ黄色いシミが少し広がったようで、色はしっかり残っていた。今日はもうトイレには行けない。トイレのいざこざは避けなければならない。
水垢で濁った鏡に顔を近づけた。額の傷は大した事はないようだ。濡れた指先でこすったら、白いチョークの粉も赤い傷跡も消えてしまった。それでも純太はしっかり絞ったパンツを持って医務室に行った。白い戸棚、白いベッド。白い色で覆いつくされた医務室にはやはり白衣を着た保健の女性教師が机に向かっていた。
「失礼します」
と言って部屋に入ると教師は回転椅子をくるりと回して純太を見た。
「どうしたの?」
白衣のポケットに「佐伯」の名札がかかっていた。佐伯の名前の上に保健・カウンセラーの文字があった。少し茶色に染まった髪はショートで、赤い縁の眼鏡が似合っていた。赤い縁の眼鏡のせいか人の良さそうな雰囲気があった。純太は少し安心した。
「はあ、ちょっと」
だが言葉は警戒からか言い渋り、それ以上何も言わなかった。口が重く扱いにくい年ごろの生徒たちと上手く係わり合うには、あまり深追いしない。そう理解しているのか、佐伯は黙って傷口を探っていた。純太が指し示したあたりに、やっと場所を見つけたようだ。
消毒をしてチューブから絞り出した軟膏を指先でチュッチュと塗りつけた。
「バンソウコウ、貼る?」
と少しからかうように言った。純太も照れ笑いして
「良いです」
と言ったからそれ以上の手当てはないといった感じでまた机に向かった。