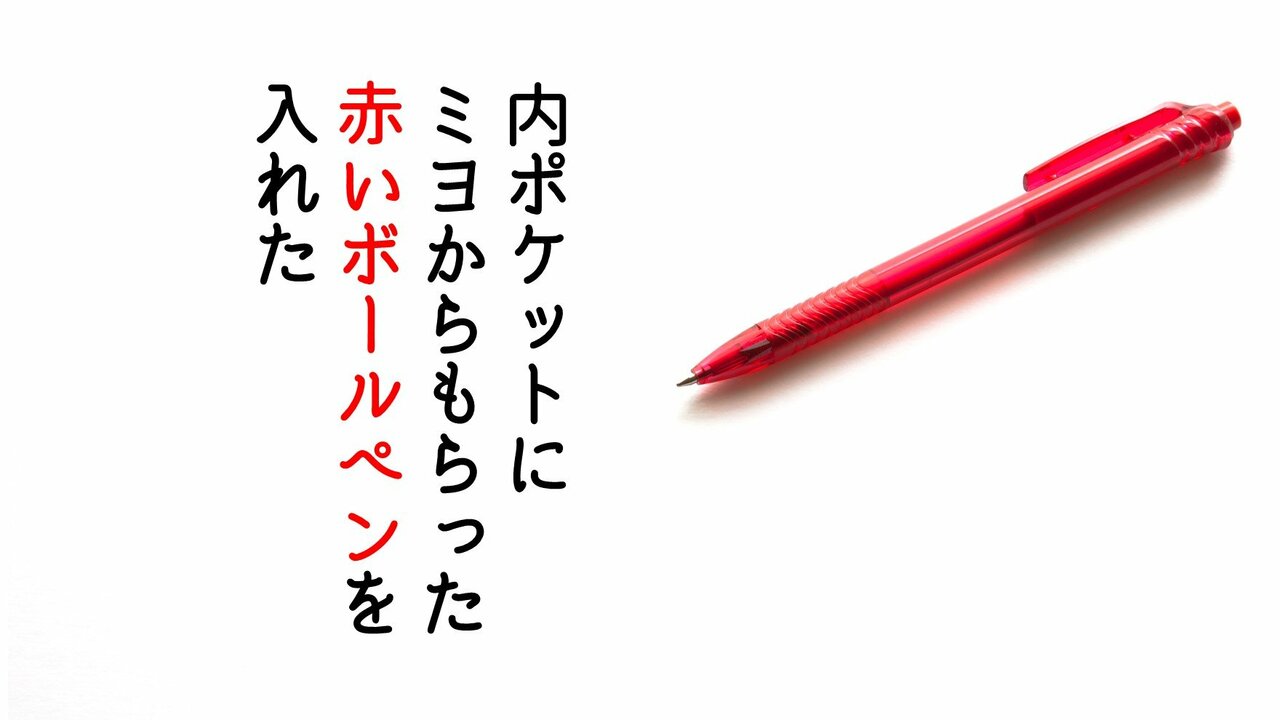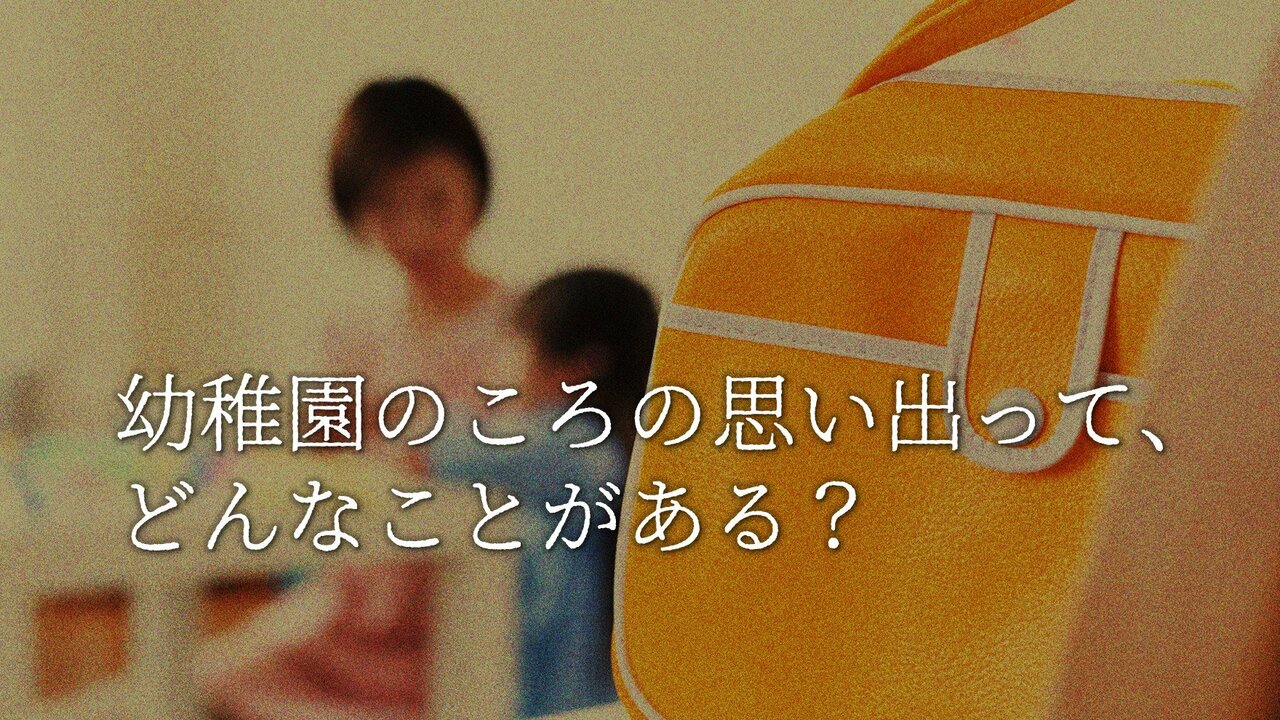第三章 運命の人
新しい年を迎えて一週間が過ぎようとしていた。冬期講習中に受けた本番前の最後の模試も、総合偏差値が六十三という自己最高の結果を残し、達也は順調すぎるほど成績を上げていた。
この日は日曜日で学校も塾もなく、達也は昼過ぎに信州中央病院へ向かった。ミヨに一日だけ外出の許可がでたので二人で初詣に行くことにしたのだ。
病院に到着すると、エントランス付近でしゃがみこんでいるミヨを見つけた。マスクは着けていないが、時折咳きこんでいるようだ。足元に近寄ってきた黒猫の頭を優しく撫でている。達也はミヨの元へ近寄ろうとするが足が動かない。
赤い光が、ミヨの体だけではなく、達也の視界すべてに広がっていく。赤く揺らめく光の中、黒猫が異様な鳴き声を発した。すると辺りを包む光は深紅に変化していく。
突然、達也は違和感を覚えた。自分の意思に反して勝手に、そしてゆっくりと左腕がミヨの方へ差し伸べられていく。信じられぬ光景。
呼吸が乱れる。自らの腕が向けるその先で、ミヨが立ちあがり目を少し細め、達也だけを見つめている。
二人だけの赤い空間。目の前のミヨが右手を差し伸べてきた。深みを増していく赤い色。ミヨがゆっくりと口をすぼめているのがわかる。唇の動きを一瞬でも見逃さないように、達也は全神経を集中させる。
ミヨの唇が真一文字に結ばれた。達也の額から汗が吹きでてくる。瞬(まばた)き一つせず達也を見つめてくるミヨ。今度は微かに口を開いている。
(ウ、……ン、……メ、……イ? どういうことだ?)
達也は唇の動きからなんとか言葉を読み取った。真意までは読み取れぬままの達也に、ミヨは何も言わず指先だけで手招きをしている。
思わずミヨから視線をそらそうとした時、足元に何かがぶつかった。先ほどの黒猫だ。達也の足元でピクリとも動かず達也を凝視している。一瞬の焦りの直後、再び発せられた異様な鳴き声に達也は慄(おのの)き、目をつぶってしまう。
「達也くん?」
ゆっくりと目を開き声のする方へ振り向くと、ミヨが立っていた。
「どうしたの? そんなに汗かいて。大丈夫?」
落ち着きを取り戻せぬ達也に、ミヨが普段と変わらぬ口調で言った。
「さあ、行きましょうか」
達也は二、三度小さくうなずいた。ミヨにあまり負担をかけないように、二人は病院近くのバス停からバスに乗り、安曇野神社へと向かった。
自然豊かな深緑の地に鎮座する安曇野神社。松本駅と梓(あずさ)橋駅の間に位置する人気の神社だ。簡素な佇まいは、参拝する人々の心をすがすがしくさせてくれる。
すでに初詣客で賑わっているようだ。鳥居をくぐると、露店からの煙とお焚(た)きあげの煙が混じり、境内を包んでいた。
「すごい人だな」
達也たちのずっと先の方の拝殿で真剣に祈る人々の姿が見える。拝殿へと続く参道には多くの露店が立ち並んでいた。
「先輩、並びながら何か食べませんか?」
ミヨは小さくうなずいている。達也は店をひと通り眺める。どれもおいしそうなものばかりで迷ってしまう。
「よし。僕、適当に買ってきますから。先輩並んでいてください」
チョコバナナを買って戻ると、達也は早速一口かじり、口の中に広がる甘い至福を味わった。ミヨは口をつけることなく、棒に刺さったチョコバナナをじっと見つめている。残りを食べ終えた達也が不思議に思って声をかけようとすると、ミヨは一度ぺロリとチョコの部分だけ舐め、口の中で舌を転がしはじめた。
「先輩、どうかしました?」
「達也くん、ちょっとその棒貸して」
ミヨは達也の棒を手に取ると、今度はチョコだけを薄く削り、その味を楽しんでいる。時折、首をかしげたり、首を横に振ったりしながらミヨはチョコだけを食べた。
「先輩、おいしいですか?」
ミヨは返事もせずチョコに夢中になっている。棒をクルクルと回しチョコが残っていないことがわかると、残ったバナナを達也の口元に運んだ。
「バナナ、苦手だったんですか? すみません」
「そんなことないわよ。チョコだけで満足なの。でも、甘すぎね」
ミヨはポケットから取り出したビターチョコを一口サイズに割り、その苦味を味わいはじめた。
「わ、わからない」
達也が苦笑している間にも列は進み、二人は拝殿までやってきた。賽銭(さいせん)をあげ、拍手(かしわで)を打つ。
(みそぎ学園高校合格しますように。それから)
達也は、隣で手を合わせるミヨをちらりと横目で見た。