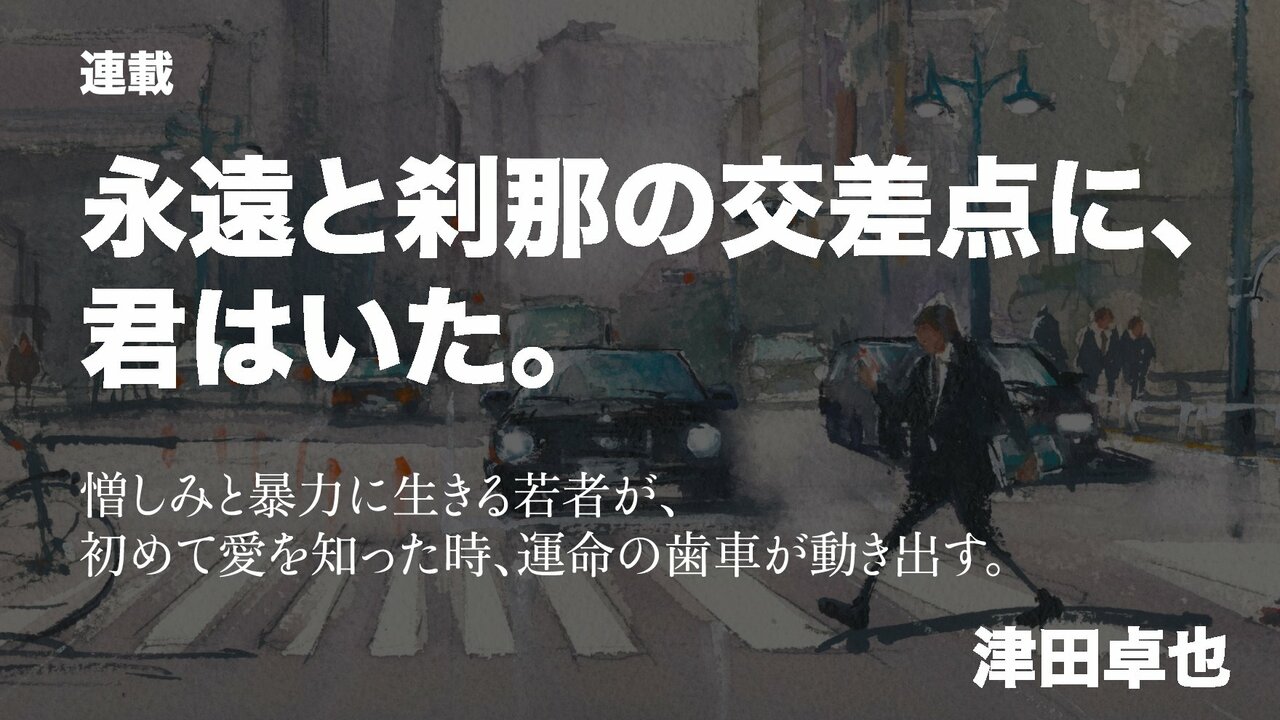第一章
1
「おまえは子供らしくない」
父はよくそう言った。無口で無表情な博昭を持て余しているようだった。
保育園に入ってからは頻繁に殴られた。自分に似ているところが気に入らない、と父が言ったのを博昭は記憶している。
父に殴られ、蹴られ、踏みつけられても博昭は泣かなかった。意地でも泣いてやるものかと思った。
その態度が気に入らないのか、父の暴力は年々ひどくなった。母も途中からあきらめたかのように、博昭が殴られるのをただぼんやりと見ていた。
母は時々博昭を街に連れ出した。そういうときの母はいつも上機嫌だった。母は父とは別の男と会っていた。しかも相手がしょっちゅう変わった。
記憶……。小学校に入ったばかりの頃、母と小旅行に行った。小太りの男も一緒だった。夜に母の喘ぎ声で目が覚めた。小太りの男が母に覆い被さっていた。まんじりともせず、博昭はその行為を見ていた。夜が明けるまで博昭は寝なかった。
だらしなく眠る母と男を見ながら、博昭は自分自身に誓った。強くなってやる。誰よりも強くなってやる。
父と母がいなくなったのは、博昭が小学五年生になった春のことだった。何人もの男たちが部屋に入ってきて、テレビを観ていた父と母を連れ出した。
二人とも無抵抗だった。覚悟をしていたかのようでもあったし、ほっとしたようでもあった。ひとりの男が博昭の肩に手を置いてこう言った。
「もう大丈夫だからね。安心しなさい」
男は市の職員だった。博昭は施設に入った。親から虐待を受けている子供たちを保護する施設だった。
施設には博昭のような子供たちがたくさんいた。そこははじめて安らぎを感じる場所だった。物心ついてから常に暴力と性の世界で過ごしてきた博昭にとって、施設は楽園だった。
たまに母のことを思い出した。寂しくはなかった。ただ、他の子供たちの母親が施設を訪ねてきたときなどは、ほんの少し心の奥がうずいた。その感情が何を意味するのかはわからなかった。
博昭は安心して眠れるようになった。硬いベッドでうずくまって眠った。
母は博昭が十四歳の時に首を吊って死んだ。施設の職員から母の死を告げられたときも博昭は泣かなかった。
悲しみと憎しみの感情をどう処理していいのかわからず、ただぼんやりと過ごした。その状態がひと夏続いた。
夏休みも終わりに近づいた頃、博昭は心の中から両親の思い出を消した。するとまた安心して眠れるようになった。それ以来、両親のことを思い出すことはなかった。
「真っ正面から愛を語ろうやないか」
また父が言った。博昭は目を瞑り、深く呼吸をした。記憶を呼び起こす。そして……。両親の記憶を細胞の隅々にまで染み渡らせる。
額の傷に指を当てた。父につけられた傷。鼻を触った。ひん曲がった鼻。息を吐き、目を開けた。部屋の空気が重くなった。
時間が止まる。大丈夫。きちんと話せる。博昭は言った。
「語りましょう。父さん」