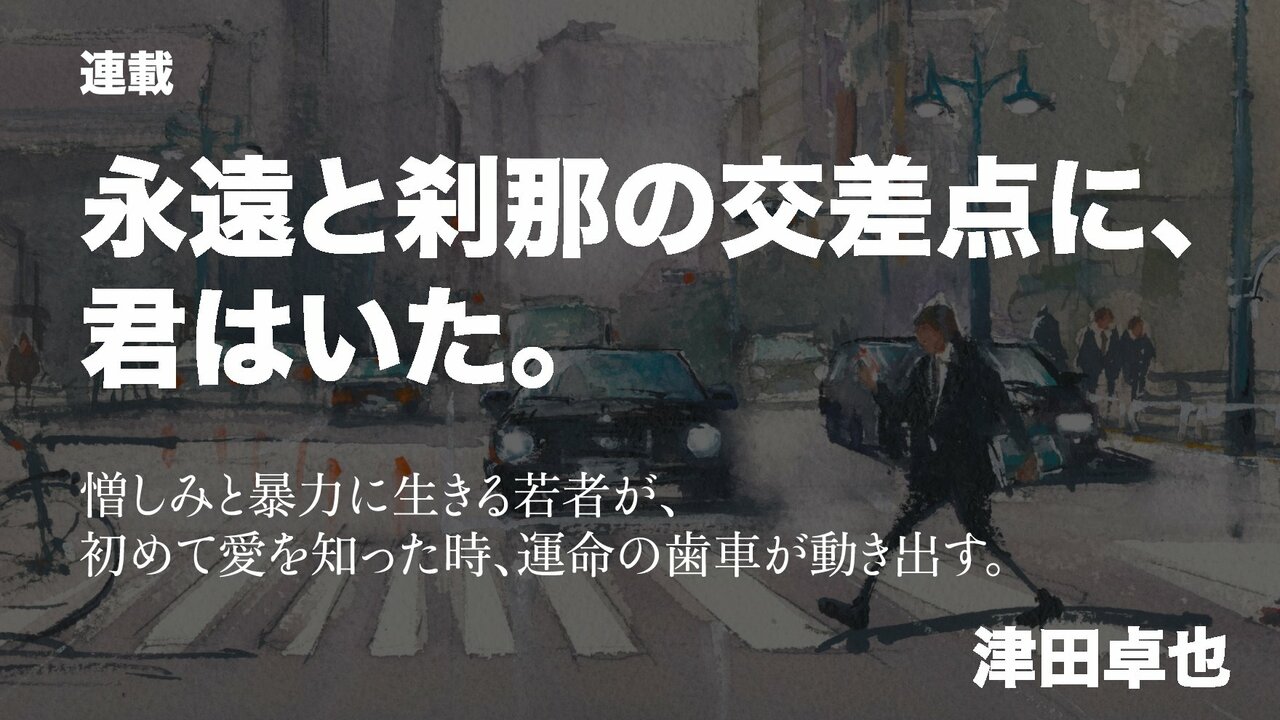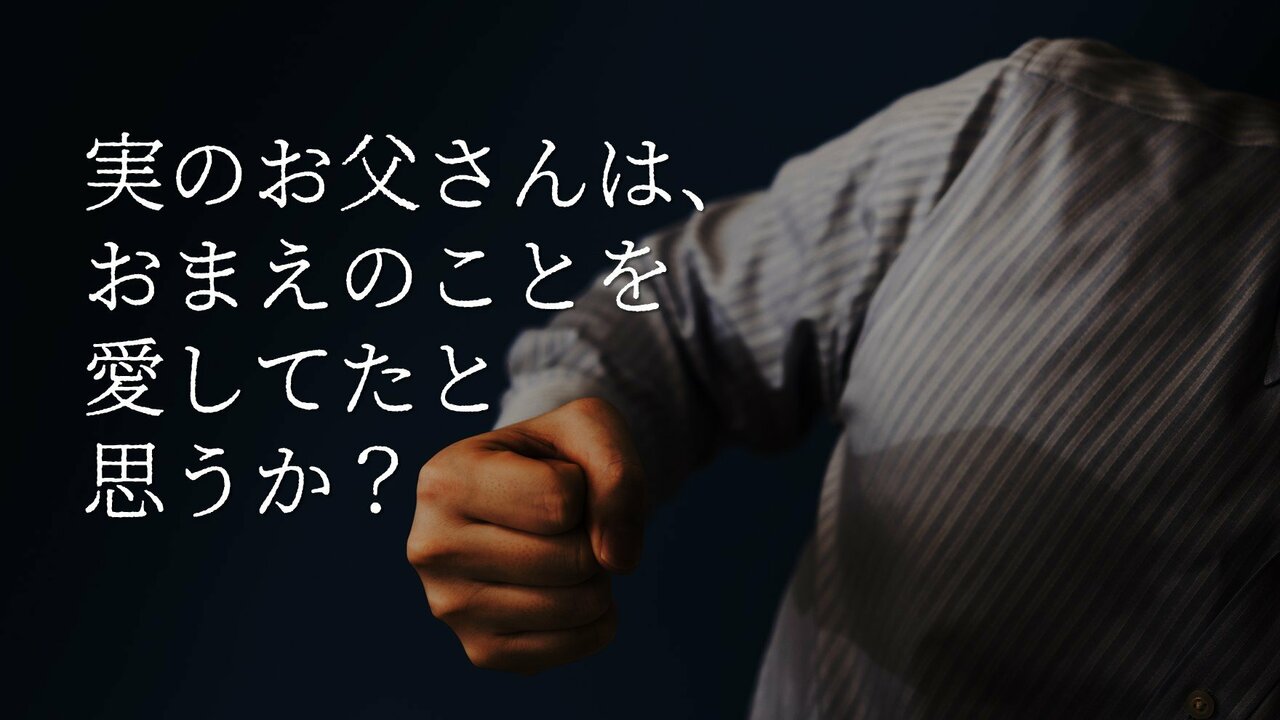第一章
1
父は黙っていた。だが、色素の薄い瞳はしっかりと博昭を捉えていた。
「そんな講釈を聞きたいんやない」と父が言った。その声には抑揚というものがなかった。博昭はどう答えればよいのかわからず、グラスの水をひと口飲んだ。
「質問の仕方がわるかったか?」父は髪を撫でた。肩まで届く長い髪。癖のある髪は、目鼻立ちのはっきりした容貌と相まって、父をますます国籍不明にしていた。
「じゃあ、こう聞くわ。おまえのお父さんや。実のお父さんは、おまえのことを愛してたと思うか?」
博昭は養父を、風間を見た。目が合った。風間の瞳は風のない海のように静かだった。
博昭は大阪の茨木市で生まれた。大阪のベッドタウンであるその街は、高度成長期に栄え、バブル崩壊とともに寂れていった。昭和の末期に建てられた家ばかりの街は、古きよき時代でもなく、新しい可能性に満ちた街でもない、B級映画のセットのような街だった。
実の父と母は喫茶店兼スナックを営んでいた。朝早くから店内を清掃し、珈琲を入れ、店を開けた。ランチの時間には工場で働く労働者で賑わい、スナックに変身すると、深夜遅くまでカラオケの音が響いた。博昭は店の二階で暮らしていた。
ひとりっ子の博昭は、夜中に聞こえる下手な歌声に耐えられず、よく家から抜け出し、コンビニやゲームセンターで時間を潰した。寂しくはあったが、家にいるよりはマシだった。博昭にとって、家はうるさいだけのただの冷たい箱だった。
父と遊んだ記憶はほとんどない。仕事をしていないときの父の行動パターンは二つしかなかった。ギャンブル。絵を描く。
父の夢は絵描きとして成功することだった。だが、父の絵は幼い博昭から見てもお世辞にも上手だとは思えなかった。
父はお金が入るとギャンブルをするために街に出た。博昭もよくつきあわされた。競馬、競輪、競艇、パチンコ、マージャン……。父はありとあらゆるギャンブルに手を出し、まるで人生そのものをひっくり返すかのように賭け事に熱中した。
賭けに負けると父は不機嫌になった。しょっちゅう癇癪をおこしては母と喧嘩をした。口の達者な母に言い負かされそうになると、父は暴れた。
暴れ始めると制御が利かず、あらゆる物を壊しまくった。グラス、お皿、食器棚、窓ガラス。そして……。母と博昭。
父は母を殴った。母の腕を包丁で切りつけたこともある。血が噴き出ている母の髪をつかみ乱打する父の顔は、まるで悪鬼のように映った。父の止まらない暴力から母を守ろうと、博昭は必死で足にしがみついたが、その行為はまったくの無駄であった。
空いている足で思いっきり蹴り上げられた博昭の鼻は直角に曲がった。フローリングの床は血で真っ赤に染まったが、母は警察を呼ばなかった。病院には行ったが、事故ということで済まされた。
「博昭。誰にも言うたらあかんで」
かがみ込みながら母は言った。その言葉を聞いたとき、博昭ははじめて母に殺意をおぼえた。