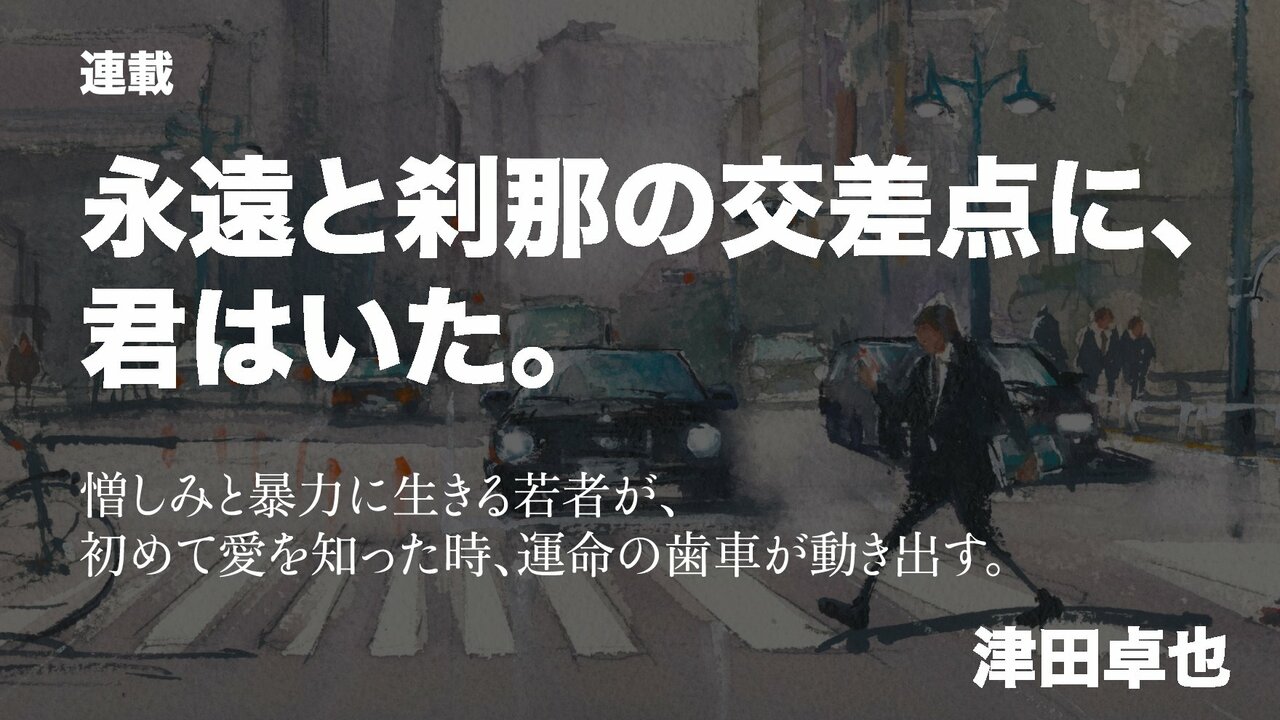第一章
1
「お誕生日おめでとう」と養父が言った。博昭は軽く頭を下げた。
特に嬉しくもなかったが、嫌でもなかった。親子で誕生日を祝うのは毎年の恒例であったし、何より父と議論をするのが好きだった。
「どや。三十六歳になった感想は?」と父が聞いてきた。
「プールの折り返し地点をターンし、水中から水面に出るような感じでしょうか。浮かび上がるというか。まあ、少しわくわくしています」
「そうか。彼女でもできたんか?」
「いえ」と博昭は答えた。
「いつまであの娘に義理立てをするつもりや?」
「別にそんなつもりは」と博昭は口を濁した。
父は黙っている。博昭もしばし沈黙する。父が彼女のことを話題に出すとは予想外であった。
「まあええ。今回のテーマは『愛』や」
「ほう」
父は議論好きだった。むかしより会う機会は少なくなったが、共同で会社経営をしている二人にとって、ディスカッションの場は年々重要性を増していた。
議論のテーマはいつも父が考えた。前回のテーマは『存在理由』。前々回は『戦争』。その前は『天皇制』であった。
「どや?」
「いいでしょう」
博昭は小さく頷いた。「真っ正面から愛を語ろうやないか」と父が言った。
過度の整形によって作られた顔は表情が読みとりづらいが、唇が微かに上部に引きつれているということは笑っているのだろう。父の、つまり風間の養子になって十六年になる。出会った頃は表情から感情を読みとることに苦労したが、さすがにいまではもう慣れた。
グレーで統一された無機質な部屋は、真夏だというのに寒々しさを感じる。テーブルを真ん中に挟んで、親子は対面になり腰掛けていた。テーブルの上にはグラスが二つ。その他には何もない空間に、空調の音だけが微かに響いている。
「博昭。愛ってなんや?」
また父が言った。博昭は考えた。そして静かな口調でこう答えた。
「愛という概念にはさまざまな捉え方がありますが、仏教における愛は慈悲にあたるかと思います。慈とは、すべての人々に深い愛情を持ち、安楽を与えるという意味であり、悲は、悩める人の苦しみを取り除いて、思いやること。
一方、キリスト教は、神の愛を説いた教えです。キリスト教では、神とは人間をはるかに超越した、大いなる存在であって、神の前ではすべての人は平等であり、罪深い存在であり、その罪は神の愛によって救われる。まあ、どちらも、どんな人にも救いの手を差し伸べている、という点では共通していますが……」