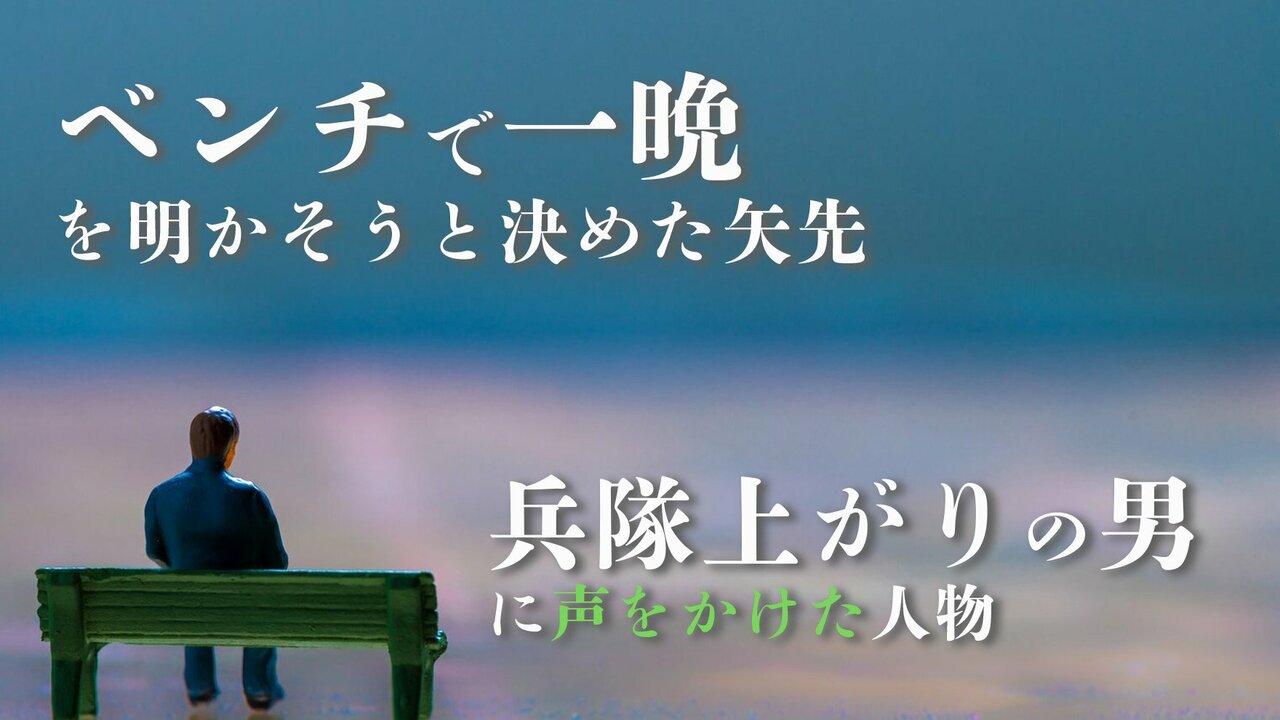一章 帰郷
「ギルバートじゃないか」
聞き覚えのある声が聞こえ近づいてきた。
「良かった……生きていたのか」
聞こえてきた声の主は俺が予想した人で間違いなかった。
「ライトか、生きていると信じていたぞ」
俺の一番の親友、ライトである。ライトは俺と同じベンチに座った。
センター国の徴兵制度は十八歳から五年間兵士になるように決められているが、大学へ進学する人もいるため三十歳までに兵士に志願すれば良いとされている。俺とライトは大学進学を選び、卒業後に一緒に兵士になることを約束した。つまり、ライトも同じく今日をもって自由の身になる。
「せっかく同時期に兵士を志願して、しかも同じ第一歩兵部隊の十班に選ばれたのに、ギルバート自ら移籍するなんて……」
開戦一か月前、俺たちの基地で教官からお互い「第一歩兵部隊十班」と聞かされていたのだ。こんな偶然は他にない。しかし俺は十班を離れ一班に所属することに決めたのだ。
「ここまで合わせてきたのに、はぐれちゃ裏切りじゃないか。僕に断りもしないで一班に行くなんて」
数秒まで俺が生きていたことを確認して安堵していたのに、ライトの顔は少しずつ険しくなる。
「一班に移籍する話を直接持ち込んできたのは本部のお偉いさん達だ。俺が魅せたあの活躍を聞いたら、誰でも俺を一班へ推薦するだろ」
俺は目をそらしながら話した。
「でも、断るくらいできたでしょ。危険で最も戦死者を出す一班を志願するのはどうかしているよ」
「優秀な第一歩兵部隊のさらに選ばれた者しか行けないところだぞ。悪くいうなよ」
「一班は所属するだけで名声と他班の倍近くの報酬を得られて、人生の勝ち組になる皆の憧れだから悪いとは思ってないよ。けど、死んでしまったら戦死者を数えるメーターが一つ上がるだけで何も残らないんだぞ」
「俺は絶対に死なない自信があったから引き受けた。ライトにもそのぐらいの自信はあったはずだ」開戦前に所属していた基地で俺とライトを超える身体能力を持つ人は教官も含めいなかった。
「それでも死の恐怖には勝てない。前線のさらに先陣を切るなんて」ライトは俺の行動に真っ向から反対してきた。他の人にいわれたら殴りにいくだろう。俺らは親友だからといって気を使うことは全くなく、自身の思いを貫き通す。それが親友という俺たちの認識である。
俺が反論しようと口を開ける前にライトの口が動いていた。
「でも全部過ぎたことだ。生きてくれればそれでいい」
「そうか……」
俺は何もいい返せなくなった。