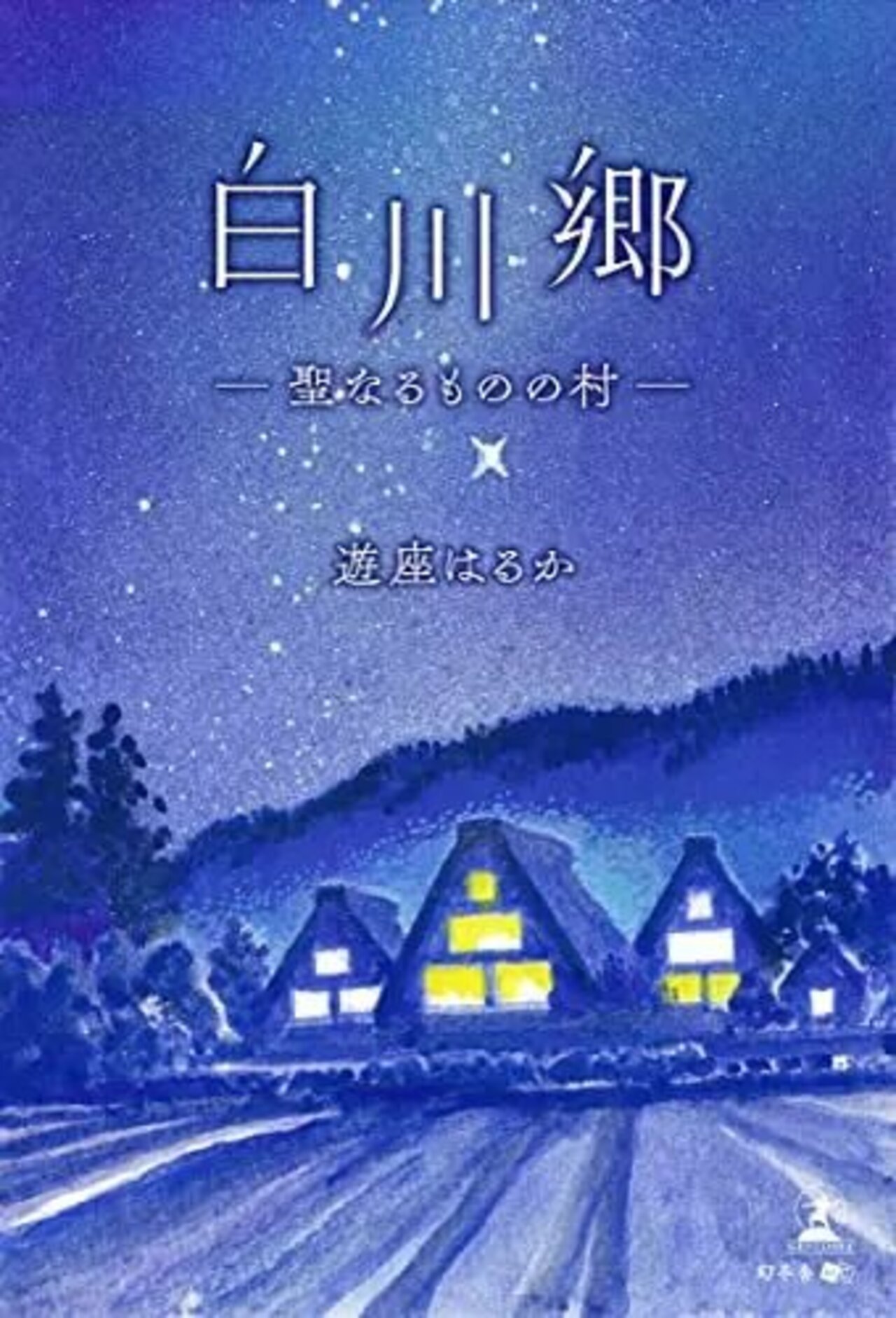4
次の日、小池に居酒屋ユキに行ったと篠原は話した。すると小池は、
「だしかん、だしかん、だしかん」
三度も叫んだ。篠原は雪乃に対する小池の誤解を解こうと思った。
「凄い美人だったけど、怪しくなかったですよ。恥ずかしがり屋だったけど。それだけ」
小池は大きくはっきり首を振った。
「もう、篠原さんも雪女に引っかかってまって。凄い美人って、いくつくらいやった?」
「三十才くらいですか。僕くらいかと」
言いながら篠原も妙な気がしてきた。確か、緑川は店が開いていればかかさず毎日、十五年近くも通い詰めているという話だった。今、三十才なら十五年前は十五才で中学生だ。ん? 篠原の考え込んだ顔を小池はあきれ返って見つめ、
「あの女は篠原さんのお母さんくらいの年齢やと思いますよ。店を開いた時、緑川さんと同い年やって聞いたで、今ではもう五十九才。魔女やで年を取らんのやさ。もう、行ってはだしかんよ」
そして小声で小池は何かつぶやいた。きっと
「いこいとる(狂っている)」
と言っているのだろうなと篠原は思った。
しかし篠原は居酒屋ユキに通い始めてしまった。雪乃の魔術に引っかかったのではなく、緑川や常連の話を聞きたかったからだ。
緑川とは、その日の原稿内容とか翌日の打ち合わせなど日常的な話はもちろんだが、緑川が飛騨支局に来るまでの、世界中の山の話や北海道支局時代のヒグマや野生動物の取材の話など、聞いているだけでワクワクするのだった。さらに緑川は飛騨のことも端から端まで何でも知っていた。それは飛騨支局在任十五年間の取材の結果だとは思ったが、どの分野も専門家に引けを取らないほどの博識で、そういう話はどれも勉強になった。
事務の小池が言うような、居酒屋のママに惚れているだけで、十五年間も飛騨支局に居座っているとはどうしても思えなかった。確かにほぼ毎日、午後六時の開店と同時にユキに入るのだから、入り浸っているとも言えた。でも店の中の緑川は、店の隅で原稿を書いている時もあるし、総局や本社のファックスを店の電話で受けたり送ったりしているし、取材相手と飲みながら話し込んでいる時もあって、仕事場を支局からユキに移動しただけのように見えた。
しかも具合がよいことには、お客はいつも少なくて、たまに来るのは緑川の知り合いばかりなので、支局よりちょっと賑やかな仕事場、という感じだった。店の客の緑川の知り合いたちも、酒を飲みに来ると言うより、緑川や居酒屋にいる顔見知り同士で話したいと思う人たちがほとんどだった。
その顔見知り同士というのが、北アルプスの登山家たち、画家や版画家や写真家たち、時には県庁の役人、銀行や信用金庫に勤めている人たち、あるいは飛騨地方の発掘調査をしている考古学者や歴史学者たちなど多士済々で、緑川はカウンター席の端っこで聞き役になっているだけなのだが、何しろ聞き上手で、誰もが機嫌よく本音で話し込み、普通の取材の何倍も濃い話を聞けるのだった。
当然、その緑川の後ろに座っている篠原もいろいろな話が聞けて、一人で夜の支局にいるよりずっと充実した時間を過ごせるのだった。