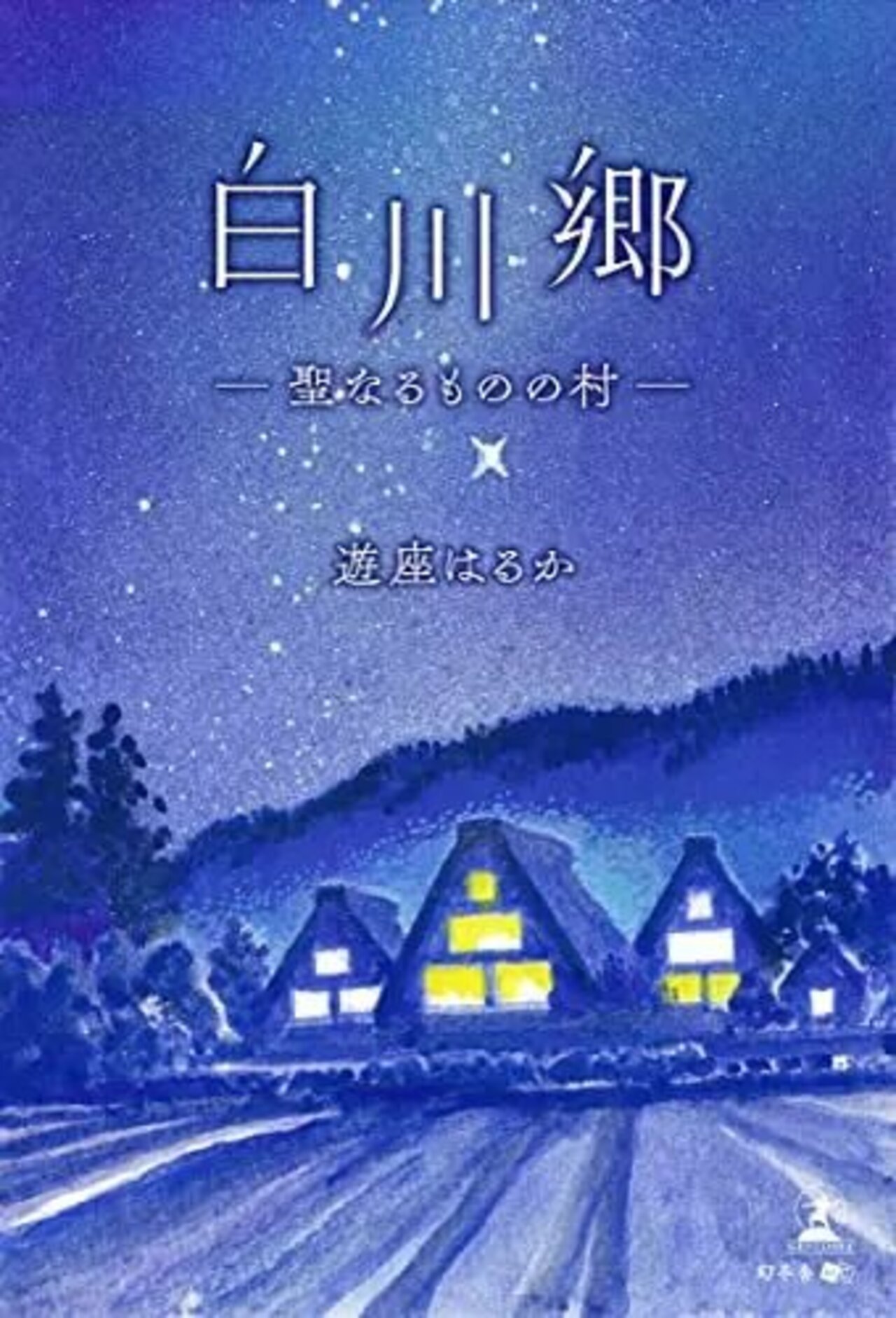第一章 二〇〇七年、飛騨支局勤務
3
ちょうどその時、厨房の奥から白っぽい着物を着た女の人が、正月の伊達巻のような大きな玉子焼きを、篠原のところに持ってきた。緑川は、
「篠原君、この人がこの店のオーナー。野沢雪乃さん」
篠原にママを紹介した。篠原は一目見るなり驚いた。そこには、事務の小池が言っていた通りの「雪女」がいたのだった。着ている白地の着物よりも、もっと真っ白な透き通るような肌、切れ長の大きな目、花びらのような赤い唇、半襟からのぞくなよやかな首、そして何よりも床まで届くほどの長い長い真っすぐな黒髪。篠原は半ば口を開けて、雪女に見入っていた。その顔を面白そうに眺めながら緑川は、
「雪ちゃん、この人が篠原准一君。今度、支局に来てくれた記者だよ。出身は生まれも育ちも東京で、杉並区だって。雪ちゃんは中野だったから、近いね」
と、篠原を雪乃に紹介した。けれど雪乃は何も聞こえなかったように、皿をカウンターに置くとそのまま厨房に戻ってしまった。それはそれで、いよいよ不思議な感じで、篠原は雪乃が消えた厨房を座席から腰を浮かせて見つめるのだった。そんな篠原に、
「いや、ごめん。雪ちゃんは、恥ずかしがり屋で、初めての人には挨拶とか出来ないんだよ。そのうちね、慣れてくると、話すこともあるから」
緑川はまるで身内の非礼を詫びるように言うのだった。今度は篠原が雪乃について詳しく聞きたいと思ったが、緑川は、
「お、十時だ。そろそろゲラが入ってくるな。戻ろうか」
話を変えて、椅子から立ち上がってしまった。そして、
「今日はもう、客は来ないだろうから、店も仕舞いにしよう。時江さん、戸締まり、しっかりね」
まるで店主のような口調で言うのだった。しかも店を出る時、看板のランプの明かりを慣れた手つきで消していた。篠原は、自分の話ばかり夢中でしてしまったが、緑川と雪乃はどんな関係なのだろうかと改めて不思議に思うのだった。店の外は、あれほど吹き荒れていた吹雪は止んで、高山らしい、しっとりと濡れたような漆黒の闇が広がっていた。