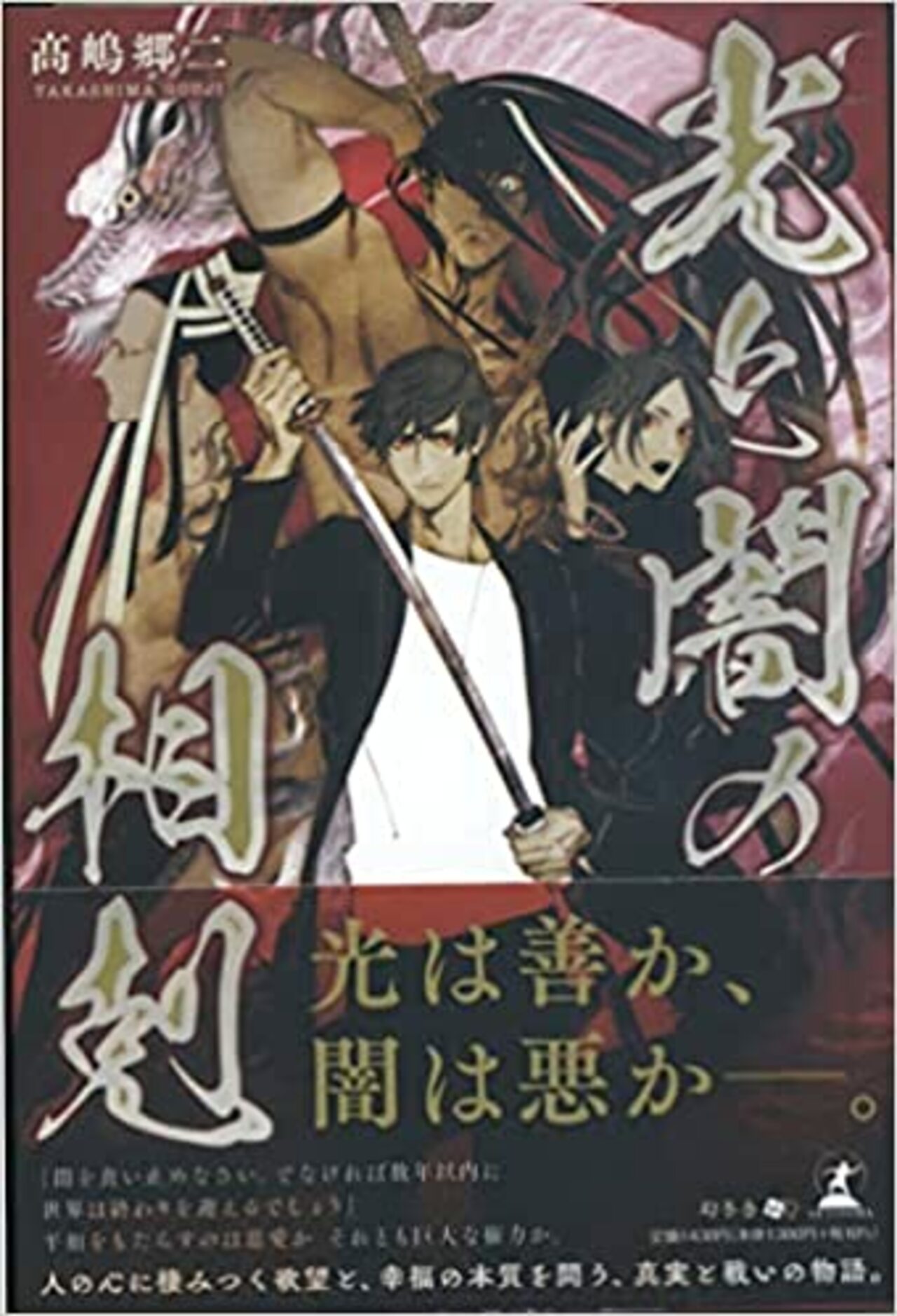英良は老人への言葉に詰まった。……上手く切り返せず苦悶の表情を浮かべる。握りしめた両掌に汗がにじんでくる。そこには蝋ろう燭そくが置かれていた。蝋燭の炎はいくつかに姿を変える。意志を持っている生き物のように老人を肯定すると縦に長く伸び、そうでない時は元に戻ったりと……。
炎は細長く伸び煤すすを出した。老人が言った後に英良は過度の精神的重圧と極度の圧迫感から解放され、心中にあったどんよりしたもやもや感から解放されほっとする。その瞬間、老人は英良の心中を見抜いて言う。
「分かってはおらぬな。己は私にこう言った。光が存在する所に闇が存在すると。ならば、闇を滅し、光だけになった時、何が起こる。考えたことはあるのか。その先に何があるのか。己は考えたことはあるか?」
平和があると、英良は答える。
「平和が来るか……一時的にはな。しかし、言っただろう。光あれば闇も存在すると。本来、人間は光と闇の両端を宿す感情なる力の空間に置かれている。理解はしているはずだ。感情には正の感情があり負の感情がある。闘いをなくすこと、即ち人が人でなくならなければならない。この意味が分かるか。己にはそれができるか?」
英良は分かると、答える。
「しかし、それができぬから皆、いがみ合い傷つけ合う。ならば聞くが、光の者には負の感情はないのか。闇の者には正の感情はないのか。そのような深きこと、考えたことはあるか答えてみよ」
光と闇は相反するもの。あくまでも闇と英良が答えると
「それは、己の思い違いではないのか。何故なら、現に……いや、止めておこう。ならば、闇同士が助け合うことはないか。闇は力が純粋な分、強き意志を持っていないか。ならば、堕天とはどのような状態だ?」
光は闇に与くみするものではないと、英良は答える。