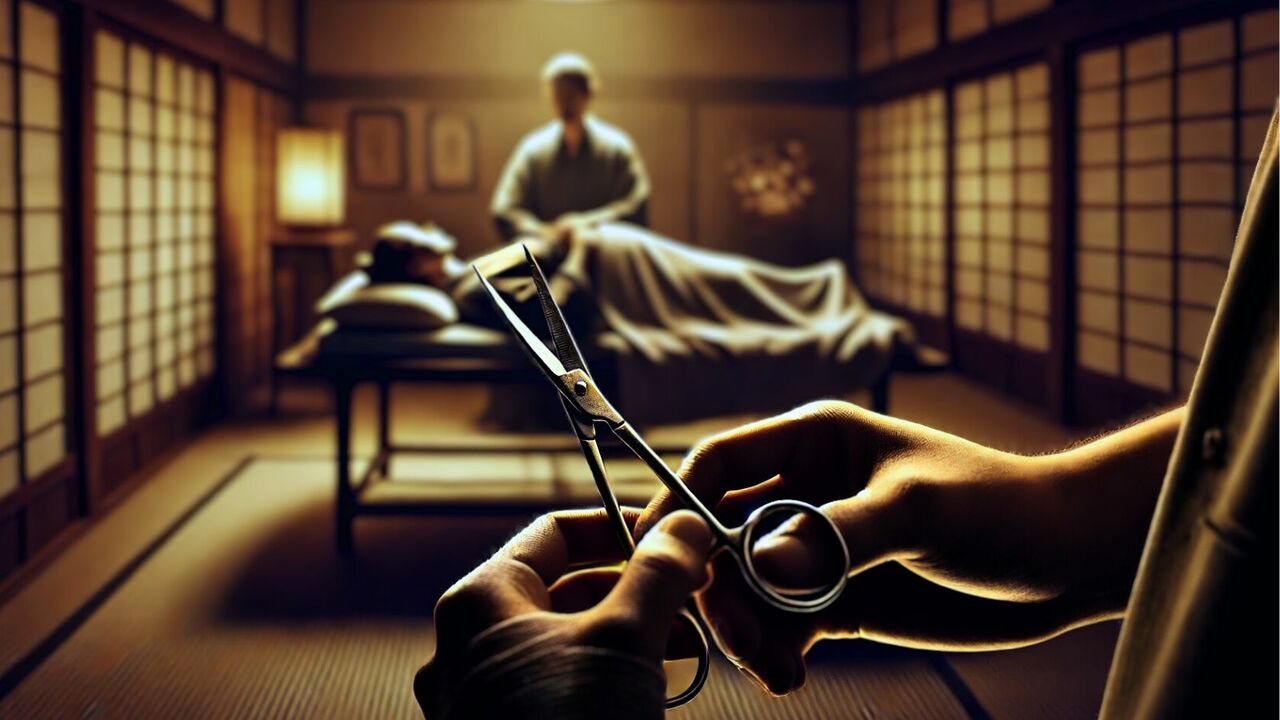序章
明治二十一年(西暦一八八八年)十月
大御門は箸を止め、眉根を寄せた。
「子供の頃から、おまえは本当に無鉄砲だったからな。大人になっても、あまり変わってないようだ……」
ため息をつきながら、大御門は呆れた顔をした。
それには万条自身も、思い当たることがあった。京都がまだ、維新の動乱に巻き込まれていない、のどかな頃だった。
ある日、京都御所に隣接する飛鳥井家の屋敷で、蹴鞠の会が催された。
蹴鞠は公家の嗜みの一つで、飛鳥井家の家職でもあった。万条もそれが得意で、大御門と一緒に子供の部に参加したのだ。
だが、張り切って準備体操をしているときだった。
ふと見れば、ひときわ身体の大きい少年が、一人混じっていた。明らかに体力差がありそうで、しかもそいつは、終始にやにやと笑っていた。
もやもやしたものを感じながら、万条は蹴鞠の輪に入った。
すると、すぐにわかった。その少年は、とんでもない悪ガキだったのだ。
競技が始まったとたん、そいつはたちまち本性を現した。小さな子の蹴りを邪魔したり、わざと足を引っかけ、転んだ姿をあざ笑ったりした。
自分が失敗したときには、何事もなかったかのように誤魔化すか、他の少年に責任をなすりつけ、罵声を浴びせかけた。目に余る行状に、子供たちはみな、地団駄を踏んで悔しがっていた。
だが諦めるほかなかった。体格の違いは歴然で、しかも彼の家格は、最上位の五摂家の一つだったからだ。
それをいいことに、そいつは勝手気ままな態度を続けた。まさに悪徳公卿そのもので、万条はしだいにそれが許せなくなってきた。
こいつは将来、きっと帝を蔑ろにし、御所を我が物顔で闊歩するだろう──。
子供ながらに怒りに震えると、万条は鞠を手にしたまま、その少年の正面に立ち塞がった。そして、こう啖呵を切ったのだ。
「卑怯者め、許さん。正々堂々、我と勝負しろ!」
当初、少年は小馬鹿にしたように、万条を見下していた。
一方、万条の父はそれを見て、血相を変えた。
この時代、家格の違いは絶対だったからだ。大急ぎで息子を引き離そうとしたが、そのときだった。
立会人を務めていた親王殿下が、意外な行動をとった。貴顕の顔をにやにやさせながら、「やらせてみよ」と、のたまったのだ。
こういう場合、公家は遊び心が勝ってしまうものらしい。所詮は子供の喧嘩にすぎず、周囲の慌てふためく様子がなんとも滑稽だった。大人たちの間も、一瞬空気が和んだ。
しかし万条は、あくまで本気だった。