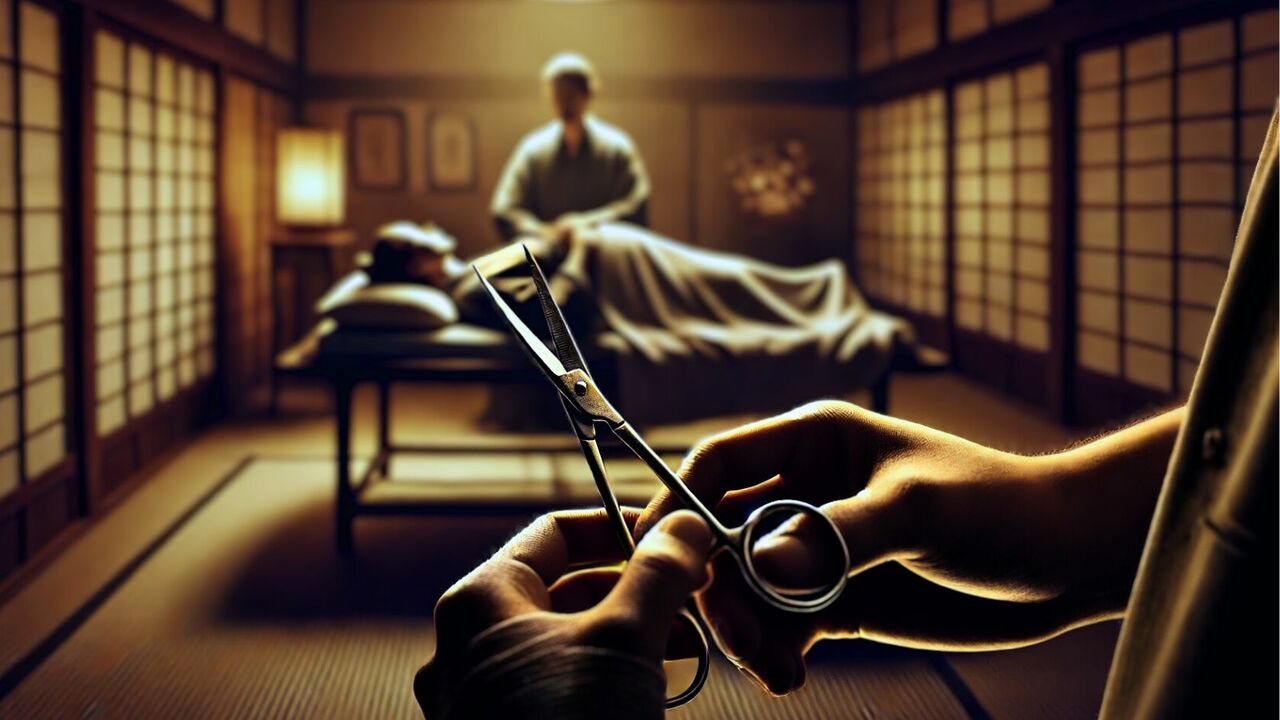序章
明治二十一年(西暦一八八八年)十月
つい最近、明治政府は医学校の国立化を強行するため、府県の税金を投入することを禁止した。そのため、どこの医学校も、廃校や統合の危機が訪れていた。
六年前、甲種医学校に昇格したばかりの京都療病院医学校も同様だった。万条が押しかけると、衛生局の木っ端役人は、いきなり現れた珍客を門前払いしようとした。万条はとことん粘り、なんとか上司との面会を勝ち取った。そして大演説をぶったものの、結局体よく追い返されてしまった。
作戦を立て直すため、いったん引き下がることにしたが、あいにくその日、宿を決めていなかった。後先考えず、勢いだけで飛び出してきたせいだった。あてもなく歩いていると、岩倉具視が落ちたという四ッ谷濠を通りがかった。明治七年、喰い違いの変で襲撃されたときのことだ。
するとそのとき、大御門の顔がふと、万条の頭に浮かんだ。やはり頼れるのは、幼なじみだけだった。泊めてもらおうと、万条は大御門の家に行ってみた。しかし夜に、先約が入っていた。後輩で、先月ドイツから帰国したばかりの、森 林太郎なる人物との会食が予定されているとのことだった。
森 林太郎といえば、かつて大御門からの手紙で、名前を聞いたことがあった。旧知の仲のような気がしなくもなかった。
「メシは大勢で食う方が美味い──」
万条は大御門をそう言いくるめると、ちゃっかりその宴席に加わったのだ。大御門は鍋に手を伸ばしながら、あっさりと万条の頼みに応えてくれた。
「それなら、元老院の長与専斎先生を紹介してやるから、相談すればいい」
「え、長与先生……」
万条はぎょっとした。長与は元東京医学校の校長で、今は衛生局長と元老院議官を務めていた。大坂で緒方洪庵の適塾を出た後、幕末に長崎で学び、明治四年には岩倉使節団の一員として欧米を視察したこともあった。いわば日本の医学界の元締めのような人物だったが、万条が複雑な表情をしていると、大御門は怪訝な顔で訊いてきた。
「どうした? 何か問題でもあるのか」
「いや、何でもない……」
「今晩のうちに推薦状を書いてやるから、持って行くといい」
大御門は早々に話を切り上げ、また美味そうに肉を頰張った。
「ところで、少し前の話だが、同志社の新島襄先生が、井上馨大臣の家で倒れられたのを聞いたか?」
肉を飲み込んだ後、大御門が思い出したように言った。万条は慌てて訊き返した。
「本当か」