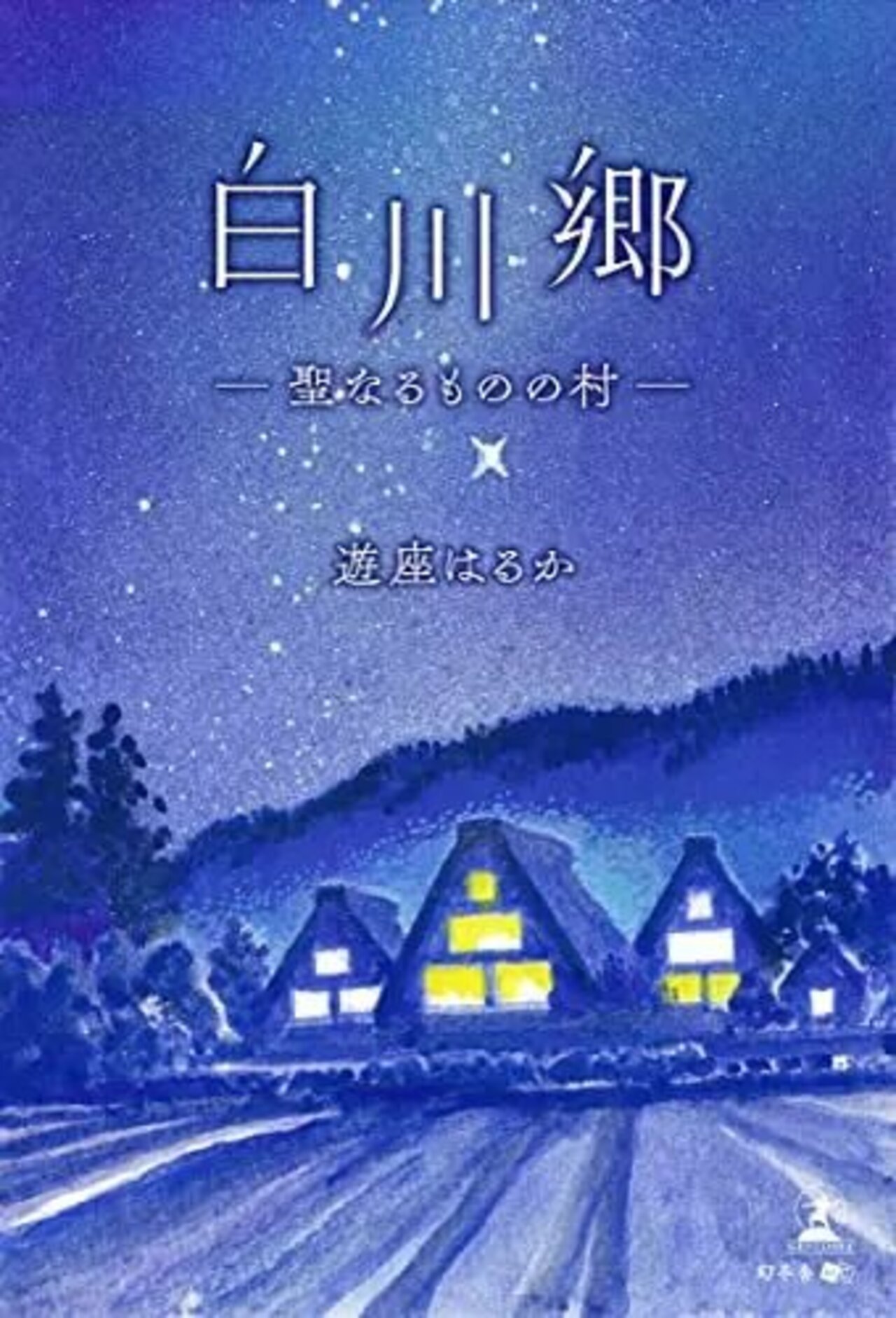篠原が確認する一瞬前に、
「あれ、篠原君じゃないか。どうして、ここがわかったの?さすがだねえ」
緑川だった。篠原はあわてた。まるで、小池の話を確かめようと思って来たと言われているようで心外だった。
「いや、違うんです。たまたま、道に迷って」
ここに来るまでの事情を説明し始めると、入口のドアから雪かきの大きなシャベルを持った太ったお婆さんが入ってきて、
「あれえ、支局長さん、気が付かなかったで。あれ、若様もおんさったかなあ。これは、これは、うたていこっちゃ(申し訳ない)」
元気な張りのある声で言った。お婆さんはシャベルを片付けて厨房に飛び込むと、酒の肴の入った小皿や箸や手拭きなど、すばやくカウンター席に並べて、
「支局長さんは、いつものホットワインかな」
笑いながら言って、篠原に向かっては何を飲むかと聞いてくれた。篠原はようやく温かい物にありつけそうでホッとした。
「ボクも、ホットワインを」
篠原がそう言うと、緑川は微笑んだ。そしてお婆さんに向かって、
「時江さん、この御人はやさ、ようやくうちの支局に来てくれた東京本社の精鋭やさ。篠原准一君。よろしうなあ」
時江に篠原を紹介した。そして、
「時江さんは、この店の、板長で総支配人。買い出しも料理も接客も、みんな時江さんがやっている」
篠原に時江を紹介した。時江は、
「あれ、支局長さん、こーわいわー(恥ずかしい)。なんも、わたしなど、間に合わん(役に立たない)やさ」
とんでもない、という風に、手を顔の前で振るのだった。時江は、太った身体に紺色の作務衣をゆったりと着ていて総白髪を短く顎の辺りで切り揃えていた。色白の丸顔、目じりの下がった一重の目が温かく、どっしりと安定感があった。なるほど、この人ならば、人里離れた店でも仕切って行けるだろうと篠原は思った。
しかし、この安定感のあるお婆さんがこの居酒屋のママなのか?妖しい雪女とは程遠い感じだ、と思ったら、
「そしてこの店のオーナーのママさんは、あの人だよ」
緑川が厨房の奥を指さした。あの、白い着物を着た女の人が、最初見た時のまま、身動ぎもせずに座っているのが見えるのだった。もっとよく見ようと椅子から背伸びすると、
「玉子焼きだけは、ママの手作りだから、注文するといいよ。ママが持ってきてくれる」
小声で教えてくれた。もちろん篠原は注文した。緑川は、
「さあ、じゃんじゃん食べて飲もうよ。オレ、篠原君が着任した時から、二人で飲みたいって思っていたんだ。今日は、とことん飲もう、な」と言うのだった。