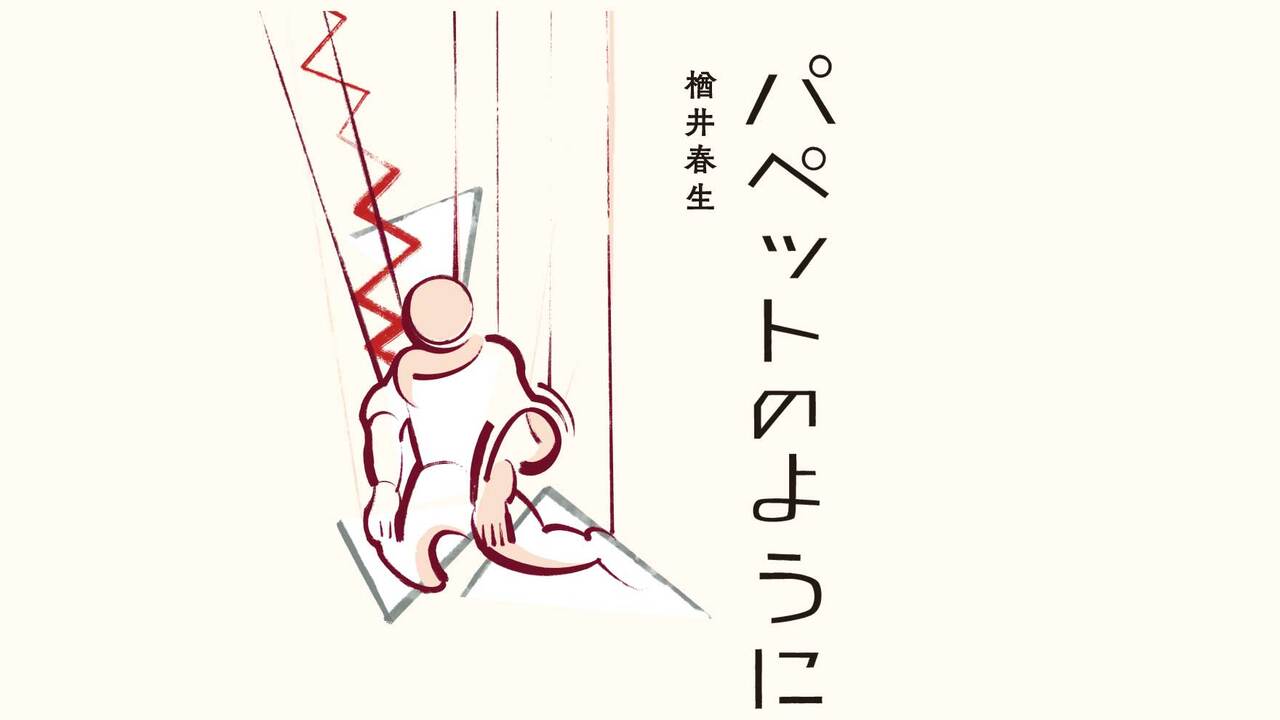一部 ボートショーは踊る
四
「これから、魚群探知機の市場が安いソナーを求めて動くと私は読んでいるだけです」
「ヨーロッパではご存じの通りノルウェーのシマール社がソナーの市場を席巻している。私はシマール社のウルマン社長とは懇意な間柄だ。彼に聞いてみてあげてもいい」
「ソナーといっても色々あります。シマール社のソナーはその中でも最高級の大型漁船を対象にしたオムニソナーが主体です。私はまずレジャーボートにも取り付けられるような安い簡易型のサーチライトソナーを考えています。従来の魚探で飽き足らないボートオーナーが大勢いると思うんですが。
それから、多分、セクターソナーを手がけることになる。しかし、三百六十度のオムニソナーに手をつけるには更にたくさんの経験を積んでからということになります」
「面白い着想だね。日本人らしい、緻密な発想だ」
ジムはにやりとした。
「シマールとバッティングしないソナーだったら彼らも欲しがるだろう。せいぜい日本の富良野電気辺りとの競争になるんだろうね」
「富良野電気は今では日本の業界では伝説の企業になっています。輸出に目をつけ、シマールのコピー製品を世界中に売り始めたのが切っ掛けで急成長した。その後を追うことは私のプライドに関わってとても気が引けるのですが」
「いや、そうじゃないだろう」
ジムはいたずらっぽい表情を浮かべて俊夫を見る。
「用心したまえよ。それが何であれ、怨念の商品に金をかけ、売り出すのは容易ではないよ」
「怨念の商品」
俊夫は首を傾げた。
「だって、君はこれに賭けるといった。何故かね」
「ただ商売になると考えた。それだけのことですよ」
「そうかね、それだけかね。怨念にはそれなりに熟成する時間が必要だ。それは人によってまた怨念の対象によってその時間は違ってくる。君の怨念の対象は何だろう。何時から、どうして君はソナーやレーダーを目指したのかね」
「勘違いしないでください。私はこの業界に三十年いて業界の隅々まで知り尽くしている。それで安価なソナーに白羽の矢を立てた。それだけのことですよ」
なおもジムの表情が崩れる。彼が俊夫の言葉に納得していないことは確かだ。
「本当にそれだけかね。誰かから聞いたのか、それとも、ものの本によるものかは忘れたが、日本人はレーダーとソナーの開発が遅れた為に第二次世界大戦に負けたと信じているらしい。まあ私は一ビジネスマンだからそんなことはどうでもよい。とにかく、君の意気込みが気に入った。協力するよ。イギリスだけを任せたいのかね。それともヨーロッパ全域を私と組んで売り込みたいのかね。当社のコンパスで私はヨーロッパ全域に市場を持っているよ」
「当面イギリスだけでスタートしていただければ。その実績次第で次のステップを考えるということでは」
「いいだろう」
ジムは頷いた。
「なるほど分かった。君と率直な話し合いができて楽しかった。どうやら我々は波長が合いそうだ。どういう周波数で行くかゆっくり考えよう」
ジムはそう話を締めくくった。