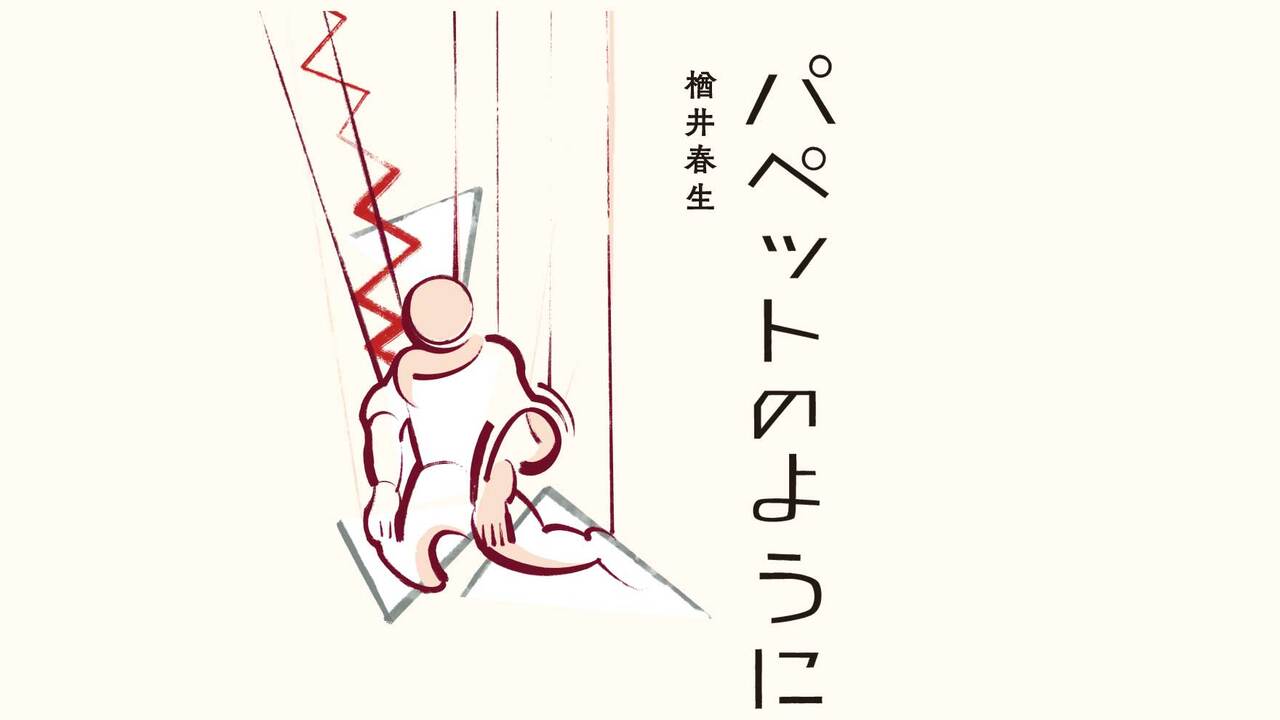一部 ボートショーは踊る
四
ロンドンのボートショーでジムのあのパペットの踊りのワンマンショーを見てから六カ月余り経ったその年の夏、俊夫はソナーの開発の進展に伴い新たに市場調査の為にヨーロッパを回る計画を再び立てた。出張先の日程を練っているうちに、ふと、またジムに会ってみたいという気になった。
あのパペットの踊りのことは俊夫の心に何時までも刻み込まれたままになっていて、時折俊夫はふっとジムのあの時の絶妙な踊りの仕草を思い浮かべ、にやりと頬を緩める。そのにやりは、しかし、ふいと頬に止まったまま動かなくなる。あのパペットの踊りの仕草は、ジム自身も気付かぬままに、俊夫の中に潜ひそんでいる何か得体の知れない衝動を探り当てたものではなかったか。
あの日、あの瞬間にも俊夫は本能的にそう感じ背筋を凍らせたのだった。ショーの最終日の弛緩した雰囲気、笑い転げる日本人たち、そして遠くで奇異な眼差しでその騒ぎに目を注ぐ、他の小間の連中たちの記憶は確かに薄れていったが、反対にジムのあのパペットのように、ぎくしゃくとした身振りで踊り跳ねる姿は、ジムの顔の表情の変化と共に、記憶の中で生き生きと蘇よみがえり、それらには肉付けが施されていく。
あの場所で笑い転げていた観衆の誰一人、多分ジム自身ですら、俊夫の心にそんな変化が訪れるなど思いもよらなかったろうし、期待もしなかったろう。誰にとってもそれは雑然と過ぎていく日々の中での一時の出来事に過ぎなかった筈だ。
そんな心の背景があって、俊夫はイギリスのドーセットの片田舎のプールという町にジムを訪ねる気になったのだ。思い立つとすぐにメールを送ってジムと連絡を取った。
『歓迎します。会社の近くにホテルの予約を入れておきます』
そんなジムからのメールの返事はとても温かいムードに溢れていた。